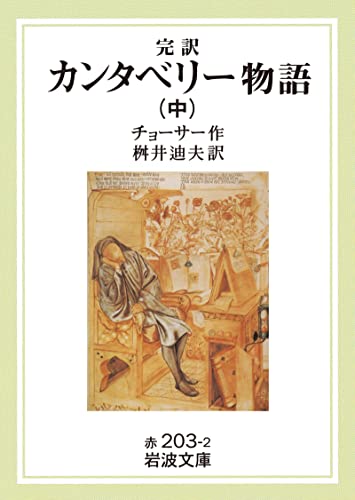カンタベリー物語 免罪符売りの話/チョーサー
免罪符売りの話の序
医者と免罪符売りに対する宿の主人の言葉
宿の主人は、先ほどの医者の話に悲憤慷慨する。そりゃそうだ。これまでで最も救いのない話でしたからね。かなり動揺しており、これまでで恐らく最長の長台詞でその感情を語る。そしてすぐに次の話、それも楽しい話を聞かなければならないと言い、冗談話をしてくれと免罪符売りを指名する。免罪符売りは一杯飲んだ後ならと受諾するが、上品な人たちが抗議の声を叫ぶ。下卑た話はやめて、何か教訓話を所望するのだった。免罪符売りはわかったと言って、飲んでいる最中に考えないといけないと言う。
宿場なのか単純に街なのか不明だが、一行には食事休憩が近付いており、免罪符売りは食事の後に話をすることになるようだ。
免罪符売りの話の序ここに続く
免罪符売りは、自分が教会で説教をする外題は常に同じ、「すべての悪の根は金銭を愛することにあり」(『テモテへの手紙』第六章)であり、全部宙で覚えているという。話の内容も固定化されており、自分がどこから来たかを述べて、教皇の勅書を全て見せる。その後に、教皇・枢機卿・大司教・司教らの免罪符を見せて、ラテン語を交えて話に風味を添える。聖なるユダヤ人の羊の肩の骨も持っており、それを見せながら骨の効能について話す。そして罪について警告し、免罪符を売り込むのだ。
免罪符売りは言明する。自分の意図は単に儲けることであって、罪を矯正することではないと。説教はしばしば悪い意図の元におこなわるとも悪びれず。
そして、自分がやっている悪徳と同じだからこそ、自分は「すべての悪の根は金銭を愛することにあり」と説教することができるのだと居直る。そして彼は説教で、遠い昔の古い物語をよく例にとる。無知な人は昔話が好きだからだ。免罪符売りは、自分が貧乏暮らしをするのは真っ平御免だと嘯く。免罪符売りは、その金儲けのための説教に使っていた話をここでするという。
免罪符売りの話ここに始まる。
フランドル地方で、若者の一団が、飲めや歌えの大騒ぎをやっていた。暴飲暴食に好色の炎、まさしく悪魔の手先といった風情である。この後、免罪符売りはストーリーから離れて、酒により色事の罪を犯した昔の有名人とそのエピソードを何人も紹介する。博打の話や、偽りの誓いの話も同じようにする。その後、免罪符売りは元の話に戻って来る。
三人の無頼者*1は、朝六時のずっと前から居酒屋にたむろして酒を飲んでいた。そこに墓に運ばれていく途中の死体が通りかかる。無頼者の一人がこの死体が誰かと居酒屋の召使の男の子に聞くと、その子は、死神と呼ばれる殺し屋に昨晩殺された盗っ人だと教えてくれた。この際、男の子は死体の主を「あなたの旧い仲間だった方ですよ」などと言う。お前も盗っ人だよなと言っているようなもので、結構度胸あるなこの子。死神はここのところの疫病*2の間に千人もの人を殺したという。男の子の話は居酒屋の主人も本当だと請け合う。そして、死神の住処は、一マイル以上離れた大きな村の近くにあると推定する。男の子も主人も、死神には気を付けた方が良いと助言してくれる。
だが、無頼の徒は、そんな奴など何するものぞと、三人で力を合わせて死神を殺してやろうと神かけて言う。三人は固く誓いを交わし、死神の住処を探しに向かう。だが彼らは、半マイルも行かない内に貧しそうな老人に出会って調子が狂い始める。老人は彼らに、何だってそんなに長く生きているのかと絡まれて、死神すら自分を殺してくれないと嘆く。老人は、老人に危害を加えないよう忠告するが、三人組は、お前は死神の話をした、だからお前は奴の回し者だと一層絡み始めた。ちょっと無理筋では?と思うがいちゃ文とはこのようなものであろう。老人は彼らに、死神が茂みの中の木の下にいると言う。言う通りに木の下にやってきた三人組は、そこでフロリン金貨を山と発見する。
ただ三人組は、自分たちのような人間が大金を持って移動すると怪しまれることを自覚しており、適当な保管場所に運ぶのは日中を避けて夜にすべきと決める。そして籤で、街に戻りパンとワインを持って戻って来る人間を選ぶ。それは、最も若い者になった。
さて木の場所に残った二人は、二人で協力して、今いない若い奴を刺し殺して、宝を山分けすることに合意する。他方、街に戻った若い男は、他の二人を毒殺して宝を独り占めすべく、偽りの目的を述べて薬屋から毒をせしめて、ワインに混入させる。そして、若い男が他の二人の元に戻ると、二人は若い男を計画通り殺害。そして若い男が持って来たワインで祝杯を上げて、二人とも毒で死んでしまう。
ここまでをいつもの調子で語り終えた免罪符売りは、ここからもいつも通り話す。つまり、巡礼団に免罪符を売りつけようとする。宿の主人は激怒、免罪符売りに実質的な罵声を浴びせる。免罪符売りは物も言えないぐらい激怒、一触即発となるが、他の巡礼団は笑い、騎士が仲介して、宿の主人と免罪符売りは接吻して和解する。馬に乗り旅は続く。
話の流れでいつも通り免罪符の商売を始めようとするのには笑った。三人の無頼の徒のことを具体的に語っている部分はともかく、その前後は非常に説教臭い。ここはリアリティがありそうだ。死神と老人の正体が不明なまま終わるのは、良い意味で気持ち悪くて良かった。そしてやっぱり、当時はフランスとの距離感が近いのだと感じられます。この話も、普通にフランドル地方が舞台ですからね。百年戦争はまだ続いている……。
カンタベリー物語 医者の物語/チョーサー
ここに医者の物語続く。
序がなく、いきなり医者が話を始める。前の郷士の物語にも、次が医者であるとの示唆は一切ない。本当にいきなり、本題の話が始まるのだ。
ティトゥス・リヴィウスの語った話だとのみ前置きがある。昔ヴィルジニウスと呼ばれる騎士がいた。彼女のたった一人の子は、美しい14歳の娘だった。賢く、気立ても良く、優しい娘だった。宴会・酒盛り・舞踏会のような、同世代の仲間が馬鹿なことをやりかねない場所にはあまり行かず仮病を使った。
医者は、子供を拙速に大人びさせ、厚かましいものにするのは危険と説く。ここから脱線し、女性家庭教師が雇われている理由は、ずっと道徳堅固であったか、かつて堕落し恋の手練手管を知って悪行を金輪際やめたか、いずれかだと言う。以前は鹿盗人だった者は森の管理が上手い。だがそういう人は、悪徳に戻ることができる。また、親たるものちゃんと子を責任をもって監督しなければならない。叱るのも怠る羊飼いのもとでは、狼が多くの羊を引き裂く。ごもっともながら説教臭いです。しかも、私の見たところ、この話には関係ありそうで実は全く関係がない。叱るとか監督とかそんなもんじゃないからなあ……。
さてこの14歳の美しい娘は、この地方を治めていた裁判官アピウスに見初められてしまう。ただ、無理矢理彼女を奪うようなことをすると、彼女や父親の味方が黙っていないのは確実なので、アピウスは、仲間のクラウディウスと謀を巡らす。クラウディウスはヴィルジニウスに対して、訴えを起こした。その訴えとは、「自分の奴隷を、年端も行かない内にヴィルジニウスが奪って行った、返還しろ」というものだった。そう、ヴィルジニウスの娘とされる人物が、実は自分の奴隷だという主張である。そしてアピウスは、ヴィルジニウスがまだ一言も主張していないのに、奴隷を返還するよう判決を下した。ヴィルジニウスははめられたことを悟るが、どうしようもない。帰宅して、彼は娘に事情を説明し、死と辱めの二択を迫る。娘は嘆き悲しむ。
「やさしいお父様、わたしは死ななければならないのでしょうか。なんの恩寵もないのでしょうか。なんの救いもないのでしょうか」
「なにもないのだ、本当に、愛するわしの娘よ」
一旦気絶し、そこから気を取り戻した彼女は、処女のまま死ぬ定めを感謝して、父に死を与えるよう乞い、また気絶する。父は娘の首を切り落とし、髪を掴んで、それを裁判官アピウスに見せに行った。
アピウスは、ヴィルジニウスを捕まえて縛り首にするよう命じたが、ブチ切れた市民が裁判所に雪崩れ込んで来て、逆に捕まってしまう。アピウスが好色なのは有名で、クラウディウスの訴訟もアピウスの仕込みだと疑われてしまっていたのだ。アピウスは獄中で自殺し、クラウディウスも絞首刑を宣告された後、ヴィルジニウスの請願によって追放刑に減刑された。
医者が「罪を捨てなさい(=人が罪を犯せなくなってから、つまり死んでからでは後悔しても遅い)」と忠告して話は終わる。
『カンタベリー物語』、既に過半を過ぎているが、ここに来て救いのない話が来ました。ヴィルジニウス父娘は本当に大変な目に遭った。わずか14歳でこんな形で人生を終えることになろうとは。愛する娘を殺し、首を持って歩かねばならないとは。最後に懲悪だけはされたが、勧善は全くされていない。そしてこの話からこの教訓を出してくる医者の考えがよくわからない。14世紀人ならすんなり呑み込めたのだろうか。敬虔なキリスト教徒なら理解可能なのだろうか。どうなんでしょう。
ところで、恐らくはローマ帝国期であろうこの話にも、遠慮なく騎士がいますね。「騎士の物語」でも、恐らくは古代ギリシャ時代なのに騎士がぞろぞろ出て来ていました。中世期、「騎士」とは何だと思われていたのでしょうか。それともこの時代の情報量だと、異なる社会制度が想像しづらいのかしら。
カンタベリー物語 郷士の物語/チョーサー
郷士の物語の序
郷士は、古のブルターニュの詩歌を披露すると言う。ただし、額がないので言葉が野卑だし修辞もちゃんとしていないと断る。百年戦争の最中の当時のイングランドにおいて、フランスは今以上に心理的距離が近く、人の往来もカジュアルに行われていたのだろうか。
郷士の物語ここに始まる。
ブルターニュと呼ばれるアルモニカの国にいた一人の騎士、カイルドのアルヴェラーグスは、ドリゲンに恋をし、ドリゲンもそれを受け容れ、結婚した。1年以上新婚生活を謳歌した二人だったが、次の1~2年間、アルヴェラーグスはブリテンに出かけてそこに留まった。ドリゲンは悲しみに沈むが、夫からやっと、そろそろ帰るとの報せを受ける。彼女の友人たちは、気晴らしに、ドリゲンを海の近くへ散歩へ連れ出す。しかしドリゲンは、船を見ては夫が乗った船ではないと嘆き、海から顔を出す岩を見て、船を壊す岩があるのは恐ろしいと泣いて、神に祈る。夫がそろそろ帰って来るというのに、心配性が過ぎるのでは? 情緒不安定になってない? 大丈夫?
さて近習の一人アウレリウスは、この美しい人妻ドリゲンに惚れてしまっていた。胸の内を彼女に打ち明けはしないまま悶々と過ごし、ある日、とうとう告白してしまう。ドリゲンは冷静ににべもなく断るが、戯れで、「海の岩を全部取り除いたなら愛する」と全てにおいて誓ってしまう。断りが本当ににべもないので、戯れの誓約が続いて私はびっくりしました。これはいけない。
とはいえ、海の岩(岩というよりも岩山に近いはず。それが何キロも何個もある)を全て取り除くなど人間には不可能であり、アウレリウスは慈悲なないのかと言う。ドリゲンこれに答えて曰く「ありませんとも」。そして自分のことは忘れろ、それにしても人妻に恋するなんて何か楽しいのかとさえ言う。こんなに取り付く島がないのに、どうして誓いを立てたりなんかしたの? 馬鹿にして煽ったんですか? これは物語の中でしっぺ返しが来るな。とはいえその時その場にいるアウレリウスは、この無理ゲーを言い渡されて絶望し、かなり長く愁嘆する。太陽神フィーバス(=アポロン)*1に、妹神ルシナに頼んで2年間ずっと大潮を起こし、水位が岩を5尋は超えるようにしてくれ、さもなくば岩をプルートーの国へ沈めてくれと願い始める。だがこれはデウス・エクス・マキナの呼び声ではなく、無理なことを言われて失恋が確定したことへの嘆きである。ひとくさり嘆いた後、アウレリウスは失神する。彼は兄によって抱えられ、家に戻された。
アルヴェラーグスはブリテンで名誉を受けた上で無事帰国し、妻ドリゲンと再び幸せに暮らし始めた。一方、アウレリウスは寝込んでしまう。憐れに思った兄は、ふと、オルレアン*2にいた頃、ある書庫で自然魔術の書物を見たことを思い出した。法学を学んでいた彼の友人が、隠していたのだ。占星術・星座に関連するその魔術書を用いたら何とかなるのではないか。そう思い、アウレリウスを誘って兄はオルレアンに行く。アウレリウスは寝込んでいたはずだが、望みが見えるとすぐ元気になっている。
さてオルレアンに近付いた頃、一人の若い学者と彼らは行き合う。この若者は兄弟が来た理由を知っていると思わせぶりなことを言う。兄弟は彼に付いて行き、道中で兄はすっかり思っていることを話す。そして、オルレアンの兄は、自分の昔の仲間のことを訊く。すると、仲間は皆亡くなったことを教えられ、兄は涙する。本筋外でさらっとしんみりエピソードを入れるな。
ともあれ、この魔術師の家に兄弟は着く。家は立派でとても寛げた。そして兄弟は、野鹿が沢山いる庭園を見る。今まで見た中で最も立派な牡鹿が百頭も猟犬に殺され、鷹匠たちが鷹狩をし、騎士たちが馬上槍試合を行って、ドリゲンが踊る。日本ならこの時点で狐か狸に化かされているなと思うところだが、ここはヨーロッパである。魔術師が両手を叩くと、これらは幻のように消え去った。三人は、ただ立派な書斎で座っていただけだったのである。魔術師は召使に夕食を準備させた。夕食後、三人はジロンド川からセーヌの河口まで*3の岩を全て取り払う魔術の報酬の話に入る。魔術師は千ポンドを要求する。アウレリウスはあっさり快諾、必ず払うと約束する。ただし早くしてと注文を付けた。魔術師もこれに応じた。翌朝三人はブルターニュに向けて出発した。そして現地到着後、アウレリウスの恋を憐れに思った魔術師は、頑張って占星術的に良いタイミングを計り。遂に魔術を実行する。一、二週間は岩はすっかり取り除かれたように見えた。
アウレリウスは魔術師に礼を言い、ドリゲンの元に行って、自分の苦しい胸の内をコメントした後、誓いに触れ、岩を除いたので見ておいてくださいと伝えて、帰って行った。岩が見えないことを確認したドリゲンはショックを受けて、二日間を嘆きのうちに過ごした。ここから彼女の長めの愁嘆が始まる。名誉が守れないなら死んだ方がマシだ、という趣旨であり、名誉を優先して命を落とした女性の逸話を何個も取り上げる。さて三日目、留守にしていたアルヴェラーグスが帰宅してくる。ドリゲンの様子を見た彼は、妻に事情を尋ねて、妻も包み隠さず答えた。アルヴェラーグスは、ドリゲンが約束を守らなければならないと言い、召使に、ドリゲンをアウレリウスの元*4へ連れて行かせる。ドリゲンは死ぬつもりだったような感触を受けるが、夫が帰って来てこの手の物語には珍しく夫婦間の報連相が機能して、夫と妻の状況認識が完全に一致する。そしてその上で、夫は妻が思い描いていたものとは異なる方向の指示を出すのだ。この方向転換はなかなか面白い。妻には生きていてもらいたかったのかな。ドリゲンとアウレリウスの逢瀬が秘密裏に行われるよう腐心している点からも、アルヴェラースグは未来を見ている。ただし、約束は果たされなければならないということだ。
ここからがこの物語の本番である。ドリゲンは、アウレリウスに誓いを果たすと言うが、どう見ても様子が尋常ではない。アウレリウスは事情を説明してもらい、約束を果たそうとしてくれている彼女とアルヴェラーグスに強い同情を覚えた。そして、あらゆる契約を捨てると誓った。つまりドリゲンはアウレリウスへの恋を諦めたのである。ドリゲンは膝をついて彼に感謝し、夫の元に戻る。アルヴェラーグスも非常に喜んだ。かくしてこの夫婦は生涯幸せに暮らした。
一方、ドリゲンのことは諦めつつも、魔術師への千ポンドの債務があるアウレリウスは、破産したと嘆くも約束は守らねばならないと魔術師の元(まだアルモニカに滞在中である)へ有り金を持って行く。そして、残りの負債を払うには財産を処分しなければならないので、支払いを二、三年待ってくれと頼む。魔術師はいぶかしんで事情を確認し、アウレリウスが想い人を得なかったことを知る。魔術師はアルヴェラースグもアウレリウスも高貴に振舞ったと褒め、自分も高貴な行いをしないと恥だと、アウレリウスの千ポンドの負債を放免するのだった。
郷士は、誰が一番寛容であったかと聞き手に問うて、話を締めくくる。
郷士は序で話が無駄に長かったので、本編も贅肉が多いのかと思ったが意外とそうでもなかった。話の内容もなかなか面白かった。惚れる相手は選べないので、それが人妻になってしまうこともあろう。約束は普通は果たすものである(不可抗力で履行不能になってしまったら別だが、今回はそれに該当しない)。ということで、アウレリウス。アルヴェラーグスには同情したい。ドリゲンも、調子に乗ったなあとは思うが、心千々に乱れたろうし、これ以上責めるのは酷。それに悪人/性悪には程遠い。魔術師は特に義理もないのに債務免除を自主的に行っており、立派で高貴な人な気はするが、行動原理がいまいちよくわからない。
*1:本文中では主にフィーバスと呼ばれているが、たまにアポロンも出て来る。14世紀の人においても、フィーバスとアポロンが同一神であることは認識されていたようだ。
*2:オルレアンと言えば、オルレアンの少女ジャンヌ・ダルクだが、彼女が『カンタベリー物語』が書かれた頃、どころか作者チョーサーが死んだ時点でもまだ生まれてすらいない。この文章が書かれた際、オルレアンの名はジャンヌ・ダルクとは一切、全く、何の関係もないのである。ジャンヌ・ダルクという言葉は、チョーサーにとってはスマホという言葉と等価で、意味が取れない。これが時代が違うというやつである。
*3:フランスの西海岸線の過半を軽く超えます。ドリゲンの要求に範囲指定はなかったはず。
*4:正確には庭園に向かわせるが、なぜそうなのか説明すると長くなるので割愛。アダムとイブが住んでいた庭園になぞられたのかなと思わないではない。
カンタベリー物語 近習の物語/チョーサー
近習の物語の序
恋を誰にも負けないぐらい知っているんだからと、恋の物語を求め*1られた近習は、恋をよく知っていることについて、そんなことはないと断ってから話を始める。
近習の物語ここに始まる。
というわけで、いきなりチンギス・ハーンにまつわる話が始まる。この物語ではカンビィウスカンと呼ばれる彼には、エルフィータという妻の元に、長男アルガルシフ、次男カンバロ、そして娘カナセーがいた。カナセーは筆舌に尽くしがたい美人だという。
さてカビィウスカンは、三月十五日に誕生の宴会をサレイで行った。その最中、一人の騎士が真鍮でできた馬にまたがり、ガラスの鏡を持ち、親指には金の指輪をはめ、脇には抜身の剣を携えてやって来た。彼は王、王妃、諸侯に挨拶した後、自らの持ち物について以下のように述べる。
アラビアとインドの王である自分の主君が、カビィウスカンの祝宴のためこの馬を贈る。この馬は24時間以内に、旱魃でも大雨でも、王の身体をどこにでも運ぶことができる。それどころか空を飛ぶことができる。そしてピンを回すだけで元に戻って来る。
一方、鏡には、どんな逆境が降りかかるか、誰が友で誰が敵か、貴婦人が思いを寄せる人の不実や裏切り、策略などを見せる。指輪は、はめるか財布に入れるかすれば、鳥と会話ができるようになるし、草の薬効もわかるようになる。剣は、どんな甲冑も切り裂く一方、剣の平で打てば剣で付けた傷は消える。なお指輪はカナセーに名指して贈られ、他はカンビィウスカンに贈られた。
人々は口々に、これらの秘宝の美しさ、不思議さを賞賛し、ああだこうだと品定めした。一方、これらをもたらした騎士は宴に参加し、カナセー姫と共に踊りの中に加わる。やがて夕餉時、カンビィウスカンは馬の操作方法を騎士に尋ねた。騎士は、要所要所は王と二人の時に伝えるとしつつ、その場でも結構細かく説明する。これを受けて、王は夕餉の席から宴会の場に戻り、タカラは塔に仕舞われた。
物語の起または序の部分に当たる。秘宝と騎士により、王宮にどんな変化がもたらされるのかワクワクするが、この第一部は結構長い割に、テーマを感知できるほどには物語はまだ動かない。
個人的には、12世紀から13世紀にかけて生きたチンギス・ハーンに関する物語が、14世紀のイングランドで成立していた事実に胸が熱くなった。この物語の存在は、モンゴル帝国が世界に与えた影響を、100年以上経過した後とはいえ中世内という意味ではほぼリアルタイムで証明している。当たり前だが、世界は繋がっていた。600年以上も昔から、ずっと。
第二部これに続く。
前日の大宴会は深夜まで続き、誰も彼もが九時まで眠りこけた。早めに引き上げたカナセーを除いて。彼女の目覚めの場面に、中世の習慣が表れていてとても興味深い。
それで彼女は最初の眠りが終わると目をさましました。
これが世に聞く、一般的だったとされる中世人の二度寝か! でもカナセーは設定上蒙古人よね? これどう解釈すればいいのだろう。
ともあれ、カナセーが二度寝しなかったのは、指輪と鏡のことでエキサイトしていたからのようだ。彼女は夜明け前に家庭教師を呼び、起きて辺りを歩きたいと言う。十人か十二人の侍女と共に、猟園を歩き回る彼女は、木の上に止まった隼(外国から来たように見える珍しい種類の隼)が悲しげに鳴くのを聞く。隼は鳴くのみならず、翼で自身の身体を打ち付け、嘴で自らの体を突いて悲しみを激しく表し、時々気絶しそうになるありさまだった。
指輪のせいで隼の嘆きの内容をある程度聞き取れており、胸の潰れる思いがしていたカナセーは、遂に隼に語りかける。こんなに悲しい様子は見たことがない、自分を傷つけるのは止めた方がいい、自分は王女だから王女の名にかけて、自分が何とかできる範囲なら助けになろう、だから怪我を治療させてくれ。
隼は失神し落ちて来て、カナセーの着物の袖の中で目を醒ます。隼は、王女を讃し感謝した後、自らの話を始める。彼女――そう、雌なのだ――は、灰色の大理石の岩の中で養い育てられていた。彼女は近くにいた雄の隼を愛したが、彼は外面がいいだけの、とんだ偽善者であった。一二年付き合ったが、雄の隼は、鳶の雌を見てそちらに心を映し、雌の隼に別れを告げて去ってしまったのだ。
自傷行為が凄い勢いなので、隼はてっきり雄だと思っていたのだが、雌だったんですね。これは意外。もちろん、男性がやる行為を女性がやっても、本来は意外に思ってはいけない。しかし中世の話でこれは、興味深いのは確かである。
それはともかく、恋人が別の相手に惚れて振られただけのことを、この隼は本当に長々と喋る。内面的な表現で文章が埋め尽くされており、具体的な事実への言及はごくわずか。感情が千々に乱れ、秩序立った思考ができなくなっていることがよく表現されていると思います。
さてカナセーと侍女たち*2はこの隼に対して悲しみの情を抱いた。カナセーは隼の傷の手当てをし、静養のための豪華な鳥籠を作ってやるのだった。
さてこの第二部の最後に、近習はこんなことを話す。
今のところは彼女の指輪のことにはこれ以上は触れません。その話の語るところでは、わたしがあなたがたに申し上げた王子のカンバロの仲介によって、後悔したこの雄の隼がどのようにして再び彼女の愛を取り返したかをお話しするのが必要になるときまでそれはとっておきましょう。そこでこれから、今までこんな驚くべきことは聞いたことが ないというような冒険や戦いのことをお話しすることにいたし ます。
まずはじめに、わたしは当時多くの都市を勝ちとったカンビィウスカンのことをお話し いたしましょう。その後でアルガルシフがどのようにしてテオドラを自分の妻に娶った か、そのテオドラのために、もし真鍮の馬によって助けられなかったなら、幾度も彼は非常な危険に陥ったであろうということなどをお話しいたしましょう。その後でカンバロがカナセーのために二人の兄弟と馬上槍試合場で闘い、彼女を手に入れることのできた次第をお話しいたしましょう。話を止めていたところからまた始めてまいります。
隼は元鞘なんかい! とまあそれはともかく、この部分は明らかに、続く第三部以降の内容の予告である。面白そうではあるけれど、ちょっと詳し過ぎる。前の話まで、部の最後にこのようなテキストが挟まれることはなかった。なんか変ですな。
第三部始まる。
陽の神アポロがその戦車を空高く駆けめぐらし、かの狡猾なるマーキュリー神の館にのり入れていく……
第三部はこれが全文である。そして第三部で近習の話は終わる。はい、つまり「近習の話」は未完なのです。じゃあ第二部の最後の予告は何だったのか? まさか、こういう話を入れるつもりだったんですが書けなかったんで許してね、という詫び証文のつもりだったのだろうか? あそこまで概略が書いていたら、勝手に補筆完成版を書く作家が後世いくらでも出て来そうなものだが、そこら辺どうなんでしょうか。
また、この一文は、登場人物としてアポロやマーキュリーが出て来たわけではない。よくわからないし今後わかるようになるつもりも正直ないので今まで書いてこなかったが、『カンタベリー物語』では、占星術的・十二宮的なあれやこれやが行ったり来たり……という表現が、時間や日時を表徴するために多用されている。これはそれに該当すると解釈すべきだ。つまり、第三部は実質的に、「○月のある日の○時ごろ」ぐらいのことしか書かれていないのである。
ここに近習に対する郷士の言葉、また宿の主人の郷士に対する言葉続く。
郷士は話を終えた近習に「近習君よ」と呼びかけて、上品、知恵がある、若いのに感じが籠っていて立派だと褒める。それに比べて自分の息子ときたら、と長々と愚痴り始めた。あいつは気高い上品さを学ぶ気がないという趣旨のことを言った辺りで、宿の主人が割って入る。
ああ、お前さんのその気高い上品さとやらには藁でも喰らえだ!
糞喰らえではない点には留意されたい。微妙に表現が違うので、この悪罵のニュアンス、程度が私にはよくわからない。糞よりは藁の方が柔らかいのか、親愛度が高いのか、それとも同程度なのか。
ともあれ、宿の主人は郷士に、話を一つか二つするという約束事を思い出させる。郷士は、それは知っている、この若者に一言二言話した*3からといって、と不満げだが、宿の主人は「つべこべ言わないで」と話を急かす。そして郷士は話を始める。
というわけで、次は郷士の話である。
総評等
この近習の物語、表現上のぜい肉がとても多い。ストーリー展開にはあまり影響しない(まだ書いていない場面に影響させるつもりだったのかもしれない)台詞や情景描写がとても多く、ページ数が膨れ上がっている。それを表現上の技法として肯定的に捉えるべきか、語り手である近習の未熟を表現していると解釈すべきか、私には判断が難しい。個人的には嫌いじゃないのだが。
カンタベリー物語 貿易商人の話/チョーサー
貿易商人の話の序
学僧の話を受けて、貿易商人は細君が口が達者な悪妻だ、じゃじゃ馬だとぼやく。そして、生涯女房を持たなかった人は、自分の細君の意地悪に感じる悲しみほど悲しいことはないのだろうとも叫ぶ。しかしながら、どうやら彼は、結婚して二か月程度しか経っていないようだ。新婚さんじゃねーか。さて宿の主人は、このこと(悲しみ)の一部でも話してくれるよう促す。貿易商人は承知するものの、惨めで悲しくなるから自分の話はしないと述べ、以下のような話を始める。
貿易商人の物語ここに始まる。
ロンバルディアに住む未婚の立派な騎士ジャニュアリィは、六十歳になった時、唐突に結婚したいと願い始めて、嫁探しを始める。貿易商人は、結婚の素晴らしさを何ページにもわたって説く。世継ぎだの妻は若い方がいいだの内助の功だの、現代の視点からすると「ん?」という要素も散見されるが、総じて結婚を礼賛し、妻というものの素晴らしさを故事格言を引きながら強調し。妻の言葉に耐えて従えと言う。惚気ているのではなさそうで、捨て鉢か皮肉の臭いがする。
さてジャニュアリィは、友達を集めて言う。自分は墓に片足を突っ込んでいるが、速やかに妻を娶ろうと思っている。妻の年齢は二十を越えていてはいけない。三十歳の女なんぞまっぴらだ。自分はまだ肉体的にはまだ元気だ。だから結婚したいという自分の意志に賛成してくれ。気持ち悪過ぎる。当時の貴人の結婚は色々とアレだし、現在でも超大金持ちの結婚だって本当にアレだが、別にジャニュアリィはトロフィー・ワイフが欲しいわけではなさそうだ。世継ぎを産ませることも第一目標には出て来ていない。ただひたすら、可愛い子ちゃんとキャッキャウフフしながら、幸福に暮らしたいというニュアンスが強い。気持ち悪過ぎる。
友人たちは意見を言う。中でも二人の兄弟は意見が対立していた。プラセボという男は結婚に賛同する。一方、彼の兄弟ジュスティヌスは反対する。頭の良しあし、酒癖、経済状態、男狂いかどうか、調べるべきことは沢山ある。基本的には好きなようにすべきだとは言うが、三年も妻をたっぷり《満足》させることはできないだろうと指摘する。ジャニュアリィは容れず、他の者も、ジャニュアリィの好きな時に望む人と結婚することに同意した。
しばらく結婚相手を探していたジャニュアリィは、遂に一人の乙女を心に定める。彼は友達を再び集めて、真実の天国には苦難と苦行による代償を払って行くべきである以上、現世で結婚の幸福を享受するといけないのではないかと不安に思っている、と吐露する。二十歳の女との結婚生活がうまく行くに違いないというこの思い込みよ。気持ち悪過ぎる。ジャニュアリィの行動を愚行だと思っていたジュスティヌスは、「結婚にそんな大層な幸福ないから心配するな(大意)」と述べた後、突然こんなことを言い出す。
さてと、皆さんがご理解になりましたように、バースの女房はわたしらの当面の結婚の問題のことでは短いながらとても上手に話しました。さようなら。神様が皆さんをお守り下さいますように。
この「バースの女房」が本当に唐突。登場人物が突然一つ上のメタレベルに移動するんじゃない、と言いたいところだが、これは鍵括弧の位置の誤植(つまりこれは実際には地の文=貿易商人の台詞)なのか、チョーサーの故意(本当にジュスティヌスがこう喋っている)なのか。判断は付きません。
ともあれ、反対されなかったジャニュアリィは、件の乙女、美しくみずみずしいメイ*1と結婚する。婚礼の場でメイは妖精のように美しかった。ところが、ジャニュアリィの近習にして、彼のために肉を切るほど信頼されている騎士ダミアンが、メイに惚れてしまう。そして体調を崩してしまうのだった。一方、ジャニュアリィに妻メイに夜の行為(なぜか歌も歌う)をしてご機嫌であったが、メイは毛ほどもそれを賞賛する気にはなれなかった。さてダミアンが体調を崩し出仕しないことを憐れんだジャニュアリィは、自分も見舞うし、それよりも先に妻メイに見舞わせることにした。想い人に見舞われたダミアンは彼女に恋文を渡す。メイはそれを引き裂いて便器に投げ入れる*2。しかしその晩、彼女は寝る際、夫に裸になるように言われて従う。何か楽しい戯れをしたかったらしい。これに対する彼女の気持ちは記載されていない。だがメイの脳裏からはダミアンが離れなくなり、彼を憐れんだ彼女は、返事の手紙(Yesの返事であったことが仄めかされている)をしたためてダミアンの元に行き、手紙をそっと彼に握らせて帰って行った。翌朝、ダミアンは元気いっぱいで起き上がり、職務に復帰する。
そうこうする内に、ジャニュアリィは失明する。恋は盲目とかではなく、本当の失明である。幸福の絶頂で盲目になった彼は、嫉妬深くなって、メイをいつも手の届くところに置いておくようになった。そんなある日、他に誰も入れないようにして、夫婦は庭を散策する。ジャニュアリィは嫉妬深いのを許せ(というよりも許容せよとのニュアンスに近い)と言い接吻をせがむ。メイは泣きながら、私が裏切ったのであれば殺してくれ、男はどうして女を不実だとこんなに非難するのかと反駁するが、その視線の先にはダミアンがいた。予め庭に忍び込んでいたのである。メイは合図し、ダミアンは梨の樹に登る。
一方、庭の反対側には、妖精国の王プルートーとその妻プロセルピーナ*3は、この様子を見ていた。プルートーは女を非難したソロモンの言葉を引きつつ女性の不実を責め、立派な騎士がそれを見ることができないのは可哀そうだと、“不正”の最中に老騎士の視力を戻してやると宣する。一方プロセルピーナは、あいつ多神教で偶像崇拝者だったじゃねーか(大意)*4とソロモンを批判し、女性に対する難癖に悲憤慷慨する。プルートーは妻をなだめて、女性云々の部分は事実上撤回するものの、約束は守るしかない*5と、ジャニュアリィの視力は回復させると宣言する。一方プロセルピーナは、メイにはメイの答えを与えてやろうと言う。
さてメイは、ジャニュアリィと共に梨の樹の下に差し掛かると、お腹が減ったから梨を食べたい、ついては自分を背中に登らせてくれと夫に頼む。ジャニュアリィは承諾して背を屈める。メイはそれを伝って樹に上っていく。そして、樹上にいたダミアンは、メイの下着の引き上げてその中へ押し入った。
この瞬間、プルートーはジャニュアリィの視力を回復させる。視力が戻ったことを喜ぶ暇もあらばこそ、彼の目に飛び込んできたのはメイの浮気現場だった。妻相手に激怒するジャニュアリィであったが、メイは、視力が回復したててありもしないものが見えているだけだと夫を言いくるめる。
あなたの視力が落ち着くまでは、あなたは何度も何度もあなたの視力に騙されるでしょ う。どう気をつけなさい、お願いです。
すげえ度胸、すげえ鉄面皮。しかしジャニュアリィは納得してしまい、メイと共に嬉しそうに屋敷に戻るのであった。
なおメイは妊娠しているようだ。誰の子なのか?
貿易商人の話の跋
女性は狡猾だ。そして貿易商の妻も様々な欠点を持っているが、そんなことはどうでもいい。なぜか? チクられるからである。といったところで、貿易商人は話を終える。
総評等
新婚なのに妻を恐れる貿易商が語る、貞淑な妻を熱心に探しながら実際に結婚した妻は不貞をかまして言い逃れも見事な人間だった老爺の物語。皮肉が効いていてよろしいです。バースの女房はじめ女性の活き活きしたところを肯定的に描くチョーサーにとって、この物語はどういう位置付けだったのだろうか。まさか、不貞もまた良し? 確かにジャニュアリィは幸せそうでしたな。
*1:メイは話の中で頻繁に「美しくみずみずしい」と形容される。六十歳のジャニュアリィとの対比表現でしょうなあ……。
*2:「流す」ではない点に注目。いやそりゃそうなんですが、こういうところに環境の違いが出る。
*3:つまりハデスとペルセポネーがいた。随分唐突に出て来た印象だが、実はそのちょっと前に、庭で彼らが踊っているとの文章があるのだ。庭が美しいことの比喩だとばかり思っていたよ。こういうことがあるから、昔の物語は油断できない。
*4:ローマ/ギリシャの神であるお前はそれでいいのか、という気しかしないが、「ああ! たった一人の真実の神様にかけて」とかも口走る。どう考えても唯一神よりも下位の存在として描かれている。中世キリスト世界におけるギリシャ/ローマの神の位置付けが何となくわかるというものだ。そもそもこの物語では、彼らは神ではなく妖精の王と女王と書かれている。妖精にデウス・エクス・マキナを委ねられるか疑問に思う向きは、シェイクスピアの《真夏の夜の夢》を想起いただきたい。
*5:約束でも契約でも宣言でもなく、女王と一緒にいる時に口走っただけに見える。それでも約束になるのか。妖精も大変ですな。
カンタベリー物語 学僧の物語/チョーサー
ここにオックスフォードの学僧の物語の序続く。
宿の主は、学僧が無口で馬に乗っていると指摘する。
お願いですからもっと快活になって下さいよ!
放っておいて下さいよ!と返したいところではあるが、続く宿の主人の主張はわからぬでもない。彼は学僧に話を促すが、聞き手の罪を思い出させるような話、眠たい話、学問的な言葉、修辞学の飾り文句*1等はやめて、平明な話を要請する。
学僧はこれを受け容れて、パドヴァで故ペトラルカから学んだ物語を語り始める。なおペトラルカは序文で、物語の舞台となるイタリアの西部のモンテ・ヴィゾー*2から、ポー川が西に流れることを延々と描写しているとのことだが、それを書き記すと長くなるので、ばっさりカットすると断る。
学僧はパドヴァに行った口ぶりである。つまり現地でペトラルカから話を「学んだ」らしい。これが、実際に対面で話を聞いたのか、残された文章を読んだのかは不分明だ。序文の話をしているので後者かもしれない。しかし、彼は巡礼の道中で実際に喋っているという設定であるにもかかわらず、ペトラルカの序文を「書き記すと」と言ってしまっている。訳文の問題かもしれないが、仮に原文もこのような表現だとすると、この当時にあっては、「口頭で話す」という設定よりも「作者が書いて読者が読む」というメタ的現実が優先されるのが常だった、と理解すべきなのかもしれない。現代の読者、特にミステリ・ファンが気にするような表現の統一は、中世では誰も気にしていなかったのだろうか?
オックスフォードの学僧の物語ここに始まる。
ヴィゾー山の麓サルッツォを統治する侯爵ワルテルは、統治能力があり敬愛されていたものの、狩に熱中する悪癖があり、しかも妻を娶ろうとしなかった。領民たちは問題視して、侯爵の所に押しかけた。代表者は侯爵を賞賛した後、「でも早く結婚してくれ、グズグズしているとすぐに年を取るし死ぬぞ(大意)」と言って、家系が断絶するのは自分たちにとっても悲惨だ、と結婚を迫る。
領主様、もしあなた様が御同意下さいますならば、わたくしたちはこの国で最も高貴で、また最も偉大な家のお生まれである奥様をあなた様のためにお選びしようと存じます。
放っておいてやれ!と言いたいところではあるが、残念ながらここは中世であり、領主の結婚(と特にお世継ぎ問題)は領民としても下手をすれば死活問題なのだ。侯爵は憐れみを催し、自分は自由に楽しんできたが結婚したら奴隷になるだろうなあとぼやきつつ、早々に結婚することに同意する。しかし、妻は領民で選ぶのではなく、自分で選ぶと言う。そして、以下を誓えと領民たちに言う。
わたしがどんな妻を娶ろうとも妻の生きている限り、言葉でも、行いでも、ここでもどこでも、あたかも皇帝の娘のように妻を尊敬するということをわたしに約束して欲しいということだ。
(中略)
お前たちがわたしの選択に対しては不平を言ったり、逆らったりすることがないように、ということだ。
フラグに見えるが、さてどうなるか。ともあれ領民も誓い、また侯爵は自分が必ず結婚する日も決めた。領民たちは帰り、侯爵は宴会の準備を家来に指示する。
第二部始まる。
侯爵の宮殿から遠くない小さな村に住んでいる、村で最も貧しい村人ジャニキュラには、見目麗しく徳も美しいグリゼルダという娘がいた。彼女は働き者で、まじめであり、父親のことも敬っていた。侯爵は狩に出かけた折にグリゼルダを見初めており、結婚するなら彼女とだろうと思い定めた。
侯爵は婚礼の日まで誰が花嫁か明かさず、グリゼルダ本人すら何も連絡せず、結婚当日に彼女の家を訪れて、ジャニキュラに自分はグリゼルダを妻に迎えようと思う、と下知する。そして、グリゼルダと二人で話し合いの場を設ける。そしてこんなことを宣う。
あなたがすすんでわたしの願いにすべて応じて下さるということ、そしてまた、(中略)わたしがあなたを笑わせようと、苦しめようと、わたしは自由で、しかもあなたは日夜そのことで決して不平を言わないことです。またわたしが「そうだ」と言うときに言葉でも顔をしかめても「いや」と言わないこと、このことを誓ってほしい。
勝手なこと抜かしてんなこの領主。しかしグリゼルダはこれを受諾してしまう。そしてジャニキュラの家から出た侯爵は、グリゼルダが結婚相手であり、皆が彼女を愛してほしいと宣する。領民に愛情を指示したのは救いです。
女官たちに格好を整えられたグリゼルダは、知り合いが信じられないぐらいの美貌となり、おまけに挙措も美しい。結婚後も彼女は領主の妻として立派な態度を誰にとっても取り続け、評判を得る。夫との関係も良好で、適切な助言すらし、夫の不在時は領主代行すら円滑にこなした。やがて彼女は女児を産む。
フラグ臭はびんびんながら、結婚生活の滑り出し自体は好調である。
第三部始まる。
冒頭から一気に不穏になる。
次のようなことが怒りました。それはしばしばあることなのですが*3、つまり、この子供がしばらくの間乳を吸っていたときに、この侯爵は妻の一貫した誠実さを知るために彼女を試してみようという気が心の中に強く起こったのでした。
次の段落で、語り手の学僧もこの夫にはさすがに否定的になる。夫には似つかわしくないという言葉すら踊っていて、なるほど登場人物は人格に問題があっても、語り手はマトモなんだなと思わされます。
侯爵はグリゼルダに、貧しく卑しいお前を富貴の身にしたのは俺だ、と恩着せがましいことを言い、小さな村で生まれた人間の指図を受けるのを恥辱視する人間もいる、と今更なことを言い、娘のために最善は尽くさねばならないが、グリゼルダではなく領民にとっての最善でなくてはならないと言う。グリゼルダは誓いは守るとして、娘の処遇を全面的に侯爵に委ねた。侯爵は内心これを喜んだが表情は憂鬱にした。そして腹心に指示して、娘をグリゼルダから取り上げさせる。その際、腹心はグリゼルダに、侯爵の命令には逆らえない誓いを立てていらっしゃいましたよね、と言わせている。グリゼルダはこれにも即座に唯々諾々と従い、娘に今生の別れを告げる。
え、「お前の夫の命令だ」と言うだけで、グリゼルダはどんな指示にも従うんですか。もの凄いセキュリティホールが開いている気がする。ともあれ、グリゼルダから娘を取り上げた家来は、侯爵に娘を差し出す。家来がセキュリティホールを悪用する人間でなくて良かったです。侯爵は秘密裏に、ボローニャ近くのパニコの伯爵に嫁いでいた自分の姉に、娘の養育を任せて送り出すのだった。片やグリゼルダは不満の顔一つせず、愛娘の名を一切口にすることはなくなった。
第四部これに続く。
四年後、グリゼルダは男児を産んだ。侯爵はまた妻を試す気になってしまう。
結婚した男というものは辛抱強い人を見つけると節度を知らないものだ。
いきなり箴言で刺してくるのは止めてください学僧さん! そして今度は侯爵は、領民がジャニキュラの血筋の者が次の領主になるのを喜ばないので、息子もその姉と同じくこっそり始末を付けると言う。誓約通りグリゼルダはこれに従う。グリゼルダから息子を実際に取り上げるのは、侯爵自身ではなくまた例の腹心でした。この人も大変だな。そして、息子がいなくなっても約束通りに振舞う妻を見て、侯爵は更なる試練のために謀を巡らす。
さてグリゼルダの娘が12歳になった頃には、領民からの侯爵の評判は悪化していた。娘と息子を侯爵が殺害したという噂が立ったのだから当たり前、自業自得である。これを奇禍として、侯爵は領民の安寧のため、彼が望むなら別の婦人と結婚しても良いというローマ教皇の勅書を偽造する。この偽造勅書を侯爵は公表した。グリゼルダはショックだったに違いないが、相変わらず態度には全く出ない。そしてボローニャの伯爵に、娘と息子の姉弟を威儀を正して、しかし素性は隠したまま、国に連れて帰ってくれるよう要請する。……これは間違いなく、侯爵が、伯爵に縁のある若い女性(実際には娘)と結婚する振りをしようとしているな。
第五部これに続く。
侯爵は、領民が別の妻を娶れと言っているから、新しい妻に場所を譲るようグリゼルダに迫り、結婚時に持って来たものは実家に持って帰るよう言い渡す。グリゼルダはこれにも唯々諾々と従う。侯爵と新妻を祝福することすらする。そして、自分が宮殿に来た際は、そもそも実家にいた際に侯爵が下賜した豪華な服を着、宝飾品を付けてやって来たので、それらも返す、さすがに持ち帰ることができない処女の報償として、下着はもらいたいと言う。そしてその宣言通り、着物を脱いで、下着姿のまま父の家に向かって進んで行った。人々は涙を流しながら彼女に従って行き、父は侯爵の生まれた日を呪う。しかしながら、グリゼルダは引き続き健気であった。
侯爵もおかしいが、グリゼルダも明らかにおかしい。ちょっと怖くなってきた。
学僧は第四部を以下のように締めくくる。
人はヨブのことを語ります。しかも殊に彼の謙遜なことを語ります。それは学者たちが好きな時に、特に男性について上手に書くことができるとおりです。だが、真実のところ、学者たちは女性たちをほとんど賞めることはいたしませんけれども、謙遜なふるまいをすることにおいて女性に匹敵するものはありえませんし、また女性の半分も真実な男もありえません。
「謙遜」なんてレベルじゃないだろ、という気はするが、これは紛れもなく「男って良く書かれるけれど、女性については書かれないだけで、実際は女性も素晴らしいよね」的な概念である。先進的と言い得るのだろうか。それとも当時これは一般的だったのか。
第六部
ボローニャから伯爵一行が近づいてくる。新しい侯爵夫人と言われている若い娘を従えて。侯爵はグリゼルダを迎えにやり、新しい妻を盛大に迎えたいが、自分の望み通りに部屋をきちんと整えることができるのはグリゼルダだけなので、お前は貧相でみすぼらしいけれど、召使として奉仕しろと言い渡す。グリゼルダはこれも素直に受諾、館を片付け、食卓を置き、寝所を作り、侍女たちと共に宴会の準備を終えた。
やがて伯爵一行が高貴な子供二人を連れて到着した。人々はその華麗な様を見て、侯爵ワルテルも馬鹿じゃなかった、妻を代えようとしたのは最善を願ってのことなんだ、と言い合った。グリゼルダよりも若いから子供を沢山作れるだろうし、高貴な身分だから人気もより出るだろうと判断したからである。彼らは侯爵を褒め称えた。この領主にしてこの領民あり。選挙で選んだはずもないのに、何だこの同レベル感は。
祝宴の場でもグリゼルダは忙しく立ち働く。態度も立派なもので (恐らく高貴な客人からは)貧しい身なりなのに名誉と尊敬を表す術を知っている彼女は何者かと訝しがられた。グリゼルダは、乙女とその弟にも優しく、真心から賞賛した*4。そんな中、侯爵はグリゼルダを呼び、新しい妻を気に入ったか尋ねる。グリゼルダは仰る通りだとして彼女を褒めた後、侯爵に一つだけ忠告する。
あなたがほかの人たちになさいましたように、この年若い乙女を責め苦で苛まれることのないようにということです。と申しますのは彼女はわたしなどと違っていっそう優しい心遣いで養育されていられます。それに、思います②、貧しい境遇で育てられた者のように逆境に耐えてゆくことはおできにならないからです。
……微妙にキレている気がしないでもないが、ともあれ、事ここに至り憐れみを最大限に覚えた侯爵は、全てをネタ晴らしする。グリゼルダは失神するが気を取り戻すと娘と息子を泣きながら腕に抱く。そして一しきり感動した旨を述べた後にまた失神する。再度我に返った彼女に、誰も彼もが喜びの言葉を述べ、好意を示した。夫の侯爵も彼女を慰めた。グリゼルダは再び富貴の身となり、祝宴が開かれ、その後幾年も、侯爵とグリゼルダは幸せに暮らした。めでたしめでたし。なお彼らの息子は、妻を大きな試練にけるようなことは決してしなかったという。
以下、ネタ晴らしした際の侯爵の自己認識である。
わたしはこの行為をなんら悪意や残忍な心から行ったのではなくて、お前の中の妻らしさを試してみたい心からであった。
この期に及んで正当化を図っているわけですが、どう考えてもこの「試してみたい」は、現代の法律からすると悪意ないし故意なので、免責事由にはなりません。民事免責どころか刑事免責にすらはるか遠く及ばないだろうなあ。地獄に落ちろワルテル(サムズダウン)。
さて物語を語り終えた後、学僧は、現在は遠い昔よりも道徳基準がしっかりしていない*5と断った上で、自分の見解を述べる。
忍耐の点でグリゼルダを妻たちが見習うべきではない、耐えられないから。しかし逆境に、グリゼルダのようにしっかりした態度で動揺せず対処すべきである、と言う。というのも、グリゼルダがあそこまで忍耐強いからには、私たちも神が送り給うものを全て善意をもって受けるべきだからだとする。そう来たか。神はいつも人を試している。我々の弱さは全てご存じであり、我々の意志を知ろうとして試しているのではなく、鍛錬のために試している。だから忍耐の徳を旨として生きようではありませんか。
学僧は更に、バースの女房の愛のために、晴れ晴れと歌を朗唱すると表明する。
チョーサーの結びの歌
グリゼルダは既に死んだという前提での歌(詩?)である。グリゼルダの死と共に忍耐も死んだ、グリゼルダのような妻はいやしない、奥様方は黙るようなことはするな、主導権を握れ、強いんだから戦いに備えて男どもに危害を加えることのないよう獰猛になれ(喋りで)、男たちを恐れるな敬うな、あなた方の能弁は鋭いから、嫉妬の縄で夫を縛れ、美人なら顔や衣服を見せびらかせ、醜いなら費用にけちけちするな、友達を作れ、気分は軽くしておけ、主人を翻弄しろ。
第六部最後の学僧自身の語りからこの歌に至るまでは、かなり意外なことに、妻の立場への賛歌になっている。皮肉なのかもしれないが、活き活きとした奥様像に、学僧は(つまりチョーサーは)たいへんに肯定的である。楚々として夫の言うことに何でも従うグリゼルダ、ぶっちゃけ非常に不気味だったからなあ。現代の小説ならば、第六部ではホラーめいた読むもおぞましい猟奇的オチが用意されてもおかしくはなかった。それぐらい彼女は不気味です。やっぱ、御伽噺の、男に従順なだけの女はあかんな(逆も同じ)。
宿の主人の愉快な言葉をお聞き下さい。
宿の主人は、樽いっぱいのビールを飲むより、妻がこの物語を聞いてくれた方がマシだと言う。この話は、彼の意図に叶った上品なものだったようだ。しかし、ないものをねだっても無駄と言う。
私の読解力がポンコツなので、ちょっと意味が取れなかった。宿の主人の奥さんは、我が強いのでグリゼルダを見習ってほしいとの、学僧やチョーサーのスタンスとは異なる価値観の表明だろうか? それとも、彼の言葉自体が反語なのだろうか?
*1:その割には宿の主人や他の巡礼者にも、飾り文句のような言葉が多い。これは14世紀には庶民にも一般的だったのか、教育を受けた人には一般的だったのか、それとも文章(この物語は小説なので歴然と文章である)はこういうものだったのか。
*2:訳文ではヴィゾー山とされ、訳注では「ヴェスルス山のこと」と記されているが、Google検索にかけても何のことだかさっぱりわからない。パラマウント・ピクチャーズのロゴのモデルの一つと噂される山で、そう言われると何となく知った気になれる。
*3:しばしばどころか決してあってはならないのは言うまでもない。神を試してはならないのと同様、いやそれ以上に、配偶者を試してはならない。
*4:自分の子供たちだと一目でわかったのかもしれないが、そのような描写はない。
*5:21世紀からすると逆である。中世のヨーロッパ人にこの認識があったのは興味深い。
カンタベリー物語 召喚吏の話/チョーサー
召喚吏の話の序
召喚吏は初っ端からキレている。そりゃそうである。直前の、托鉢僧の話で散々おちょくられたから。嘘吐き托鉢僧の嘘の話を信じないように願うと巡礼団に呼び掛けた後、托鉢僧は地獄を知っていると豪語したが托鉢僧と悪魔は大してかけ離れていないから当然であると難じる。天使がある托鉢僧を連れて地獄を案内した際に、彼は天使に、托鉢僧が誰一人として地獄に来なくて済むようにしてほしいと願った。天使は彼をサタンのところに連れて行き、サタンの尻の穴から蜜蜂のように千の二十倍もの托鉢僧が飛び出してくるのを見せる。托鉢僧は辺りいっぱいにうようよ群がったが、やがて悪魔の尻の中に這うように戻って行った。召喚吏は、この尻は代々の托鉢僧が自然に受け継いだものと愚弄して、神よ救い給え的なことを言うが、この呪われた托鉢僧は別ですと言い放ち。前置きを終える。
ここに召喚吏が彼の話を始める。
舞台はヨークシャーのホルデルネッセである。その地の托鉢僧がいつもの調子で喜捨等を募っていた。説教を終えた彼はその場から離れ、今度は家から家を回って、食べ物を募る。喜捨をしてくれた人の名は全て、奉納帳に書きつけられていく。ところで托鉢僧には御付の召使がいた。托鉢僧が家の外に出た途端に、この召使は奉納帳に書かれた人の名前を消すのである。そして托鉢僧は嘘の作り話を人々にして奉仕した。
ここで巡礼団の托鉢僧が、それは間違いだ(それは嘘だ!ぐらいのニュアンス)と突っ込むが、宿の主人が止めに入り、召喚吏に続きを促す。召喚吏は話を続ける。
やがて托鉢僧は、以前この近辺では最も多額を喜捨してくれた家に着いた。家の主人は家の中で病で臥せっており、托鉢僧は彼に、更なる釈義(もちろん更なる喜捨も必要になる)を薦める。そうするうちに、部屋に主人の奥さんがやって来る。托鉢僧は彼女を盛大にハグし、ちゅうちゅうキスをして美貌を褒め称えた。奥さんは病人の夫が怒りっぽくなって困ると言い、托鉢僧は確かにそれは問題なので二言三言、注意すると誓う*1。奥さんは托鉢僧に食事をして行かないかと誘い、托鉢僧は、雄鶏の肝、柔らかいパン、あぶった豚の頭ぐらいしかいただかないが、自分のために獣を殺すのは止めてほしい、自分たちは栄養を聖書からもらって粗食に慣れているなどとぬけぬけと言う*2。そして、奥さんは、二週間ほど前に托鉢僧がこの町から出て行ってすぐ、自分たちの子供が亡くなったという。托鉢僧は、ちょうどその頃僧房で眠っていたら、お子さんが天国に上っていくのが見えた、これは僧房の他の僧侶も見た、とこれまたぬけぬけと言い、自分たちの祈りは世俗の者の祈りよりも効力があるなどと言い始め、敬虔を長々と自慢する。話は、病んだ主人トマスに、更なる喜捨を求めることに収斂していく。
病人は、喜捨を複数の托鉢僧に何度もして、一向に身体は良くならない、もう金はないと言う(たぶんちょっと怒っている)。托鉢僧は、自分たちが最高の僧侶なのになぜ他の托鉢僧に喜捨をするのかと責める。托鉢僧自身はトマスの金など欲しくはないが、キリストの教会のためにはやむを得ないと言い放つ。あんなに良い奥さんを怒るのは良くないと、上から目線で説教を始める。
怒りから遠ざかるように。托鉢僧は、怒りがもたらした悲劇を語り始める。その昔、セネカが語ったことには、怒りっぽい王の在位中に、裁判官がある騎士に仲間殺しの嫌疑をかけて死刑を宣告し、別の騎士に執行を命じる。だが殺されたとする騎士が帰って来たので、刑の執行を命じられた騎士は執行を中止した。そして騎士三人で裁判官の元に戻って来ると、裁判官は三人全員を死刑にした。死刑を宣告された騎士は死ななければならない。行方不明だった騎士はそもそもの原因だから死なねばならない。執行を命じられた騎士は、命令に従わなかったのだから死なねばならない。
もう一つ、托鉢僧は怒りっぽかったカンビセス王のエピソードを語る。酒を飲み、悪漢の振る舞いをしていた彼に、家来が、酒は心も体も壊すからほどほどにするよう諌言する。カンビセスは大酒を飲んだ上で家来の息子を自ら矢で射殺し、酒が手足や目の力を奪ったか?と煽る。托鉢僧は、かように王の悪徳を指摘するなと説く。……こいつひょっとして僧院は王だから文句を言うなと言ってる? そして彼は、トマスに怒りを懺悔せよと迫るのであった。
病人トマスは、懺悔なら午前中に司祭にしたと言って、托鉢僧への懺悔は拒否する。そこで托鉢僧は、だったら金をくれと言い募る。他の人がのうのうと暮らしている時に自分たち僧侶は紫貝や牡蠣でしのいでいるが、修道院はまだ礎石が用意できておらず、自分たちの住まいにはタイルもない。これらが14世紀において貧乏の証なのかはよくわからないが、ともかく托鉢僧は、自分たちの説教が良くないというならそれは世界が破滅に向かっているということだと嘯き、なおもトマスに金を要求する。トマスはさすがに内心めちゃくちゃ怒った。トマスは表面上、寄進を承諾する振りをして、これから渡すものに関しては僧院の修道僧に平等に分配するよう条件を付ける。そして寝ている自分の下に財産を隠してあると托鉢僧に信じ込ませて、尻の下に托鉢僧の手を置かせることに成功する。そこでトマスは托鉢僧の手に盛大な屁をぶちかます。屁を握らされた托鉢僧は激怒してトマスの家を出て、領主*3の館に行き、侮辱を受けたことを報告する。長の妻も一緒に話を聞き、下衆(トマス)の頭がおかしくなったと言う。
長は夢うつつの中にいるかのようにじっと坐っていました。
まあこんな話を聞かされたらそりゃこうなるわな。そして長は、屁を含めて全ての音は空気の振動でしかない*4ので、それを平等に分けることなど不可能だ、トマスのような下衆は放っておいて食事をしようと提案する。
屁の十二等分についての、肉切り役である長の従者の言葉
ここで肉切り役の従者が登場し、屁を等分にする方法を話せると言う。長は許可し、従者は馬車の車輪を使うのだと説く。車輪は一般に十二本の輻(スポーク)を持っていて、修道院は一般に十三人でできているので、丁度いい。ここにいる托鉢僧は車輪の中心である轂に鼻を付け、他の十二人は輻の外周の端に鼻を付ける。そしてトーマスには、車輪の中心・轂で屁をさせれば、音も臭いも平等に届く。1.車輪の轂と輻が空洞で、2.その空洞が繋がっており、なおかつ3.轂に穴が開いていなければ、この方法は実現不能だが、ともあれ、長も奥様も他の皆も、托鉢僧を除いて、従者の言葉に感心した。そして老トマスは馬鹿者ではなく、微妙深遠な何かがこの知恵を語らせたのだろう、ということになった。
召喚吏はここまで語り終え、もう町*5に着いていると言う。
総評等
話の中の托鉢僧は屁をつかまされはしたものの、前話の召喚吏が地獄に連行されたのと比べれば、大して酷い目には遭っていない。随所で尊大に振舞って嫌な奴なのは明確なものの、領主(長)は托鉢僧に対して同情的であり、十二等分の方法を従者が思いつくまでは、彼もその奥様も、被害者にして病人トマスを悪しざまに罵っている。そして最後まで、托鉢僧は追加で懲罰は受けないのである。最後にフォーカスが当たるのは従者の知恵と、それを実現した場合に想像される情景の滑稽味である。
召喚吏が語り手により非常に直截的に馬鹿にされていたのに比べて、托鉢僧への皮肉は、皮肉が効いていて、こちらの方が手が込んでいる。托鉢僧は自分が悪いことをしているとは思っていないし、語り手自身も一々托鉢僧をダイレクトにこき下ろさない。その尊大な勘違い行為をひたすら繰り広げさせて、間接的に托鉢僧を馬鹿にするという手段を取っている。お主やるな。
カンタベリー物語 托鉢僧の話/チョーサー
托鉢僧の話の序
寺領廻りの立派な托鉢僧はいつも召喚吏にしかめ面をしていたが、野卑な言葉をかけてはいなかった。しかしながらバースの女房の話を終えた際に、遂に言葉の上でも攻撃的になる。彼は、バースの女房の話を褒めた後、召喚吏についての面白い話をすると言う。
召喚吏というものにはいいことは何も言われていないことをよくご存じでしょう。あなたがたのどなたも、それで気分を悪くされないようにお願いします。召喚吏っていうのは、姦淫の罪のための召喚状を携えてあちこち走り廻り、町々のはずれではひどくぶたれているのです。
宿の主人は喧嘩は止めるように口を挟むが、召喚吏も反応してしまい、好きなことを言えばいい、言い返してやるとお冠である。宿の主人は召喚吏も止め、托鉢僧に話を始めるよう促す。この人たちなんでこんなに仲が悪いの?
托鉢僧の話ここに始まる。
托鉢僧が住んでいる地方には、昔々、社会的地位の高い副監督*1が住んでいた。様々な罪に対する処罰を大胆におこなっていて、中でも好色漢を一番ひどい目に遭わせた。十分の一税の支払いを滞らせている人もひどく罰せられた。彼はスパイ網を持つ召喚吏を手近に用意していて、この召喚吏が、告げ口も大歓迎、二十四人の罪人――恐らく税金の滞納者――を密告するなら好色漢を見逃すよう手心を加えていた。この手口をぼろくそに言ってやると托鉢僧は息巻き、召喚吏は頭がおかしいと匂わせ、召喚吏の権限は托鉢僧の自分には一生及ばないと言う。
ここで巡礼団の召喚吏が口を挟んでくる。巡礼団参加者の語り手が物語を喋っている際に、他の参加者が話を止めて台詞を言うのは、これが初めてである。召喚吏は、女郎屋の女も管轄外だと言う。托鉢僧も似たようなものだと言いたいらしい。宿の主人はさすがに「こん畜生!」と罵って、托鉢僧に、召喚吏がわめいても話を進めるよう促す。いや大変ですな。
話は続く。物語の中の召喚吏は、女衒たちも手下にしていた。彼らは知っていることを全て召喚吏に話し、彼はそれによって大儲けをしたのである。法的召喚状もなしに、庶民の無知につけ込んで、破門にあうと脅して金を巻き上げていたのである。女たちも召喚吏に、自分が寝た者を教えた。この情報を元に、彼は宗教裁判所への召喚状を偽造して、男から金を巻き上げた。
そんなある日のこと、召喚吏は立派な楯持と出会う。はるか北の国*2から来たという楯持は、代官としての仕事を一部でやっている点では召喚吏と共通しているとのことで、なぜか意気投合した様子で、召喚吏を兄弟呼ばわりする。召喚吏は楯持に名前を聞くと、楯持は自分は悪魔だと答え、自分に何かくれる者がいないか見付けるためにこの辺りで馬を乗り回していると言う。召喚吏はいったん恐れるものの質問を重ねる。悪魔は神の手伝いになること*3もあるようだ。召喚吏は悪魔に対して真実の誓いを立て、悪魔は人がくれた物をとり、自分は自分の分をとり、両者の収穫量が不均等になったら平等に分けるようにしようとする。悪魔はこれを受諾した。
しばらく行くと、二人は、馬方が馬を駆り立てている場面に遭遇する。馬方は馬がうまく動いてくれないので、馬を「悪魔めがお前を捕まえてゆくがいい!」と罵る。召喚吏は悪魔に、ほら人が馬を与えたぞと囁くが、悪魔は馬方が本気で言っているわけではないので貰わないと言う。実際、馬がうまく動くようになると、馬方は上機嫌で馬を褒めるのだった。
次に、二人は街の外に住む老婆の元に向かう。召喚吏はいつもの手口で彼女から12ペンスを巻き上げるつもりだった。偽造の召喚状を見せて老婆と召喚吏が押し問答するうちに、老婆はこう口走る。
あたしゃお前の体と、あたしの鍋を、色の黒い荒っぽい悪魔めにくれてやるよ!
これを聞いた悪魔は口を開く。
なあ、わしの親しいおふくろのメイベルさん、お前さんの言っているこのことはほんとにお前さんの意志かい?
老婆は答える。
死ぬ前に悪魔が奴をひっ捕まえるがいいや、鍋もなにもかもみんな! 考え直すんなら別だがね。
召喚吏が考え直すわけもなく、老婆を罵倒する。ここに至り、悪魔がもらう条件が遺漏なく整えられてしまった。悪魔は、相変わらず召喚吏を兄弟と呼びかけつつも、お前の体と鍋が自分のものになったと告げ、今夜地獄に一緒に行くと告げ、召喚吏を捕まえる。召喚吏は、代々の召喚吏がいる場所、地獄へと連れて行かれるのだった。托鉢僧は、悪魔に気を付けろと言い、召喚吏を悪魔が捕まえないうちに彼らが悪行を悔い改めるよう皆で祈るよう願う。
悪魔にやるのが自分の物でなくてもいいという隠し条件は後出し気味である。悪魔が誰にもこの条件で約束しているとすれば混乱は必至であろうが、突っ込むのは野暮だろう。
なお托鉢僧は、総序の歌にて、有能ではあるが、人のことは言えない破戒僧気味の人間として描かれている。そういうのを頭に入れた上で読むと一層興味深い。
カンタベリー物語 バースの女房の話/チョーサー
今回から岩波文庫版では中巻です。
この女房さんのパートは長い上に、他のパートと決定的に異なる点がある。語り手自身の話である「序」が濃いのだ。その濃さはやはり、バースの女房アリス―ン自身に起因する。彼女は、女傑です。そうとしか言いようのない強烈なキャラクターである。登場人物がこれほどの活力をもって迫ってくることは、これまでの『カンタベリー物語』にはなかった。今後、彼女に匹敵あるいは凌駕する強者は登場するのか?
バースの女房の話の序
物語に入る前に、これまででダントツで最長の自分語りがなされる。複数回にわたる結婚の正当化、処女の神聖視の論破*1、夫の操縦方法、夫たちとのエピソード。そして最後になぜか、次回と次々回に出番がある召喚吏と托鉢僧がいがみ合う。
以下、アリス―ンの話の概要を書きますが、実際には、聖書を中心とした比喩が大量に入るので、概要と実際の文章とでは、受ける印象がかなり異なります。
バースの女房アリス―ンは五回結婚している。複数回結婚することをキリストは禁じていない*2し、神も産めよ増やせよと言っているではないか。ソロモン王をはじめ複数の妻がいた人間はいるし、聖人たちも結婚を悪いことだと言ってはいない。処女であれと忠告してくる人はいるが、それは忠告であって命令ではない。アリス―ン自身は、自分が処女ではないことを誇ることはしないが、神はその人に合ったことをされるわけで、引け目にも感じていないし、処女でいるべきであったとも思わない。処女は道徳的完全無欠なので、キリスト様はそれを望む人間にそうお話になったのだとも言う。
生殖器にはちゃんと機能があるのだから、使うことは義務ではないが、使いたい人は使うべきだ。アリス―ンは処女を羨ましいとは思わない。(恐らくセックスのことを指して)夫の負債はちゃんと払うべきだし、アリス―ンは喜んで夫の肉体を虐待する。夫の肉体を支配するのはアリス―ンである。夫は妻を愛するのである。
ここまでアリス―ンは一気に話す。一応「」付ではあるが、ここまで地の文がない。そしてやっと地の文と他の人間の台詞が登場する。免罪符売りが茶々を入れて来るのだ。自分は結婚するところだったが、そんなことなら結婚しなくて良かったと。
これに対してアリス―ンは、まだ話は終わっていない(大意)とビールの比喩を使って反発する。免罪符売りは恐らく苦笑交じりに、若い自分たちに姐さんの話をしてくれと言う。まあ実質的には引き下がってますね。これを受けて、アリス―ンは自分の体験をまたぞろ長々と始める。
アリス―ンの夫は五人中三人が、年寄でお金持ちの良い人だった。彼らは夜の生活があまりできなかった。アリス―ンは、夜の労働をするために彼らに何をしたかを思い出すと笑えると言う。そしてよく飼い慣らしたと主張する。がみがみ小言を言うことで。
その手法は、嘘を言うことだった。アリス―ンは、自分が彼らの浮気を疑っていたり、夫が妻であるアリス―ンを軽んじしたりするかのような当てこすり、小言、叱責を繰り広げて、それを通して夫をコントロールするのだ。具体的なこの小言が何ページにもわたって記載されている。なかなか強烈です。しかも、夫が酔ったときに喋ったことを非難する風を装った小言もある。実際には夫はそんなことは言っていないのだが、何せ酔った時だと言われているので夫自身は真贋が判断できない。加えて、アイリーンは、妹や家の徒弟などと口裏を合わせている。夫は騙されてしまいますよね。いや酷い奥さんだと思います。しかしアリス―ン曰く、夫も嬉しそうだったらしい。自分が夫を愛していているから嫉妬していると思わせた、ということのようだ。そして嘘、空泣き、口では口で言い返し、ベッドで酷い目に遭わせる等の手法を駆使して、夫婦間の争いを断念した方が良さそうだと夫に思わせるように仕向けた。もちろんおべっかも使う。男の方が女よりも分別があるとか、本当に口八丁。
自分の手管を詳細に述べた後に、アリス―ンは四番目の夫について語る。彼は情婦を囲う道楽者だった。そのことを腹を立てたアリス―ンは、彼に仕返しをしたという。だがその内容が何かはちょっとよくわからなかった。
五番目の夫は、彼女にとっては最も残酷な痴れ者で、アリス―ンの心に取り入る術をよく心得ていたという。オックスフォードの学僧だったという。彼はアリス―ンの親友アリス*3の家に下宿していたという。そしてアリス―ンは、この夫を愛のために選んだようだ。
四旬節の頃、アリス―ンは、アリスとジャンキン僧(ん?)と共に野原に出かけて、アリス―ンはジャンキンと大いにいちゃついてしまった。そこで、自分がやもめになったら結婚してくれるかとジャンキン僧に聞く。そのような話の流れに持って行く際、彼女は、自分が彼女を誘惑したのだと男に信じ込ませるよう、母親から教えられた話術を駆使したようだ。やがて四番目の夫が亡くなり、嘆くアリス―ン。葬儀にはジャンキンも参列した。ときにアリス―ン四十歳、ジャンキン二十歳。月の終わりには、彼らは結婚していた。
わたしは思慮分別などで恋をしたことは一度もありません。いつもわたしはわたしの欲望に従っていました。(中略)彼がわたしを好きな限り、どんなに貧乏だろうと、地位が何だろうとわたしは構いませんでした。
結婚後、彼女は財産を全て五番目の夫にくれてやった。しかし彼女はこれを後悔することになる。彼女が彼の本から一枚ちぎった際に、聴力に問題が出る程、夫が強く殴ってきたからだ。ここから彼女の話はその経緯の説明に移行する。ただし相変わらず脱線が多いので、最初はその説明に移ったことはわかりづらい。
夫は結婚後、故事等を引いて女房の欠点を矯正しようとする。だが人から欠点を指摘されることをアリス―ンは好まない。彼は読書が趣味であり、その中には悪妻のことが書いてある本の読書も含まれていた。良妻の話よりも悪妻の話をより知っていたぐらいだった。アリス―ンは主張する。どんな学者も女性聖人の話以外で女をよく言うことはない。だが女が学者のようにもし物語を書くなら、男の悪行が大量に書かれるはずである。男を持ち上げて(そのために?)女を落とす――などと女性が悪く言われがちなことについての文句を脱線気味に述べた後、アリス―ンは本題に立ち戻り、五番目の夫が本で読んで得た、邪悪な妻の、極端な故事や伝説をたくさん紹介してきたことを語る。おまけに、以下のようなことまで(諺かもしれないが)妻に語る。
「しょっちゅうがみがみ言うような女と一緒にいるよりか、獅子か恐ろしい竜と一緒に住んだ方がましだ」
「同じ部屋の中でがみがみ言う細君と一緒に住むよりか、高い屋根裏部屋に住んだ方がましだ。彼女らはとても邪でひねくれた性だから、夫が愛しているものをいつも嫌うのだ。女は下着を脱ぐとき恥じらいも脱ぎ捨てるのだ」
「美しい女は、純潔でなければ、豚の鼻にはめた金の指輪に等しい」
そらまあ妻がブチ切れないわけがおまへん。現代だと、夫が、結婚は男にとって損だというネットの戯言を得意げに妻に聞かせるようなものですね。『カンタベリー物語』のこちらの方がもっと酷いですが。ええよやったれ、読者の俺が許す。
というわけで、こういった本を読むのを夫が止めないと見て取ったアリス―ンは、読書中の夫の手から本の三枚*4を引きちぎって、夫の頬をげんこつで殴る。夫は炉の中にもんどりうって倒れるので、相当な勢いで殴ったのだと思われます。夫は立ち上がりこちらもげんこつで妻を殴る。妻は床に倒れてこちらは一時動かなくなった。驚いた夫は逃げ出そうとするが、目を醒ましたアリス―ンは跳び上がって「財産を狙って私を殺したのか(大意)」と問い詰める。夫は許しを請い、話し合いを経て、夫が持つ本は全て焼かれた。そしてアリス―ンは家庭の全権(財産の管理も含めて)を握ることになる。夫は、妻が生涯好きに振舞って良いこと、妻の名誉を維持することを約束し、妻は夫の体面を守ることを約束する。以降、夫婦はこれを守り、言い争いなく暮らすようになった。めでたしめでたしといったことろであろうが、五番目の夫に関しては、アリス―ンは少々脇が甘かったように思う。人を見る目がなぜかこの際は曇っている。恋愛で人を選ぶとこうなることもある、ということかしら。
……以上の話を語り終えた後、バースの女房はぬけぬけとこう言い放つ。
さてもし皆さんがお聞き下さいますなら、わたしの話をいたしましょう。
そう、「話」はまだ始まってすらいなかったのである。
召喚吏と托鉢僧の間に取り交わされた言葉
托鉢僧はここで呵々大笑し「これは長い前置きでございますな!」と叫び声でツッコミを入れる。気持ちはわかる。これに召喚吏がなぜか強く反応し、邪魔だ黙れ(大意)と托鉢僧をこき下ろす。
なんだってお前は前置きなんぞと言うんだい。なんだって!
いや企画趣旨からしたら、托鉢僧の言う通りこれまでの話は前置きでしょ? しかし、この引用部分には、チョーサーの創作者としての本音が滲んでいる。作者にしてみれば、バースの女房自身の物語は、本編であるお話と同じく、自らの創作物である。しかも力が入っているのは明白。普通の前置き扱いをしてくれるな、ということなのだろう。
さて托鉢僧は召喚吏の文句を受けて、召喚吏の笑える話をしようと言い出す。すると小官吏は、ではシッティングボーンに着く前に、托鉢僧の笑える話を二つや三つしてお前の心を呻かせると脅す。宿の主人が止めに入り、バースの女房に話をさせよと諭す。バースの女房は、托鉢僧の許しを得られるなら話を続けると言うが、これに対して「結構ですとも」と促したのは宿屋の主人である。
『カンタベリー物語』には粉屋v.s.家扶という対立があったが、托鉢僧v.s.召喚吏は更に露骨である。他の人パートにまで出張って来ていがみ合うのだもの。言い争う内容もより直接的で、話の目的が相手を揶揄するためであることを、まだどちらも話していない段階で明言してしまう。新しい対立の形であり、枠物語の有効活用が一歩進んだ印象である。托鉢僧の頭越しに話を進めるよう仕切る宿の主人も可笑しい。もっとも、托鉢僧が身振りで了承した可能性もある。
そして、やっと、本当に、バースの女房の序が終わって、話が始まるのである。
バースの女房の話ここに始まる。
アーサー王の古の頃、この国は妖精に満ち溢れていたが、今やすっかり見ることができなくなった。托鉢僧がありとあらゆる所に祝福を与えながら歩き回っているからだ。おかげで女も安全にあちこち歩ける。
どの茂みにも、あるいはどの樹の下にも、托鉢僧以外に誰も悪霊はおりません。ところで、その托鉢僧が女たちにたいし、辱めることよりほかには何も知らないときておりますから始末が悪い話です。
やっぱり女房さんは托鉢僧にムカついておられる! この妖精云々、托鉢僧云々は、以下に続くアーサー王の騎士の物語とは何の関係もない。この嫌味を言わんがためにわざわざ付け加えた個所なのだろう。「托鉢僧以外に誰も悪霊はおりません」という表現も、暗に托鉢僧は悪霊のようなものだと仄めかしているようで面白い。バースの女房、やっぱりいいキャラしてるわ。
ともあれ、アーサー王の家来に若い騎士がいた。彼は乙女を見て、その処女を力ずくで奪ってしまう。訴えられた彼は、死刑を言い渡されたので、アーサー王に慈悲を乞うた。王は生かすも殺すも思いのままにして良いと、妃に騎士を与える。王妃は、12か月と1日以内に、女性が最も望むものは何かを調べて答えるよう命じる。騎士は答えを得るためあちこちに出かけて様々な人に「女性が何を一番愛するか」を訊く。だが答えは十人十色でバラバラであった。その答えの一部については、バースの女房自身がツッコミを入れていく。特に、「心変りせずに思慮深いものと思われ、一つの目的にじっとしがみついていて、男の人が話してくれることをなんでも暴いたりしないこと」に対しては、「熊手の柄ほどの値打ちも」ないと指摘し、王様の耳は驢馬の耳の、秘密を知っていたのが妻だったバージョンの伝説を紹介して、女性が秘密を隠し通すことはできないとする。
結局、騎士は女性が最も愛するものを知ることができず、失意のうちに家路につく。その途中で彼は、貴婦人の一団が踊っているのを見かけて、ヒントが得られれるかもしれないと近付く。ところがその場所に行き着くと、一団は消えていた。代わりにとても醜い年老いた女が草の上に座っていた。彼女は助けになろうと言う。騎士は婦人が最も望むものは何かと質問し、老婆は、もしそれが騎士にできることならば騎士は自分に対してそれをしなければならないと言った。騎士がきっとそうすると誓うと、女はこれで騎士の命は安全だと言う。騎士は宮廷に戻り、約束通り、王妃の課題に対して回答を示す。
女性たちは愛人に対してはもとより、夫に対しても支配権をもつことを願い、彼の上に君臨することを願っております。
宮廷中の既婚者も未婚者も寡婦も、騎士の言ったことには反対しなかった。そればかりか、騎士には命を助けられる値打ちがあると評価された。ここで年老いた女が立ち上がり、自分が騎士に答えを教えたと言った後で、誓約を持ち出す。つまり、騎士はこの醜い老婆を娶らねばならないのだ。騎士は、全財産と引き換えに自分を自由にできないかと泣きつくが、女はすげなく拒否。妻、夫に愛される人*5でなければ承知できないと主張する。騎士は地獄だと嘆くが、やむを得ないので結婚して妻と共に寝床に行く。宴会などは一切開かれず、王妃との面会の翌日に騎士は女とひっそりと結婚し、昼間はずっと隠れていたようだ。
さて床入れしても、騎士の悲しみは晴れず、寝返りをし、輾転反側する。年老いた醜い妻は笑顔で、妻に対する仕打ちとしてはひどくない?(大意)、直すべきところがあれば直すよ(大意)と問いかける。騎士は「直してだって?」と反応して、もう直すことなんてできはしない、醜い、老いてる、身分も低い、心臓が裂けたらいいのにと嘆く。
ここから妻の長い説教が始まる。夫が態度を改めたら直す術はあると言った上で、「だが」と続けて、気高さは由緒と富裕に由来するものの結局は生き方によってこそ担保されるのだから、今の横柄な態度には何の意味もないと懇々と説く。続いて貧乏については、貧乏は心配事から人を解放する効果もあり、貧乏は何の苦しみも与えないと説く*6。老いについては、老人を敬うべきなのは常識ではないかと説く。醜く年を取っている件については、これは間男される心配がないということだと説くけれど、これについては夫の欲を満足させてあげましょうと言い、以下のような選択を迫る。
死ぬまで醜くて年を取っているけれど、あなたには真実のつつましい妻であって、生涯一度もあなたの気に入らないことのないのと、それとも若くて美しいが、そのためにあなたの家(中略)へ、訪問者がぞろぞろやって来るような機会をつくるのと、いずれか一つをね。
騎士は熟考して、溜息をついた後、その選択を妻に委ねる。妻が夫の支配権を得たのだ。それを騎士も認める。そうすると、妻は両方ともになると宣言する。夫がカーテンを開けると、そこには美しく若々しい女がいた。喜ぶ夫は彼女に千度もキスをする。一方、妻は夫に喜びや楽しみを与えるようなことについて、何でも夫に従った。かくして二人は完全な喜びのうちに生涯を送る。
バースの女房は、最後に、妻たちに対し、優しくて若く床ぶりが初々しい夫と、夫より長い寿命をキリストに願う。妻の指図を受けるのが我慢できないような夫には命を短くしてくれるよう祈る。年寄で怒りっぽい吝嗇家には即時に疫病を見舞うよう願う。いい根性してる!
この物語には、ご都合主義臭、それも物語にとってではなく、バースの女房にとっての都合のよさが感じられます。しかしながら面白いのは確か。説教めいた場面も嫌味がなくて結構楽しく読めてしまう。配偶者を支配したいと願うのは、まあぶっちゃけ夫側にもそういう奴多いだろうし、わかりますとても。そして実際に結婚したこの二人が、どちらか一方の都合でのみ生きていくことにはならなそうなことを書かれているのは、喜ばしいし、これが現実的な「幸福な夫婦生活」なのだろうと思います。……ただし、性犯罪者が幸福な生活を送れるようになって良かったのか、一抹の不満は残ります。殺されないまでも、いてこまされるべきでは?
総評等
バースの女房さんが強烈。序における自分の話はもちろん、話本体においても、結構な割合で自分の意見を開陳しており、語り手に血が通っていることを痛感させます。考え方への賛否はもちろんあるでしょうが、14世紀人だから21世紀人の基準で判断してはいけない、という場面は稀で、21世紀人としてある意味対等に扱えて、共感ないし反発できる*7のは素晴らしいと思います。
なお、彼女は総序の歌にて、耳がどういうわけか遠いことが書かれていた。その伏線が回収されたということになるだろう。
*1:ただし処女そのものは否定していません。処女をありがたがる行為そのものを批判しています。
*2:難じているように読めるエピソードもあるが、アリス―ンは、回数指定はないと主張する。
*3:中公文庫版ではこの親友も「アリス―ン」と翻訳されているが、言語はAlysらしいのでアリスと表記します。
*4:枚数がいつの間にか増えているのは笑いどころ。
*5:愛されるとの条件は回答に入っていないので、結婚して夫は支配できるが、愛されることまでは要求できない気がする。ただこれは21世紀人としての発想なのかもしれない。14世紀に「夫婦は愛し合わなければならない」という強い縛りが所与の前提としてあるならば、女の主張は正しいことになる。
*6:しかも騎士の財産は結婚によっては減っておらず、結婚によって貧乏になったわけではない点には留意したい。
*7:私はほぼほぼ共感側です。
カンタベリー物語 弁護士の物語/チョーサー
宿の主人が一団の者に与えた言葉
宿の主人の知識によると、時は4月18日午前10時(時間は太陽の位置からの推定)。彼は一団を振り返って、時は間断なく流れていくので無駄にできないとして、弁護士を話し手に指名する。弁護士はこれを快く受諾する。
直前の(未完とはいえ)料理人の話との関連性は一切示されない。時間も午前10時である。ということで、解説によれば、弁護士の物語は翌日最初の話だろうと推定されている。妥当だと思います。
そして、粉屋・家扶・料理人のときと異なって、宿の主人が弁護士相手には、下にも置かぬ丁寧な対応をしている。
「弁護士様」と宿の主人は言いました。「あなたの祝福を願って、一つ約束通りにお話をしてください。あなた様は、この度、わたくしの指図 に従うことにあなたの気高いお心からご同意下さいました。さ、あなたのお約束を果たして下さい。そうすれ ばあなたの義務だけは果たされたことになります」
粉屋・家扶・料理人にはあんなに砕けた態度を取っていたのに、お前誰だ、と言いたくなるほどの豹変ぶりである。弁護士はそれほどの上流階級ということなのだろうか。今でも弁護士相手には、誰もが(弁護士同士でも)先生先生と連呼することに思いをはせました。
さてこの要請を快諾する弁護士は、契約を破るのは望まない、約束は負債だ、約束は守ると、にこやかにではあるが実に法律家らしい答えを返す。ただ自分は値打ちのある話を知らないと謙遜する。そしてチョーサーには韻の技術に長けてはいないようだが様々な物語を知っていると、唐突にチョーサーを褒め始める。そして、チョーサーの著作2作を、かなりの字数を使って説明する。ダイレクトマーケティングですなー。そして弁護士は、韻文はチョーサーに任せて、散文で物語を始めるとする。だが『カンタベリー物語』は、ここも含めてほぼ全て韻文なのであった。
弁護士の物語の序
弁護士の物語は、ここから韻文色が訳文上でも強くなる。本人が前のパートで、自分は散文で語ると明言しているのだから、これは弁護士が散文で語った内容をチョーサーが韻文に仕立て直したということであろう。弁護士にはそこそこ程度にしか評価させなかった韻文について、実際にはチョーサーは自信満々だったのであろう。
ここで弁護士は、貧乏は大変だぞ(大意)と話し始める。生活は苦しいし、苦しいのをキリストが助けてくれないとか言い出すし、尊敬も得られない。それに比べて裕福な貿易省は幸福である。しかも各国の情勢に通じ様々なことを知っている。弁護士は、彼らがいなければこれから語る話も知らなかっただろうと言う。
衰退国の住民でおまけに氷河期世代の人間にとっては、喧嘩売ってんのかという内容である。でもこれはチョーサーの風刺かもしれない。
弁護士の物語ここに始まる。
イスラム教徒であるシリア大公は、ローマの皇帝*1の娘コンスタンスが美女にして才媛であると聞き及び、彼女を手に入れなければ死ぬなどと言い始めて、外交交渉の結果、国ごと洗礼を受けて姫と結婚する運びになった。そしてコンスタンスは供の者と船で出航した。出発にあたり、姫は悲愴な決意を述べる。弁護士は神や皇帝に文句を言う。面白いのは皇帝に対する文句で、出航の時期の設定に関して「もっといい占星学師はいなかったのか」と詰る。現代では「何言ってんだコイツ」ものであるが、14世紀においては真っ当な批判だったはずである。興味深い。一方シリアでは、大公が先例に合わせて生贄の儀式を廃止しようとしていた。大公の母は大臣たちと諮り、先例を受け容れるふりをして後で血の雨を降らせることを決める。そして彼女は息子の大公に、先ほど改宗したと嘘を付き、以前からキリスト教に改宗したかったとこれまた嘘を付く。喜ぶ息子に口づけをして、母は家路につく。
第二部以降もずっとそうだが、弁護士は自らが語った登場人物の先ほどの心情や行動に対して、聖書や古代の歴史的挿話を引いて、歌の詠唱よろしく感想を付随していく。このため弁護士の物語は、ストーリー自体の内容に比して字数が大幅に増えており、かなり叙事詩的な色合いを帯びている。『カンタベリー物語』でこういうのはこれが初めてです。なかなか面白い。
内容については、イスラムへの偏見がこれでもかというほど強調されていてびっくりします。生贄の儀式があると思われていたのかしら。この頃、ヨーロッパ世界は既に何度も十字軍を経験しているはずなのだが。あと気になっているのは、幕切れの大公の母がどういう気分であったかである。欣喜雀躍する息子を前に、彼女は何を思ったか。まあ権力闘争を前に実子など屁でもない、という権力者は歴史上とても多いだけに、何も感じてはいないかもしれない。ただチョーサーがそういう人間を自分の物語に用意したかというと、どうなのだろう。
第二部これに続く。
コンスタンス姫一行は海路でシリアに到着した。大公の母はコンスタンスに、自分の娘であるかのように接し、やがて大公も出御し、キリスト教徒たちも出席して華々しい宴がおこなわれた。そして宴の最中に、大公とキリスト教徒たち――ローマからの随員はもちろん、大公の意を受けて洗礼を受けた現地の人も含む――は残らず惨殺される。ただ一人、コンスタンス姫だけは殺されずに、舵もない船に乗せられて、いくばくかの宝物、食べ物、衣類と共に、海に送り返されたのだ。しかし彼女は神の思し召しか知らず、三年間漂流して、異教徒の地である北イングランドのノーサンバランド*2に漂着する。近くの城の城代にコンスタンスは保護されるが、自らの素性を決して明かそうとはしなかった。コンスタンスは長い間そこに留まり、熱心に祈りを続けたので、現地の人は彼女に感化され、城代の妻をはじめキリスト教の信者が増えていった。
やがて、ある騎士が、コンスタンスに言い寄ったが撥ねつけられたのを逆恨みし、城代の妻を殺害してその罪をコンスタンスに擦り付けてくる。城代の主(つまり正式な城主)アラ王の前で裁きにかけられるコンスタンスであったが、奇跡が起きて冤罪は晴れた。そしてコンスタンスはアラ王と結婚する。しかしアラ王の母ドネギルドは、息子がコンスタンスと結婚したことを恥と捉えていた。
やがてコンスタンスは男子を生む。出産時にアラ王は出払っていた。子の身体は健康そのものであったが、ドネギルドはそれをアラ王に知らせる手紙を途中で手に入れて改ざんし、コンスタンスが悪魔を生んだとアラ王に知らせることに成功する。そして、アラ王は悲しみながらも妻と子を気遣う手紙を出すが、ドネギルドはこれもまた書き換えて、コンスタンスと幼児を船に乗せて海に流すようノーサンバランドの城代に命じる内容にしてしまう。城代は嘆きながらもこの命令書に従い、コンスタンスとその息子を海に流してしまうのだった。
というわけで、舞台がイングランドになりました。同じ異教徒の地なのに、シリアとの扱いの差は何だ。これだから現地人の書いた現地が出て来る国際冒険譚はダメなんだよ!(戦中期に書かれた日本の子供向け冒険小説を脳裏に浮かべながら)
姫は海流頼みでシリア→ギリシア→モロッコを経由し、イングランド北部北海側のノーサンバランドに漂着する。めちゃくちゃなルートで無理が過ぎるが、キリスト教圏以外の地理関係やを当時の人がいかほど認識していたかは甚だ疑問なので仕方がないのかもしれない。そしてこれなら、物語をイングランドに持ってこれますからね。
コンスタンスに城代の妻殺しの濡れ衣を着せるため、騎士は、凶器をコンスタンスの傍に置いておくというトリックを弄する。今や誰でも思いつく初歩的手法ではあるものの、これは紛れもなくトリックです。14世紀の書物にこれが記載されている事実は、ミステリ・ファンとしては痺れるものがあります。現代人が中世を舞台に書いた小説ではなく。中世人が中世を舞台に書いた小説にこういうことが書かれている事実! 冤罪を晴らすのが神の奇跡なのはミステリ・ファンとしてはガッカリなのが残念です。というか、イングランドで奇蹟は起こすが、シリアでは大量虐殺を静観した神って、本当に神なんですかね? シリアにいるキリスト教徒全員の命より、コンスタンス一匹の命が重いの? 神を試すなと言われそうだが、そんな神要る? 崇拝に値する?
そして、こっちでも首長の母親が諸悪の根源なのかよ! この物語を作った誰かが母親に遺恨があったとしか思えない。そしてこちらの方が、シリアの大公の母よりも遥かに陰湿です。ただこれは、シリアでの事物よりもイングランドの事物の方を強調して重きを置きたいがために、解像度を上げただけのような気もします。しっかし本当に胸糞。情報伝達をダブルライン化していなかったり、命令確認手段が用意されていなかったり、母親を信用してしまったりする落ち度はあれど、それでも胸糞。
興味深かったのは以下の一文です。
結婚した妻たちはまことに聖なるものでありますが、指輪をもらって結婚した夫の数々の快楽の行いにも、やむをえぬこととて夜じっと耐えなければなりません。
性行為に対するこの皮相な見方! 14世紀においても、これが一般的であったかは、『カンタベリー物語』の他のパートを読む限り、結論は明らかのように思います。上流階級ではこういうのが普遍的だったのかもしれない。あるいは、コンスタンスはアラ王と結婚なんかしたくなかったことを示唆しているのかもしれません。
第三部これに続く。
城に戻ってきたアラ王は、妻と子がどこにいるか尋ねる。城代の説明等により全ては明らかとなり、王は母を殺害した。そして昼も夜も妻子のことを悲しみ続けるのだった。一方コンスタンスと息子は5年間漂流する。途中異教徒の支配地に船が一時打ち上げられて、現地の城主の執事がコンスタンスを愛人にしようとするが、コンスタンスが抵抗したので彼は海に落下し溺れるなどした。結局彼らは、ジブラルタルとセウタの間を通過し*3、皇帝の命でシリアを討伐した帰路にいる元老の船に拾われる。元老はコンスタンスと息子を保護するが、彼女が皇帝の娘であることに気が付かない。ローマに戻った元老は、コンスタンスと息子の世話を妻に託す。この元老の妻はコンスタンスの伯母だったが彼女もコンスタンスに気付かない。やがて、讀罪のためアラ王がローマ教皇の元に巡礼にやって来る。元老はアラ王の宿所で彼を歓待する。その歓待の席には、コンスタンスの息子(つまりアラ王の息子)を連れて行く。息子は母の言いつけ通り、アラ王の顔をずっと見ていた。アラ王はこの男子を不思議に思う。なぜならコンスタンスに顔がそっくりだからだ。元老に話を聞き、この子の母はコンスタンスかもしれないと、彼は後日、元老の屋敷を訪ねる。アラ王とコンスタンスは再会するが、コンスタンスはアラ王の命令で海に流されたと思っているので、悲しみのあまり立てず、アラ王の目の前で二度も失神する。が、アラ王は彼女に何とか事実を説明することに成功し、幸福を取り戻す。
この後、コンスタンスは、アラ王に頼み、自分の父である皇帝に自分のことを知らせないよう願う。息子マウリスは、アラ王と皇帝の面会の場に同席し、皇帝はマウリスの会を見てコンスタンスのことを思う。そしてアラ王は、皇帝との宴会を用意し、妻と共に出迎えに行く。コンスタンスは父である皇帝と再会し、自ら名乗る*4。大団円である。後にマウリスは教皇により皇帝となった。アラ王はコンスタンスと共に帰国するが1年後に亡くなる。夫を失って深く悲しんだコンスタンスはローマにもどって来る。親しい友人は皆生きていて、父親の皇帝も生きていた。コンスタンスは嬉し泣きする。
繰り返しますが大団円です。波乱万丈の極みだった第二部に比べると劇性はだいぶ落ちます。面白さも正直だいぶ落ちます。でも特にコンスタンスの言動に、本音が見え隠れする局面が多いように感じられました。アラ王と幸福に暮らしたとは書かれているものの、実際にはずっとローマで暮らしたかったのだろうなと。そして本当に、時代設定がめちゃくちゃですね。教皇がローマ皇帝を戴冠するようになったのにローマに皇帝が常駐していて、なおかつイングランドが異教徒、シリアにはイスラム教徒かあ。
弁護士の物語のエピローグ
宿の主人は鐙の上に立って、弁護士の話が有益な話だったと言う。そして次の話者に司祭を指名し、巡礼団には司祭がこれから説教をなさると宣う。だがそこに船長が横槍を入れ、自分が愉しい話をすると言う。
船長の横槍への反応は誰のものであれ記録されていない。彼が一方的に宣言してこのパートは終わってしまう。じゃあ次は船長の話なのかというと、違う。『カンタベリー物語』は各エピソードの順番にも議論のある小説であり、実際には次は船長の話だったのかもしれない。しかし少なくとも、私が読んでいる岩波文庫版では、次はバースの女房の話なのである。
総評等
コンスタンスが中心にいる話なのに、コンスタンスの人格の印象がとても薄い。自主性もあまり感じられない。時々本音が漏れ見える程度。キリスト教に敬虔なのはわかりますし、異教徒に対する偏見に満ちているわけでもないが、生身の人間という気がしないんですよねえ。完全に物語のための道具。この時代に女性はそう描写されるものなんだよ、というわけでもない。シリア対応の母親や、アラ王の母ドネギルトは、悪役ながら活き活きしています。
物語にとって都合の良い奇跡しか起きない。シリアでは災難に遭っているし、漂流期間が計8年と長いため、コンスタンスが特別愛されている気もしない。イングランド人が満足すように物語を盛り上げるための奇跡ばかりだ。あとイングランド人の扱いが、元は異教徒なのに良い。これまた都合が良い。
*1:ローマに皇帝がいて、シリアを支配しているのがイスラム、というタイミングが歴史上にあったか疑わしい。神聖でもローマでも帝国でもない国家の皇帝がローマにいたタイミングを狙えば何とか、というところだろうが、そういう人いたんですかね。姫も一緒なのだから皇帝はローマに住んでいないといけないし。
*2:この地方がキリスト教化していない時期、イスラム教は生まれてすらいないのではなかったか。時代考証上おかしいのは、皇帝がいるというローマではなく、イスラム教国のシリアだったのだった。
*3:ということは北海から地中海に流れたということになる。
*4:この際の名乗りが少し嫌味ったらしい。「塩の辛き海に、一人で押しやられ、死ぬべき運命を与えられたのはこのわたくしでございます」そりゃまあ皇帝の命令でシリアに嫁がされて大変なことになったのだから、これぐらい言うわな。