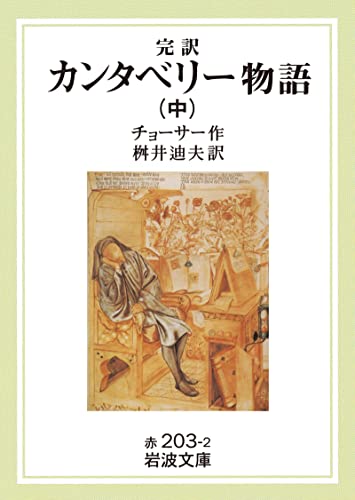カンタベリー物語 学僧の物語/チョーサー
ここにオックスフォードの学僧の物語の序続く。
宿の主は、学僧が無口で馬に乗っていると指摘する。
お願いですからもっと快活になって下さいよ!
放っておいて下さいよ!と返したいところではあるが、続く宿の主人の主張はわからぬでもない。彼は学僧に話を促すが、聞き手の罪を思い出させるような話、眠たい話、学問的な言葉、修辞学の飾り文句*1等はやめて、平明な話を要請する。
学僧はこれを受け容れて、パドヴァで故ペトラルカから学んだ物語を語り始める。なおペトラルカは序文で、物語の舞台となるイタリアの西部のモンテ・ヴィゾー*2から、ポー川が西に流れることを延々と描写しているとのことだが、それを書き記すと長くなるので、ばっさりカットすると断る。
学僧はパドヴァに行った口ぶりである。つまり現地でペトラルカから話を「学んだ」らしい。これが、実際に対面で話を聞いたのか、残された文章を読んだのかは不分明だ。序文の話をしているので後者かもしれない。しかし、彼は巡礼の道中で実際に喋っているという設定であるにもかかわらず、ペトラルカの序文を「書き記すと」と言ってしまっている。訳文の問題かもしれないが、仮に原文もこのような表現だとすると、この当時にあっては、「口頭で話す」という設定よりも「作者が書いて読者が読む」というメタ的現実が優先されるのが常だった、と理解すべきなのかもしれない。現代の読者、特にミステリ・ファンが気にするような表現の統一は、中世では誰も気にしていなかったのだろうか?
オックスフォードの学僧の物語ここに始まる。
ヴィゾー山の麓サルッツォを統治する侯爵ワルテルは、統治能力があり敬愛されていたものの、狩に熱中する悪癖があり、しかも妻を娶ろうとしなかった。領民たちは問題視して、侯爵の所に押しかけた。代表者は侯爵を賞賛した後、「でも早く結婚してくれ、グズグズしているとすぐに年を取るし死ぬぞ(大意)」と言って、家系が断絶するのは自分たちにとっても悲惨だ、と結婚を迫る。
領主様、もしあなた様が御同意下さいますならば、わたくしたちはこの国で最も高貴で、また最も偉大な家のお生まれである奥様をあなた様のためにお選びしようと存じます。
放っておいてやれ!と言いたいところではあるが、残念ながらここは中世であり、領主の結婚(と特にお世継ぎ問題)は領民としても下手をすれば死活問題なのだ。侯爵は憐れみを催し、自分は自由に楽しんできたが結婚したら奴隷になるだろうなあとぼやきつつ、早々に結婚することに同意する。しかし、妻は領民で選ぶのではなく、自分で選ぶと言う。そして、以下を誓えと領民たちに言う。
わたしがどんな妻を娶ろうとも妻の生きている限り、言葉でも、行いでも、ここでもどこでも、あたかも皇帝の娘のように妻を尊敬するということをわたしに約束して欲しいということだ。
(中略)
お前たちがわたしの選択に対しては不平を言ったり、逆らったりすることがないように、ということだ。
フラグに見えるが、さてどうなるか。ともあれ領民も誓い、また侯爵は自分が必ず結婚する日も決めた。領民たちは帰り、侯爵は宴会の準備を家来に指示する。
第二部始まる。
侯爵の宮殿から遠くない小さな村に住んでいる、村で最も貧しい村人ジャニキュラには、見目麗しく徳も美しいグリゼルダという娘がいた。彼女は働き者で、まじめであり、父親のことも敬っていた。侯爵は狩に出かけた折にグリゼルダを見初めており、結婚するなら彼女とだろうと思い定めた。
侯爵は婚礼の日まで誰が花嫁か明かさず、グリゼルダ本人すら何も連絡せず、結婚当日に彼女の家を訪れて、ジャニキュラに自分はグリゼルダを妻に迎えようと思う、と下知する。そして、グリゼルダと二人で話し合いの場を設ける。そしてこんなことを宣う。
あなたがすすんでわたしの願いにすべて応じて下さるということ、そしてまた、(中略)わたしがあなたを笑わせようと、苦しめようと、わたしは自由で、しかもあなたは日夜そのことで決して不平を言わないことです。またわたしが「そうだ」と言うときに言葉でも顔をしかめても「いや」と言わないこと、このことを誓ってほしい。
勝手なこと抜かしてんなこの領主。しかしグリゼルダはこれを受諾してしまう。そしてジャニキュラの家から出た侯爵は、グリゼルダが結婚相手であり、皆が彼女を愛してほしいと宣する。領民に愛情を指示したのは救いです。
女官たちに格好を整えられたグリゼルダは、知り合いが信じられないぐらいの美貌となり、おまけに挙措も美しい。結婚後も彼女は領主の妻として立派な態度を誰にとっても取り続け、評判を得る。夫との関係も良好で、適切な助言すらし、夫の不在時は領主代行すら円滑にこなした。やがて彼女は女児を産む。
フラグ臭はびんびんながら、結婚生活の滑り出し自体は好調である。
第三部始まる。
冒頭から一気に不穏になる。
次のようなことが怒りました。それはしばしばあることなのですが*3、つまり、この子供がしばらくの間乳を吸っていたときに、この侯爵は妻の一貫した誠実さを知るために彼女を試してみようという気が心の中に強く起こったのでした。
次の段落で、語り手の学僧もこの夫にはさすがに否定的になる。夫には似つかわしくないという言葉すら踊っていて、なるほど登場人物は人格に問題があっても、語り手はマトモなんだなと思わされます。
侯爵はグリゼルダに、貧しく卑しいお前を富貴の身にしたのは俺だ、と恩着せがましいことを言い、小さな村で生まれた人間の指図を受けるのを恥辱視する人間もいる、と今更なことを言い、娘のために最善は尽くさねばならないが、グリゼルダではなく領民にとっての最善でなくてはならないと言う。グリゼルダは誓いは守るとして、娘の処遇を全面的に侯爵に委ねた。侯爵は内心これを喜んだが表情は憂鬱にした。そして腹心に指示して、娘をグリゼルダから取り上げさせる。その際、腹心はグリゼルダに、侯爵の命令には逆らえない誓いを立てていらっしゃいましたよね、と言わせている。グリゼルダはこれにも即座に唯々諾々と従い、娘に今生の別れを告げる。
え、「お前の夫の命令だ」と言うだけで、グリゼルダはどんな指示にも従うんですか。もの凄いセキュリティホールが開いている気がする。ともあれ、グリゼルダから娘を取り上げた家来は、侯爵に娘を差し出す。家来がセキュリティホールを悪用する人間でなくて良かったです。侯爵は秘密裏に、ボローニャ近くのパニコの伯爵に嫁いでいた自分の姉に、娘の養育を任せて送り出すのだった。片やグリゼルダは不満の顔一つせず、愛娘の名を一切口にすることはなくなった。
第四部これに続く。
四年後、グリゼルダは男児を産んだ。侯爵はまた妻を試す気になってしまう。
結婚した男というものは辛抱強い人を見つけると節度を知らないものだ。
いきなり箴言で刺してくるのは止めてください学僧さん! そして今度は侯爵は、領民がジャニキュラの血筋の者が次の領主になるのを喜ばないので、息子もその姉と同じくこっそり始末を付けると言う。誓約通りグリゼルダはこれに従う。グリゼルダから息子を実際に取り上げるのは、侯爵自身ではなくまた例の腹心でした。この人も大変だな。そして、息子がいなくなっても約束通りに振舞う妻を見て、侯爵は更なる試練のために謀を巡らす。
さてグリゼルダの娘が12歳になった頃には、領民からの侯爵の評判は悪化していた。娘と息子を侯爵が殺害したという噂が立ったのだから当たり前、自業自得である。これを奇禍として、侯爵は領民の安寧のため、彼が望むなら別の婦人と結婚しても良いというローマ教皇の勅書を偽造する。この偽造勅書を侯爵は公表した。グリゼルダはショックだったに違いないが、相変わらず態度には全く出ない。そしてボローニャの伯爵に、娘と息子の姉弟を威儀を正して、しかし素性は隠したまま、国に連れて帰ってくれるよう要請する。……これは間違いなく、侯爵が、伯爵に縁のある若い女性(実際には娘)と結婚する振りをしようとしているな。
第五部これに続く。
侯爵は、領民が別の妻を娶れと言っているから、新しい妻に場所を譲るようグリゼルダに迫り、結婚時に持って来たものは実家に持って帰るよう言い渡す。グリゼルダはこれにも唯々諾々と従う。侯爵と新妻を祝福することすらする。そして、自分が宮殿に来た際は、そもそも実家にいた際に侯爵が下賜した豪華な服を着、宝飾品を付けてやって来たので、それらも返す、さすがに持ち帰ることができない処女の報償として、下着はもらいたいと言う。そしてその宣言通り、着物を脱いで、下着姿のまま父の家に向かって進んで行った。人々は涙を流しながら彼女に従って行き、父は侯爵の生まれた日を呪う。しかしながら、グリゼルダは引き続き健気であった。
侯爵もおかしいが、グリゼルダも明らかにおかしい。ちょっと怖くなってきた。
学僧は第四部を以下のように締めくくる。
人はヨブのことを語ります。しかも殊に彼の謙遜なことを語ります。それは学者たちが好きな時に、特に男性について上手に書くことができるとおりです。だが、真実のところ、学者たちは女性たちをほとんど賞めることはいたしませんけれども、謙遜なふるまいをすることにおいて女性に匹敵するものはありえませんし、また女性の半分も真実な男もありえません。
「謙遜」なんてレベルじゃないだろ、という気はするが、これは紛れもなく「男って良く書かれるけれど、女性については書かれないだけで、実際は女性も素晴らしいよね」的な概念である。先進的と言い得るのだろうか。それとも当時これは一般的だったのか。
第六部
ボローニャから伯爵一行が近づいてくる。新しい侯爵夫人と言われている若い娘を従えて。侯爵はグリゼルダを迎えにやり、新しい妻を盛大に迎えたいが、自分の望み通りに部屋をきちんと整えることができるのはグリゼルダだけなので、お前は貧相でみすぼらしいけれど、召使として奉仕しろと言い渡す。グリゼルダはこれも素直に受諾、館を片付け、食卓を置き、寝所を作り、侍女たちと共に宴会の準備を終えた。
やがて伯爵一行が高貴な子供二人を連れて到着した。人々はその華麗な様を見て、侯爵ワルテルも馬鹿じゃなかった、妻を代えようとしたのは最善を願ってのことなんだ、と言い合った。グリゼルダよりも若いから子供を沢山作れるだろうし、高貴な身分だから人気もより出るだろうと判断したからである。彼らは侯爵を褒め称えた。この領主にしてこの領民あり。選挙で選んだはずもないのに、何だこの同レベル感は。
祝宴の場でもグリゼルダは忙しく立ち働く。態度も立派なもので (恐らく高貴な客人からは)貧しい身なりなのに名誉と尊敬を表す術を知っている彼女は何者かと訝しがられた。グリゼルダは、乙女とその弟にも優しく、真心から賞賛した*4。そんな中、侯爵はグリゼルダを呼び、新しい妻を気に入ったか尋ねる。グリゼルダは仰る通りだとして彼女を褒めた後、侯爵に一つだけ忠告する。
あなたがほかの人たちになさいましたように、この年若い乙女を責め苦で苛まれることのないようにということです。と申しますのは彼女はわたしなどと違っていっそう優しい心遣いで養育されていられます。それに、思います②、貧しい境遇で育てられた者のように逆境に耐えてゆくことはおできにならないからです。
……微妙にキレている気がしないでもないが、ともあれ、事ここに至り憐れみを最大限に覚えた侯爵は、全てをネタ晴らしする。グリゼルダは失神するが気を取り戻すと娘と息子を泣きながら腕に抱く。そして一しきり感動した旨を述べた後にまた失神する。再度我に返った彼女に、誰も彼もが喜びの言葉を述べ、好意を示した。夫の侯爵も彼女を慰めた。グリゼルダは再び富貴の身となり、祝宴が開かれ、その後幾年も、侯爵とグリゼルダは幸せに暮らした。めでたしめでたし。なお彼らの息子は、妻を大きな試練にけるようなことは決してしなかったという。
以下、ネタ晴らしした際の侯爵の自己認識である。
わたしはこの行為をなんら悪意や残忍な心から行ったのではなくて、お前の中の妻らしさを試してみたい心からであった。
この期に及んで正当化を図っているわけですが、どう考えてもこの「試してみたい」は、現代の法律からすると悪意ないし故意なので、免責事由にはなりません。民事免責どころか刑事免責にすらはるか遠く及ばないだろうなあ。地獄に落ちろワルテル(サムズダウン)。
さて物語を語り終えた後、学僧は、現在は遠い昔よりも道徳基準がしっかりしていない*5と断った上で、自分の見解を述べる。
忍耐の点でグリゼルダを妻たちが見習うべきではない、耐えられないから。しかし逆境に、グリゼルダのようにしっかりした態度で動揺せず対処すべきである、と言う。というのも、グリゼルダがあそこまで忍耐強いからには、私たちも神が送り給うものを全て善意をもって受けるべきだからだとする。そう来たか。神はいつも人を試している。我々の弱さは全てご存じであり、我々の意志を知ろうとして試しているのではなく、鍛錬のために試している。だから忍耐の徳を旨として生きようではありませんか。
学僧は更に、バースの女房の愛のために、晴れ晴れと歌を朗唱すると表明する。
チョーサーの結びの歌
グリゼルダは既に死んだという前提での歌(詩?)である。グリゼルダの死と共に忍耐も死んだ、グリゼルダのような妻はいやしない、奥様方は黙るようなことはするな、主導権を握れ、強いんだから戦いに備えて男どもに危害を加えることのないよう獰猛になれ(喋りで)、男たちを恐れるな敬うな、あなた方の能弁は鋭いから、嫉妬の縄で夫を縛れ、美人なら顔や衣服を見せびらかせ、醜いなら費用にけちけちするな、友達を作れ、気分は軽くしておけ、主人を翻弄しろ。
第六部最後の学僧自身の語りからこの歌に至るまでは、かなり意外なことに、妻の立場への賛歌になっている。皮肉なのかもしれないが、活き活きとした奥様像に、学僧は(つまりチョーサーは)たいへんに肯定的である。楚々として夫の言うことに何でも従うグリゼルダ、ぶっちゃけ非常に不気味だったからなあ。現代の小説ならば、第六部ではホラーめいた読むもおぞましい猟奇的オチが用意されてもおかしくはなかった。それぐらい彼女は不気味です。やっぱ、御伽噺の、男に従順なだけの女はあかんな(逆も同じ)。
宿の主人の愉快な言葉をお聞き下さい。
宿の主人は、樽いっぱいのビールを飲むより、妻がこの物語を聞いてくれた方がマシだと言う。この話は、彼の意図に叶った上品なものだったようだ。しかし、ないものをねだっても無駄と言う。
私の読解力がポンコツなので、ちょっと意味が取れなかった。宿の主人の奥さんは、我が強いのでグリゼルダを見習ってほしいとの、学僧やチョーサーのスタンスとは異なる価値観の表明だろうか? それとも、彼の言葉自体が反語なのだろうか?
*1:その割には宿の主人や他の巡礼者にも、飾り文句のような言葉が多い。これは14世紀には庶民にも一般的だったのか、教育を受けた人には一般的だったのか、それとも文章(この物語は小説なので歴然と文章である)はこういうものだったのか。
*2:訳文ではヴィゾー山とされ、訳注では「ヴェスルス山のこと」と記されているが、Google検索にかけても何のことだかさっぱりわからない。パラマウント・ピクチャーズのロゴのモデルの一つと噂される山で、そう言われると何となく知った気になれる。
*3:しばしばどころか決してあってはならないのは言うまでもない。神を試してはならないのと同様、いやそれ以上に、配偶者を試してはならない。
*4:自分の子供たちだと一目でわかったのかもしれないが、そのような描写はない。
*5:21世紀からすると逆である。中世のヨーロッパ人にこの認識があったのは興味深い。