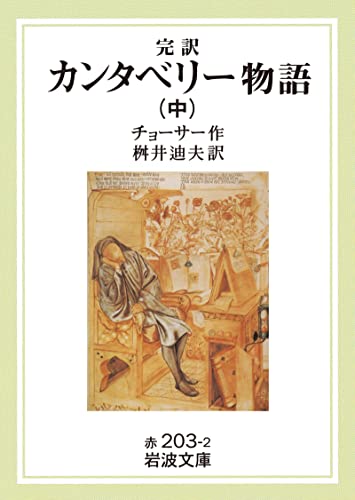吸血の家/二階堂黎人
二階堂黎人の諸作品を再評価*1したくなってきた。これ自体に理由は特にない。ただ、『容疑者Xの献身』論争における事実上の敗北が、その後の作家としての評価に悪影響を与えたのは確かであり、ここ10年ほどは、それは気の毒だと感じるようになっていた。また、私も中年となり、人生経験も浅いながら積み増しはしたため、恐らく以前の作品を再読すれば違った感想も抱けよう。告白しておくが、二階堂黎人の初期作品は私にとって紛れもなく、青春を彩った小説群の中に含まれている。恩義や親しみはあるのだ。加えて、ある程度のまとめ読みと再評価は、作家・作品に加えて読書そのものの解像度を上げる効果があり、作家を変えつつ定期的に行うべきである。2023年後半、私にとってのそれが二階堂黎人だったということである。
ただし、当方もそれなりに多忙であるため、読書ペースはゆっくりになります。1年後に二階堂蘭子シリーズを完走できていたらご喝采、ぐらいのペースを想定しています。次回更新は早速1か月以上は空くでしょう。
なお、作家・二階堂黎人は、二階堂蘭子シリーズの語り手に、自分と同姓同名の登場人物・二階堂黎人を宛がっている。よって、感想をしたためる際に、単に二階堂黎人と書いただけでは、それが作家なのか登場人物なのかわかりにくくなる。そこで、二階堂蘭子シリーズを取り上げる投稿に限り、登場人物の二階堂黎人は「黎人」と記載し、作家の二階堂黎人は「二階堂黎人」または「二階堂」と記載することにします。この注意書きは、本シリーズの感想においては、毎回掲げます。
時代設定は、昭和44年(1969年)1月である。二階堂黎人のデビュー作は『地獄の奇術師』で、しかもその事件は昭和42年11月スタートである。物語の時系列順または刊行順に読むならば、『吸血の家』は後回しにすべきところだ。しかし、ホームズはじめ大概のシリーズと同様に、二階堂蘭子シリーズも、作品の執筆順・刊行順と、作品内の時系列順は必ずしも一致しない。『吸血の家』は『地獄の奇術師』よりも先に書かれ、鮎川賞に応募され、佳作入選となった。だから創作順を無視すれば、『吸血の家』を先にしてもおかしくないのだ。
少し悩んだが、デビュー当時の状況を勘案して、今回の二階堂作品のまとめ読みに当たっては、『吸血の家』から始めることにした。今回本作は再読となる。初読の際――まだ私は高校生だった!――は、『地獄の奇術師』から始めたので、順番を変えたら感じ方が変わるかにも興味が湧いた次第である。
今回は一応章立てを行うが、毎回やるとは限らない。できるだけ自由に行きたいので、そういう縛りは入れません。
あらすじ
《血吸い姫》
物語は文政年間または天保年間に八王子宿で起きたとされる、凄惨な《血吸い姫》の言い伝えが記述されて始まる。このパートはまだ三人称だ。《血吸い姫》は八王子宿の飯盛り旅籠にして女郎屋《久月楼》での出来事とされており、吸血行為は、座敷牢に閉じ込められた姫が、同じ牢に入れられた女郎が死んだ後で、生きるため、これから血を吸っていた、という形式で行われる。吸血鬼ではない点に留意されたい。超自然的現象は、姫の死後の呪いという形で表れる。ここでも奇病にかかって死んだり火事になったりするだけで、呪われた人間が吸血行為を行うわけではない。
なお、《血吸い姫》の舞台となる旅籠は、本編の《久月》および雅宮家の前身である。
伝承パートが終わると、いよいよ舞台は昭和44年(1969年)の現代に飛ぶ。
第一の血 白い魔術
昭和44年(1969年)1月10日金曜日*2、午前10時過ぎ。関東一円で朝から雪が降る中*3、東京都の国立市にある旭通り*4の真ん中辺りにある喫茶店《紫煙》に、不気味な女がやって来て、店主・店員・常連客に、二階堂家へ伝言せよとして、八王子山合の《久月》で事件が起きる、24年前の事件も関係すると言い残し、去る。この女の足跡は、途中でふっつり消えていた。
喫茶店《紫煙》は、蘭子と黎人が所属する《推理小説研究会》が常連として入り浸る場所で、店主もミステリ・マニアで、大量の蔵書を有する。またこの話の中で居合わせた「常連」とは、《推理小説研究会》の顧問の教授と助教授である。彼らは女の登場前に推理小説談議、特に名探偵談義に花を咲かせていて、読者の印象に残るのですが、以後一切出て来ません。よって『吸血の家』においては彼らの名前を覚えておく必要はないです。
そして場面は二階堂家に移り、蘭子と黎人が登場する。彼らは雅宮家(現存するのは美人三姉妹+そのうち一人の娘、および使用人だか何だかよくわからない住み込みの夫婦。屋敷外に住む係累にも変なのがいるらしい)の状況を確認した後、24年前の事件を説明させるため、三多摩署の中村警部を呼び出す。中村警部は24年前(昭和20年、1945年)冬の、《久月》で起きた、陸軍将校殺人事件を説明する。それは雪上に犯人の足跡がないタイプの事件であった。
この事件を語る過程で、彼らは雅宮家のことに更に深く触れていく。加えて、足跡のない殺人の講義を蘭子が行う。
第二の血 呪縛浄霊
昭和44年(1969年)1月18日、蘭子と黎人は中村警部と共に、雅宮家にやって来る。屋敷では、雅宮一家の他、三姉妹の一番下の妹の婚約者、ブラジルから帰国してきたという初老の客、新興宗教の教祖を名乗る女、三姉妹の真ん中の妹の元夫がいた。教祖は怪しげな儀式をしている。
19日の夜、教祖が主催する浄霊会が開かれ、そこで事態が急変する。
20日の朝、死体が発見された。24年前の事件を第一の殺人とすれば、第二の殺人の発生である。今回も密室殺人の一種であった。
そして21日の朝にも、テニスコートで死体が発見される。これも犯人らしき足跡がない不可能犯罪であった。これが第三の殺人である。
第三の血 吸血の家
第二の血の最後で第三の殺人の一報が入り、第三の血ではその詳細が描かれる。そしてこの章で、殺人犯と蘭子・黎人とが対峙し、真相が解明される。
単体の物語として
モチーフ
二階堂黎人がモチーフをここまで和風にするのは実は珍しく、その意味で貴重な物語である。ただし、最初の呪いの伝説でわざわざ《血吸い》をさせたり、タイトルを『吸血の家』としたり、和風建築の庭にテニスコートを現出させたりと、洋風テイストにできるだけ寄せようとはしている。この点を不均衡と捉えた場合、作品の評点は辛くなるはずだ。個人的にはほとんど気にならなかった。いいじゃないですか、和風建築の屋敷の庭にテニスコートがあっても。そんなこと言い出したら、畳の部屋にテレビなんか置けなくなりまっせ。また《血吸い》も、飢餓状態に追いやられた姫が行うのが人肉食ではなく吸血なのも理由付けがなされているので、問題は特に感じない。
ただし、この和のテイストと、足跡のないテニスコートの殺人は、若干食い合わせが悪いようには感じられた。血吸い姫伝説を持ち出してテニスコートは、雰囲気が少し壊れるようには思います。変に伝説を出さずに足跡のない殺人だけに絞ったらこの弱点はなくなるが、その代わりに犯人側のアレがやりづらくなるから痛し痒し。難しい。とはいえこれはいちゃ文の類であり、モチーフによっておどろおどろしい雰囲気を出せているし、そこをベースにして哀しみの空気感も引き出せているので、問題なく奏功していると思います。モチーフの湛える雰囲気が、真相のそれと絶妙に共鳴している点は高く評価したい。
トリック等
何といっても第一の事件のトリックが鮮烈で、長く記憶に残る。私も忘れていなかった。他方、第二・第三の事件のトリックは、そこまで鮮烈ではないし偶然に頼った面もあるのが気にはなるが、十分に納得できるロジックで、現実味のあるトリックが披露される。素直に良い。
全体的には、複合的な要素が絡まり合って事件が発生しているのが興味深い。最初から二階堂黎人は二階堂黎人だった、ということがはっきり示されているように思う。事件の真相を単純化できないのだ。一行で説明しつくすのは全く無理です。ただし、訳が分からないほど複雑というわけでもなく、読んでいると結構わかりやすいのだ。何回読んでも真相がよくわからない作品、ありますからね。その点、二階堂黎人は大丈夫です。
冒頭の女の行動
二階堂家に報せを告げに行くのは良い。事件における立ち位置が彼女のような人物であれば、そうしたいときもあるでしょう。問題はなぜ《紫煙》に行ったかである。これがよくわからない。
足跡のない殺人の講義
蘭子により、足跡のない殺人についての講義が実施される。これは状況の整理としてなされるわけだが、これだけで結構楽しい。本格ミステリ・フリークならにやりとさせられる。なお蘭子は、高木彬光は社会派に逃げたことがあるから評価しない旨を述べており、狭量を感じる。
注記
本書のもう一つの特徴は、注記が章ごとに付されているということだ。これがなかなか面白い。伏線として機能するもの、真相解明章で伏線を指摘するものの他、黎人の推理小説観が垣間見れる過去作品への評価であるものもかなりあって、二階堂黎人が『吸血の家』をどう位置付けたいのかがうっすらわかるようになっている。これは効果を上げていて◎。
なお、注記の中には、マイクロフト・ホームズに関するものがある。これだけが、ノリが砕けている。
*12 ホームズの兄だよ。お兄さんだよ。
一体どうした? ここだけ完全に冗談のように砕けた態度になっている。他の注記は冷静なのに。注記以外の黎人の記述全体を見渡しても、ここだけテンションがおかしい。マイクロフト・ホームズに、黎人か二階堂黎人は、何か妙で個人的な奇縁や思い入れがあるのだろうか。あるなら語ってくれ。ということで、ここは戸惑いました。
幕切れについて
某人物の最後の選択は、初読時は少し不満で、当該人物はもっと自由に振舞っても良いのではと感じたことを思い出した。だが今は違う。既に立派な中年男性である私にとって、もう今更そっちに行くのは面倒なのは痛いほどわかるのだ。いかに名探偵とはいえ、19歳の親戚のお子様(蘭子)に、未来を見るべきだと偉そうなことを言われて感じるのは、崇敬でも怒りでもなく、年長者視点からの「まだ若いな。眩しいな」という微笑ましさだ。私ならその場で笑ってしまうだろう。冷笑、嘲笑、失笑ではなくて。
二階堂蘭子サーガとして
雅宮家との関係
雅宮家の人物で最初に登場するのは、三姉妹の長女・絃子である。彼女は本当に最初の方で登場する。黎人が帰宅すると出迎えるのだ。何なら語り手に「黎人さん」と呼ばわって、この物語で黎人の名前を最初に出す人物ですらある。
なぜ絃子が二階堂家に出て来たか。実は二階堂家は、黎人・蘭子兄妹の親である陵介・鏡子が不在にしており、絃子は二人のためにご飯を作りに来ているのである。彼女は――つまり雅宮家の美人三姉妹は鏡子の又従姉妹である。それだけ聞いたら遠縁だが、自分の不在時に子供の世話を頼んでいる。それに応えて、絃子はわざわざ二階堂邸までやって来て家事をするのだ。刑事たちが来たらお茶出しまでする。めっちゃ親しい親戚じゃないですか。
私事で恐縮だが、私も母の調子が悪かった時に、伯母(もう故人だ)に食事を作ってもらっていた時期がある。伯母には、親戚の中でも特別な想いがある。葬式でも他の親戚のそれ以上にしんみりしたものだ。
そのレベルの親しい一家がこんな大事件に巻き込まれるというのに、黎人と蘭子の親戚としての反応は薄い。彼らだけではなく、その両親の反応も本書では記載されておらず、ひょっとするとこれまた反応が薄いのではないかと疑われる。二階堂一家はどうなっているんだと言いたいところだが、兄妹に関しては、推理小説談議に花を咲かせる《推理小説研究会》所属の二十歳前後の学生は、リアルタイムではこんなものかもしれない。残りの人生のどこかで、違う考えに至るのかもしれない。
父母については、そもそも登場しておらず反応が伝えられていない。
ただいずれにせよ、二階堂家にとっても雅宮家の事件は我が事に近い大事件であったはずで、何らかの心理的影響が残ってもおかしくない。今後はそういう目線でサーガを読んでいきたい。
二階堂蘭子
態度、立場
気にならないと言えば嘘になるのが、二階堂蘭子の立ち位置である。彼女は弱冠19歳の未成年(当時)の女子大生に過ぎない。もちろん義父が警視庁の幹部なので、一定の範囲に七光りは及ぶ。これまでにも難事件の謎を解いているので、名探偵としての実績もあるだろう。しかしそれでもなお、蘭子は特別に扱われ過ぎているように思う。
-休日に警部を呼び付け、過去の事件を説明させる。
-事件現場から自由に出入り。しかも当該事件の関係者の親しい親戚であり、浄霊会にも出席するなどしている。本来なら事件関係者として扱われてもおかしくない。ところが警察は、彼女を警察側の身内として扱う。
- 《紫煙》に来た謎の女から拘りを持たれる。
- 犯人からも拘られている形跡あり。
- 名探偵とはどうあるべきか、的な会話が作中に横溢する。
蘭子は社会的には19歳の小娘に過ぎない。しかもこの作品は、鮎川哲也賞応募作、つまりはデビュー前の処女作に近い。その中で、彼女が名探偵なので特別扱いされた描写を重ねられると違和感が生じるのはやむを得ないことだ。鮎川賞選考委員も、この点は気になったのではないか。
とはいえ、二階堂蘭子がメタ的にも実績を積んだ今読めば、違和感はそれほどない。
意味不明な行動
本事件の犯人は、千々に乱れた心境を吐露した手紙を蘭子に残す。問題にしたいのはその取扱いである。
蘭子は、私が読み終わった後で、この手紙に火を点けた。擦ったマッチを近づけると、手紙は角の方から簡単に燃え上がった。
蘭子は、いつまでもいつまでも、唇を噛みしめながら、灰皿の上で燃えていく手紙の様子を見つめていた。
なんで燃やすの?
犯人の手紙は、千々に乱れた自らの心境を蘭子個人に赤裸々に吐露した、生々しくも胸に響くものである。この犯人と蘭子の関係性や因縁は、蘭子が蘭子であるからこそ生じている。犯人の動機をここで言うつもりはないですが、仮に、仮にですよ、犯人が邪知暴虐そのものだったとしても、燃やすのは明らかに違うんじゃないか。手紙を燃やして彼女は前に進むというのだろうか。極めて親しい親戚が一家全体で巻き込まれている、蘭子にとっても他人事ではないはずの事件なのに。それとも、雅宮家なんかどうでもよかったんですかね彼女にとっては。お前の母親不在時に、わざわざ家までやって来て飯を作ってくれた親戚のおばさんは、雅宮絃子なんだぞ。その事件の犯人でこれか。
……それとも、二階堂蘭子は、親戚の事なんかどうでも良いのだろうか。雅宮家は母親筋の親戚である。ということは、義母の事もどうでも良いのだろうか。義父の事は? 義兄の事は?
私は二階堂蘭子を非難したいわけではない。明らかにおかしい行動を当然のような顔をして、いやそれどころか厳粛な表情で遂行する彼女のことを、隠れた性格破綻者ではないかと疑っているだけだ。ホームズの例を引くまでもなく、名探偵にはそのような側面を持つ人物が多い。だから、このような「疑い」は、サーガに謳われる名探偵としての彼女の魅力を増しこそすれ、減らしはしないのである。
黎人
刑事、蘭子に加えて事件関係者ともよく会話し、捜査に関与しようとしている。ワトソン役としては積極性があって良いと思います。ただし蘭子を探偵として信奉している気配は既に強い。外れる推理を披露して蘭子等に否定されるのを繰り返すのも、私は彼がわざと間違えることで、蘭子を立ているのではと疑っている。なぜなら、これほどの蘭子シンパであれば、自分を含めた蘭子以外の人物が謎を解くのを嫌がるはずであるからだ。本当に自分が真相を看破できたと思ったならば、蘭子に気付かせるためにサポートに回る可能性が高い。少なくとも、事件を解明できたと関係者の前で得々と推理を披露したりはしないだろう。ただし、『吸血の家』で黎人が披露する推理は、あからさまに外れだとわかるものではなく、蘭子による、外れだという指摘それ自体が読み応えのあるものになっている。作者はこの点で手を抜くことはしていない。
クライマックスでは実質的に荒事を担当しており、フィジカル面では割と心強い(蘭子は悲鳴を上げているだけ)。
ということで、結構活躍しているな、という印象である。下線部の迷解釈については、いったんそうと仮定して他の作品も読んでいきたいと思います。
二階堂陵介、鏡子
本書では登場しない。前者はお仕事、後者は洋行中である。実の息子と義理の娘が親しい親戚の家での殺人事件の現場にいるというのに、完全に放置している。情愛のある親子関係ならば通常はあり得ないが、恐らく「蘭子が名探偵として既に実績を得ており、黎人はすっかりその助手である」事実を信頼してのことだろうと推定しておきます。
親しい親戚に対するスタンスが見えないのは上述の通り。
両親については、もう一つ気になることがあるが、こちらは真相に触れないと書けないので、今回は省きます。
中村警部
彼をはじめ警察が特段の無能とは感じなかった。邸内で二回目の殺人(第三の殺人)を許したのは失点だし、終盤の荒事も止められはしただろう。しかし、ではどうやったら防げたのか具体的に考えると、なかなか難しい。そして、中村警部が真面目な正義感で、おまけに誠実な人物なのも確かなところである。これはこれで良い人物造形だと思います。
ただ、24年前の事件を蘭子たちに話すのを当初嫌がっていた理由が、私にはよくわからない。捜査情報を素人のガキに話せるか、というわけではない。恐ろしい未解決事件だから嫌だった、ということのようだが、それを今更、日常的に事件情報をやり取りしている蘭子と黎人相手に言うのか。実際の理由は他に何かあるのではないか。
村上刑事
雅宮三姉妹はいずれ劣らぬ美女揃いという設定である。この三姉妹に最もポワンとしてしまうのが村上刑事である。絃子との初対面では、なんて美しい人なんだと呟いてしまうし、三姉妹の亡き母に話が及んだら、三姉妹と比べてどうだったかなどと訊いてしまう。お前は一体何をしに来たんだ。
とはいえ、仕事自体は、中村警部同様、誠実にこなそうとしている。後半では功労者とも言える活躍を見せてくれる。蘭子や黎人が彼に一定の信頼を寄せているように見えるのも、むべなるかなだ。
貝山店主(船長)、玉絵、朱鷺沢教授、三峰助教授
《紫煙》の店長、その娘で店員、《推理小説研究会》の顧問、その助手である。《紫煙》で登場して以降は出て来ないので、この話では名前を覚えておく必要はないが、他の話で出て来るかもしれないので、記載しておきます。
総評等
新本格の一翼を担う作家、いやもっと言えば、一時代を画したムーブメントの一翼を担う作家のデビュー作に相応しい、完成度の高い逸品だと思う。もちろん若干の小説上の欠点と呼べそうなものはあるが、本格ミステリとしての完成度は高い。トリックも鮮烈、キャラクターも相応に印象的だ。
二階堂蘭子が最初から名探偵として下にも置かぬ扱いを受けているのは、違和感を覚えられても仕方がない弱点である。それ以外の点では、広くオススメできる名作だ。第一の殺人が一番鮮烈とはいえ、第二第三の殺人も水準以上の良いトリックなのもポイントと言えよう。
カンタベリー物語 賄い方の話/チョーサー
賄い方の話の序
一行は、カンタベリー街道のブレーの森のすぐ近く、ボブ・アップ・アンド・タウン(カンタベリーの北2マイルのハーブルタウンのこと、と注釈されているがGoogle Mapを見てもよくわからない)と呼ばれる村に着いた。もはやカンタベリーは目と鼻の先であり、城門や大聖堂の塔が見えていてもおかしくない。
宿の主人は、皆さんどうしたっていうんです!と冗談を飛ばす。恐らく、巡礼団の皆が疲れているのを見て取ったのだろう。彼は、馬の上で船を漕いでいた料理人を起こし、朝だというのに*1何を寝ているのか、夜は蚤にたかられて眠れていなかったのか、一晩中酒でも飲んでいたのかと詰問する。
料理人の顔は青ざめていた。彼は、よくわからないおもっ苦しい感じがすると答える。その様子を二日酔いと見て取った賄い方は、口が臭い、腐った息、この野豚と罵る。料理人は膨れっ面になったが言い返せず、頭を振る。その拍子に彼は落馬し、助け起こされるまでそこに横たわってしまう。巡礼団は大騒ぎになるが、料理人の二日酔いは良くならない。
宿の主人は、酒に呑まれているから料理人は無知蒙昧な話をするだろうなと愚痴り、彼のことは放っておこうと言う。*2そして、賄い方に話をするように促す。と同時に、上司である料理人にあんなことを言っては賄い方自身の立場が悪くなるだろう、店の勘定も細かくチェックされるぜと注意する。
賄い方は、そんなことにはなりたくないし、そもそも料理人を怒らせたくない、自分は冗談のつもりで言ったと弁解する。ただ、面白いところを見せてやろうと、ワインの入ったひょうたんを取り出して料理人に差し出す。そうすると、料理人は、差し出されたワインをぐびぐびと飲んで、上機嫌になり、賄い方に礼を言った。
宿の主人は、酒は愛と調和のためになる、必携の品だなと大笑いする。そして、賄い方に話を促し、賄い方は応諾する。
賄い方の話
古の時代、まだ下界にいたフィーバス*3は、世界で最も血気盛んな若い騎士で、最も優れた射手だった。大蛇パイソンを射殺すなど、数々の偉業を成し遂げた。彼は歌も上手く、美しく、気高く、名誉を重んじる一つも欠点のない騎士道の華であった。
フィーバスは一羽の真っ白なカラスを飼っていた。そのカラスは人語を解せた。
さてフィーバスには愛する妻がいた。ただフィーバスは非常に嫉妬深く、騙されるのを嫌ったため、妻を監視していた。賄い方はこれには否定的である。
さてフィーバスは、妻のためにと様々なことをしたが、妻が鳥籠から逃げたいと思うようになるのも当然であった。そして妻はこっそり情夫を作り、カラスの見ている前で淫らなことをしてしまう。カラスはこれを見て楽しみ、浮かれているところをフィーバスに見咎められた。カラスは彼の妻が無名の男、価値のない男と寝床でつるんでいるのを見たとご機嫌に語る。淫らな行為も具体的に喋ってるなこれ。
それを聞くや、フィーバスは妻を弓矢で射殺した。そして楽器も弓矢も壊して、カラスを難詰する。
「さそりの舌をもつ裏切り者よ」と彼は言いました。「お前はわたしを破滅させた」
フィーバスは、怒りのために早まったことをした、証拠もないのに早まって殺してはならない、などと嘆き悲しんだ後、カラスの偽りの話に仕返しをしてやると言って、白い羽を毟り取って彼を黒くし、歌も言葉も奪い、それが子孫にも続くように呪ったうえで、外へ投げ捨てた。このようなわけで、カラスは全て黒いのである。
賄い方は、口は災いの元で、言われた方は言った方を恨みに思うという趣旨のことを述べ、教訓とするように促す。
この事態の主な責任はフィーバスにより、次点で彼の妻だが、それを認めずフィーバスはカラスを責める。この八つ当たりの心理の動きは納得できるものであり、この話の教訓は現代でも生きているように思われる。また賄い方は、折に触れてキリスト教的な視点からの教訓をよく語る。書物は我が事でないので、と謙遜をよく入れるのも特徴だ。でもなかなか教養があると思います。
次回について
ということで、『カンタベリー物語』完走まで残り1話まで詰めたわけですが、その残り1話が最大最強の難物です。めちゃくちゃ長い宗教的説法で、物語要素がゼロなんだよなあ。ぶっちゃけ興味ないっす。ブログの記事を書けるかどうか心許ない。更新するにしても、だいぶ時間を空けないと無理だ。
カンタベリー物語 錬金術師の徒弟の話/チョーサー
出ました、中世ならではの職業の人が!
錬金術師の徒弟の話の序
聖セシリアの話が終わったとき、前夜の宿から5マイルも行かないうちに、ブーフトン・アンダー・ブレー*1で、一人の男が一団に追いついてくる。乗っていた馬をよほど急かしたのか、馬は汗びっしょり、口から泡も吹いている。チョーサーは最初、男の職業がよくわからなかったが、外套が頭巾に縫い付けられているのを見て悟る。とはいえ、この段階ではまだ記載されない。タイトルでバレバレではありますが。で、「外套が頭巾と繋がっている」のは、錬金術師がよくやっていた格好なのでしょうか?
彼は、宿から巡礼団を追って来たという。彼の師匠が話好きで、その師匠が一団に合流させてほしいということであった。
宿の主人は、師匠という人は面白い話を知っているのかと問う。弟子の男は、師匠は色々知っていると請け合う。宿の主人は、師匠の職業を尋ねる。すると弟子の男は、金銀を作るのが仕事だ(大意)と言う。宿の主人は、それにしては衣服が粗末だなと言う。徒弟の男は結構感情的になり始める。
だって師匠は金輪際成功することはないんですからね!
かくして徒弟はぶっちゃけ始める。師匠は賢過ぎる、過ぎたるは及ばざるがごとしで、それは師匠の明らかな欠点だ。町の郊外、隅っこ、袋小路などにこっそり隠れ住んでいる。自分の顔色が良くないのは、火を吹く仕事をずっとしているのに一向に成功しないからである。あちこちからゴールドを借りて、10ポンドからせめて1ポンド増やそうと信じ込ませる*2。一度として成功したことはなく、自分たちはそのうち貧乏になるだろう。
ここまで語り終えたところで、彼の師匠が追い付き、自分の話がされているのをすっかり聞いてしまい怒り出す。チョーサーがそれを見ての感想がこれ。
この師匠はいつも人の言葉に疑いをもっていましたものですから。それというのも、カトーが言っていますように、脛に傷をもつ人は、なんでも自分のことを話されているんだ、と考えるものですからね。確かに。
チョーサーが錬金術師に良い印象を持っていないのは明らかである。これは非常に興味深い。現代人の我々であれば、錬金術が無為な行為と知っているし、錬金術師を完全に疑ってかかるわけだが、錬金術など核融合でもしない限り不可能、中世では20000%無理であることを知らない同時代人がどうだったか私はこれまで一次資料に当たったことはなかった。『カンタベリー物語』はその貴重な一次資料の一つである。同時代でも錬金術師はうさん臭く思われていたのですね。住んでる場所も日陰者系だし。これは「錬金術師の徒弟の話」本体でも色濃く表れます。
錬金術師は、徒弟にもうこれ以上話すなと言うが、宿の主人は徒弟を焚きつけて、徒弟もやけっぱちになったのか話を止めようとしない。どうにもならないと悟った錬金術師は逃げ去る。
徒弟はもはややけくそである。師匠はいなくなった、悪魔が打ち殺してしまうがいいとまで言って、自分が知っていることをばらすと宣言する。
錬金術師の徒弟の話
第一部
徒弟は師匠と7年暮らしていた。だが知識は教えてもらえず、財産は失われるばかり。生きている間に返済できそうもない借金まである。自分を良い見せしめにしてくれと彼は言う。別に彼のみならず、この道では誰もがこうなっている、実際に自分以外にも同じような境遇の人間ばかりだと嘆く。
徒弟は錬金術の補助としてやったこと、見たことをかなり詳細に語るが、体系立てて教えてもらっていないという自分の主張通り、雑然としていてよくわからない。そしてぶっちゃける。
夜昼本に向かって座し、この秘密の、馬鹿げた学問を勉強したって、すべては無駄なんです。いやあ、それどころじゃないんです。(中略)とうてい無駄だから。彼が本の勉強をしていようとしていまいと、実際のところは、まったく同じだっていうことがわかるでしょう。(以下)金銀に変えることにかけては、結局おんなじだという結論になるでしょうから。つまりは、無知な人も学のある人もどちらも失敗するということです。
当事者にしてこの認識! そして彼は、それでもなお賢者の石が現れる希望を抱いてしまうと言う。賢者の石を永久に探し、つまりは永久に無為な行為を続けてしまう。
そして実験が失敗すると――ときに爆発すら起きてしまう――徒弟間で、あいつが悪いこいつが悪いの口論になる。それを師匠が止め、またやり直しになるのだ。だが金銀は一向に作れない。最も賢く見える者が、最も愚か。金のように輝いているものが全部金とは限らない。美しいリンゴが全て良いリンゴだとは限らない。
しこうして第二部これに続く
徒弟は、悪い伴僧の物語を始める。ただし本格的に始める前に、他の伴僧に詫びを入れる。全ての教団には誰か悪党がいるものであって、その一人の悪党のために教団全体を貶めるつもりはないと断る。まあ巡礼団には宗教関係者が結構含まれるから、こうも断るか。
さてロンドンに一人の僧がいた(この僧は善良である)。いんちき伴僧はこの僧に声をかけて、1マルクを借りる。そして3日目に返済する。伴僧はこの僧に感謝するふりをして、自分の仕事場に連れて行く。そして、水銀を銀に変えるという。だがそれはいんちきだった。銀のヤスリ屑を予め炭に仕込んでおき、燃やすと陽気に銀が残るという算段である。伴僧は銅でもトリックを仕掛けて、銀に変えたように見せかける。しかも作業を全て自分でやるのではなく、火を吹くなど一見メインに思える作業は僧に任せている。僧はすっかり騙されてしまった。そして伴僧から、この処方箋を高値(40ポンド)で売りつけられるのであった。
徒弟はこのような詐欺を警告し、錬金術に触れることを警告する。過去の偉人で錬金術に成功した者も、それを書物に書かなかった。なぜなら神が望まなかったからである。
どのようにして人がこの石にたどり着くかを、哲学者たちが明かすのを天の神様がお望みにならない以上、わたしは最善の忠告として、これはもうそのままにしておきなさい、と言います。(中略)神様の御意志と反対のことを何でもやろうとして、神様を敵とする人は、決して栄えることはありますまい。
総評等
錬金術師が14世紀にどう見られていたのかの貴重な一次資料である。ただの詐欺師と思われていたようだ。理性的な判断だと思う。詐欺に引っ掛かるところがまた人間らしいし、手口が詳しく書かれているのもまた興味深い。当時からこういうトリックがあるのはよく疑われていたのだろう。やっぱり14世紀人だって理性的なわけですよ。そりゃそうだよな、同じ人間だものね。また、徒弟の語り口が鼻息荒いのが面白い。ヤケクソ感、もうどうにでもなれ感が強く、読んでいて楽しいです。
ということで、読者としては錬金術を嘲笑しておけば良い。だが現代人として忘れてはならないのは、錬金術が千年以上にわたって蓄えたゴミのような知識の山にわずかに含まれた、宝の知識を萌芽として、科学が芽生えたということである。頭が良いわけでも、人間としての階梯を登ったわけでもない我々が、単に現代に生きているというだけで貪る、安楽、安寧、安逸、利便のほとんど全ては、錬金術を母として生まれた。つまり我々は数十億人のオーダーで、錬金術の恩恵に預かっている。それをゆめ忘れてはならない。そしてそのことを、チョーサーは知らなかった。知ることができるはずもなかった。史実は面白いものである。
そして全体的トーンから、ニュートンどころかコペルニクスすら生まれていないこの時代、錬金術の最終目的である貴金属錬成は、神の秘蹟に踏み入ることと認識されていたことがひしひしと伝わって来る。だからそれは悪いこととされた。科学と倫理のせめぎ合いは、今でも社会における大きなテーマである。だが現代人は、チョーサーが言うところの「神様の御意志と反対のこと」をやり倒して、繁栄を手にした。かかるがゆえに、この物語は、作者チョーサーの思惑も予想も遥かに越えて、600年後の今でも大いに響く物語になっていると思う。チョーサーの立場は正しいのだろうか? 我々の立場は間違っているのだろうか?
カンタベリー物語 第二の尼僧の物語/チョーサー
序もマリアへの祈りも、どうやら韻文っぽい。
第二の尼僧の物語の序
安逸を悪徳として非難する。快楽の門番、その反対である勤勉(仕事)をもって対抗すべき、安逸は腐敗した無為、破滅の原因ととにかくボロクソ。ここでいう安逸はidlenessのようであり、日本語の「安逸」とは必ずしもマッチングしていないのかもしれない。
マリアへの祈り
尼僧は、処女セシリアの死を語るとして、マリアに祈る。また、自分(わたし)が書くものを読む読者に、自分が上手く書く努力をしないからと非難しないでくれと願い。……この「わたし」は第二の尼僧なのか、チョーサーなのか。前者ならメタレベルがぶれていることになる。
第二の尼僧の物語
かくして、クラシック音楽のファンなら名前を聴いたことがあるであろう聖チェチーリアの物語が始まる。
処女セシリアはローマ貴族の娘で、小さい頃から敬虔なキリスト教徒であった。彼女はヴァレリアンと結婚するが、純潔を保とうとする。初夜において、彼女は夫に、天使が自分を守っており、淫らな行為をされると相手を殺すが、清い愛で自分を導くなら天使はあなたをも愛すだろうと言う。ヴァレリアンは、天使を見せてくれと頼むと共に、セシリアが他の男を愛するなら殺すと返す。セシリアは洗礼を受けるなら天使を見せると言い、ウルバンに会いに行けという。
ヴァレリアンは言いつけ通り、隠れた生者の墓の中でウルバン教皇に会う*1。ウルバンが主イエス・キリストに祈り、セシリアとヴァレリウスのことを願うと、輝く白い衣服をまとった一人の老人が現れる。老人を見たヴァレリウスは倒れるが、老人は彼を起こし、神を信じるか問う。ヴァレリウスが信じると答えると、老人はかき消すように消えた。そしてウルバンはヴァレリウスを洗礼する。
ヴァレリウスの帰宅後、夫妻の前に天使が現れる。天使は薔薇と百合の二つの王冠を彼らにそれぞれ授け、何か望みはあるか訊く。ヴァレリアンは弟ティビュルスにもこの恩寵に預からせたいと願った。ティビュルスがやって来て、辺りに薔薇と百合の花の香りが満ちていることを不思議がる。ヴァレリアンは、ティビュルスが正しい信仰を持てば王冠も見えるようになるだろうと言い、偶像を捨てるように言う。ティビュルスは言われる通り偶像を斥けることを誓う。
ティビュルスはこれから自分はどうすればいいのか尋ね、ヴァレリアンにウルバンの所へ行けと言われる。ティビュルスは、ウルバンがお尋ね者になっていて、彼の仲間だと知られれば自分たちも焼き殺されるだろうと危惧する。セシリアは、人が生きるのがこの世だけならその心配もわかるが我々には天国があると諭す。ティビュルスはウルバンに会って洗礼を受け、毎日決まった時間に天使を見られるようになった。……色々な意味でキマってるな、と思うのは私が異教徒だからかしら。
さてイエスが彼らに様々な奇蹟を行った後、遂に殉教の時が来る。ローマの長官アルマキウスは彼らを捕えて、ジュピターへ生贄を捧げないなら斬首刑に処すことを決めた。だがマクシムスら協力者の助けも得て、セシリアたちは捕まった後も、死刑執行人を含む多くの人に布教し洗礼を施すことに余念がない。
さてヴァレリアンとティビュルスは生贄を捧げよと命じられるが拒否したため、首を落とされる。それを見ていたマクシムスは、彼らの魂が天使に伴われて天に昇っていくのを見たと言い出し、これまた多くの人を改宗したため、むち打ちされて殺された。
セシリアがこの死んだ三人の男を葬った後、遂にアルマキウスは彼女を捕える命令を役人たちに出す。ところが改修済の役人たちはこれに抵抗して泣いた。しょうがないのでアルマキウスは、捕えるのではなく連れて来るよう命令を変更。やって来たセシリアと論戦する。なおセシリアの態度は無礼で、アルマキウスは居丈高だ。どっちもどっちと思うのは私が異教徒だからか? 二人とも、相手の価値観を延々と否定するんですよね。セシリアはここに、自分の価値観を誇る要素も入る。議論は平行線を辿り、アルマキウスは生贄を捧げるか信仰を捨てるかすれば逃げられるぞと、最後の選択をセシリアに迫る。セシリアは断固拒否し、引き続きアルマキウスの権力権威を蔑む。
アルマキウスは、自分への侮辱は何でもないが、神々への侮辱は許せないとする。セシリアはこれを愚かだと言い、偶像を否定する。偶像否定論者が後に聖人として偶像化してるんですがそれはいいのか?
さてアルマキウスは怒り、セシリアを家に連れ戻して風呂釜の中で煮殺すよう命じる。だがどんなに火を焚いても、セシリアの身体は一向に熱くならない。ということで、アルマキウスは視覚を送り、セシリアの首を落とそうとする。だが彼女の首は三度突かれても落ちなかった。四度突くことを禁止する法があったため、刺客は引き上げる。
とはいえ致命傷ではあった。セシリアは三日間苦しんで死んだが、その間も信仰を説くことを止めなかった。彼女はウルバンに、自分が三日間の休息をもらうよう主に願ったのだと明かし、自分が死ぬ前に自分の信徒をウルバンに委ねんがためだったと言う。ウルバンは彼女を手厚く埋葬した。
セシリアの家は聖セシリア教会となり、今でもセシリアに貴い奉仕を行っている。
総評等
聖セシリアの伝承ほぼそのまま。これにあまりツッコミを入れるとキリスト教にツッコミを入れることに近付くのであまりやりたくないです。ただ、聖人が偶像を否定するのを見ると、毎回微妙な気分になるんですよね。
セシリアの毅然とした姿勢は印象的です。でも夫と結婚しても処女を通すのはどうなんだろうと思わないでもない。聖人だから良いという理論なのだろうか。でも聖人指定は死後よね? はたまた、修道女制度がないからしょうがないという理論なのだろうか。
そして相変わらず、敬虔と設定されている宗教人の話はあまり面白くないな。小説として登場人物が生きていないのである。ミステリで敢えて似た読み口な作家を挙げると、天城一かなあ。そしてあっちは、私がミステリに関心があるため、人物が活きていなくても興味深く読める。こっちには関心がないので、つまらないなあという思いから逃れることはできません。
カンタベリー物語 尼僧付の僧の物語/チョーサー
尼僧付の僧の物語の序
おやめなさい! あなたのお話はもうよろしい!
騎士がこう言って(割と直球)、修道僧の話を止める。理由として、没落を聞くのは非常に痛々しいことを挙げている。逆に貧しい境遇の人が昇りつめて繁栄する話は楽しいので、そっちが良いと言う。宿の主人も同調して、済んだことを嘆いても仕方がない(大意)と言う。悲しいことを聞くのは苦痛だと言う。だったら尼僧院長の話も止めろよと思うが、中世人の感覚はこういう細かい部分がよくわからない。
宿の主人は更に言い募る。聞くのが苦痛だし退屈、手綱の鈴を鳴っていなかったら寝て落馬していたところだとまで言う。知らなかったはずの修道僧の名前(ピエルス殿)で呼び掛けさえする。そして、何か狩猟の話でもしてくれと言う(たぶん修道僧に)。そして恐らく修道僧は、断って、ふざけるような気分ではないから、他の人に話をさせれば良いと返事をする。ぶんむくれだ。
宿の主人は、それならばと、尼僧付の僧ジョンにこちらに来てと呼び掛けて、楽しい話を所望する。尼僧付の僧は応じて、話を始める。チョーサーは彼のことを「愛する僧、善良なる人ジョン」と書いている。好意は明らかだ。
なおこのパートで、宿の主人は「聖ポールの鐘にかけて」と喋る場面がある。聖ポール聖堂は当時からあったわけだ。もちろん今の建物になる前のものだろうが、まあやっぱり歴史がとてもあるということなのだろう。
尼僧付の僧の物語
彼が語るのは、雄鶏と雌鶏である、チャンテクレールとペルテローテの物語である。
田舎に住む少々年老いたその寡婦は、夫の死後、娘二人と一緒に貧しくも質素に暮らしていた。彼女はチャンテクレールという雄鶏を飼っていた。時を告げる鳴き声は正確そのもの、外見も良く、七羽の雌鶏を従えていた。その雌鶏の中でも最も美しいのがペルテローテであった。二羽は相思相愛であった。
ある明け方、チャンテクレールが酷く悩んでいるように唸ったのでペルテローテは驚く。チャンテクレールは、獣に襲われ殺される悪夢を見ていた。それを聞いたペルテローテは、夢を恐れるなど臆病過ぎるとドン引きする。そして、胆汁がたまり過ぎたのだろうから、上からも下からも下す薬を飲むべきだと助言する。
雄鶏はこの助言に一応感謝するが、友人が殺害される夢や、友が難波する夢、自分が殺される夢などなど、悪い夢が正夢になったという、本で読んだエピソードを紹介し、引き続き夢に怯える。さらに、下剤なんかくそくらえです(ママ)という。しかし彼は、止まり木でペルテローテと密着しているため機嫌がよくなってきて、夢だってくそくらえという気持ちです(ママ)と言って地面へ飛び降り、餌をついばみ始めた。
やがてこのチャンテクレールは、ペルテローテの庭で歩こうという提案に従い。雌鶏たちと共に庭に出た。そこには運悪く、狡猾な黒狐ラッセル卿が潜んでいた。尼僧付の僧はここで、女性の助言はしばしば致命的だと唐突に言い始めるが、これは鶏の話であって女性の忠告を非難するのは雄鶏だ、自分の言葉ではないとよくわからない言い訳を始める。
黒狐に気付いたチャンテクレールは逃げ出そうとするが、黒狐はすかさず遜った態度を取り、チャンテクレールの歌声を絶賛し始める。チャンテクレールは歌を披露腺と首を伸ばしつま先で高く立ち、目を閉じた。やにわにラッセル卿は彼の首に食いつき、森の中へ引きずり込もうとする。
雌鶏たちの騒ぎに気付いた飼い主の寡婦と娘二人は、狐を目撃して、後を追う。近所の人々も加勢する。
その様子を見ていたチャンテクレールは、狐に対して、自分だったらあいつらを言葉で追い払うし、雄鶏をすぐに食うと言う。狐は「本当に、そうしてやろう」と発話してしまい、咥えていたチャンテクレールの首を話してしまう。チャンテクレールはすかさず逃げ出し、樹上に飛び上がる。すると狐はまた阿った態度に出るが、雄鶏はさすがにもう騙されない。
「目をあけて見なければならん時に、すすんで目を閉じるものなんぞには、神様、どうか不幸をお与えください」
「いやそうじゃない」狐は言いました。「沈黙しなりゃならない時におしゃべりをするような。自制力に欠けている奴こそ、神様、不幸をお与え下さい、だ」
かくして勝負(?)は痛み分けに終わる。いや逃げられたから狐の負けか? 尼僧付の僧はここで、狐・鶏の話だと思っている人も教訓を取るよう頼む。
尼僧付の僧の物語への跋
宿の主人は、(なぜか)尼僧付の僧のズボンに祝福あれと言い、楽しかったと褒める。彼の筋肉も褒める。僧が俗人だったら種鶏になったろうにと残念そうである。そして、次の語り手に尼僧を指名する。
総評等
女性云々はほぼ関係がない話である。散歩しようと提案してその途中に敵に襲われた場合、散歩を提案した者が悪いとなるのはよく理解できない。それ以外はなかなか面白い御伽噺であった。
カンタベリー物語 修道僧の物語/チョーサー
ここから岩波文庫版は下巻です。
修道僧の物語の序
宿の主人が修道僧とかわした愉快な言葉
メリベウスの物語を聞き終えた宿の主人は、自分の妻ゴッドリーフ*1のことを思い出して興奮している。宿の主人は妻の暴力的な様子に不満たらたらである。が召使の男の子を殴ると(中世サービス業の闇!)ゴッドリーフは棍棒を持ち出して来て「犬どもを皆やっつけろ。背中も骨もみな打ち砕け!」と叫ぶらしい。……私には読解力がないので、妻が夫に加勢しているのか止めているのかわかりません。また、他人が彼女の意に染まないことをすると、帰宅後に、夫に妻の仇を討てと喚き散らすらしい。大変ですな。
やがて宿の主人は、妻の話はこれくらいにして、と言って、修道僧に話を振る。ところがこれが、皮肉や当てこすりに塗れている。名前は知らない、どこの教団か知らない、お肌つやつや、さぞや立派なお立場だろう、体格も立派、もし僧院に放り込まれなければ何人も子供を作られただろう、自分が教皇なら元気のいい男には皆細君を持たせてやるんだが、自分たちの細君は僧侶とよく寝てる、あ、全部冗談ですよ。……修道僧に妻や恋人を寝取られた経験でもあるのかな?
修道僧は宿の主人のコメントを辛抱強く聞いてから、悲劇――高い地位にいた人が悲惨な境遇に落ちて惨めな末路を迎える話、と修道僧は定義する――を話すと言う。思い出すままに喋るので、順不同になるだろうとの断りも入れる。
なお、ここでローチェスターがもうすぐだという台詞がある。まだ往路のはずなので、ちょうど半分ぐらいまで来たことになるのかな。
修道僧の物語
ここに修道僧の物語、名士列伝始まる。
高い地位の人の転落を悲劇の体にならって嘆くとしましょう、運命の女神を遮ることなどできはしない、なんぴとも当てにならない繁栄を信じるな、昔からある事例を心に留められよ。まあ単なる前口上だが、それはもうやったよなという気はします。以下、触れれた人間を紹介するが、「簡単な紹介」とあるのは、転落を数行程度で簡単に紹介されただけと思召せ。
ルシファー
簡単な紹介。
アダム
簡単な紹介。
サムソン
没落前のエピソードも含めて、結構詳しく話す。
ヘラクレス
没落前のエピソードも含めて、少し詳しく話す。なおネッススは「人」とされ、焼身自殺については、毒で死ぬことを潔しとしなかったとされている。
ネブカトネザール
没落前後のエピソードも含めて、少し詳しく話す。なお当然のことながら旧約聖書準拠であり、数年発狂した後、王に復帰する。いや復権しとるがな。
バルサザール
没落前のエピソードも含めて結構詳しくやる。なお旧約聖書準拠ゆえ、彼はネブカトネザールの息子とされるが、実在性には疑問符が付く人物である。
ゼノビア
没落前のエピソードも含めて結構詳しくやる。ローマの凱旋式で見世物になったことは紹介されるが、最期については触れられていない。
イスパニアの王ペトロのこと
簡単な紹介。
キプロスのペトロのこと
簡単な紹介。アレクサンドリアを手中にしたのに、朝、寝床で殺された。
ロンバルディアのベルナボ
簡単な紹介。
ピサのユゴリーノ伯のこと
没落後の獄中での幼い息子とのやり取りが詳しく紹介される。人肉食をしたとは記載されておらず、悲しみのために息子の両腕を噛んだこと、息子がそれを受けて死んだら自分を食べてくれと言い残して死んだことが記載されている。悲惨。
ネロ
没落前のエピソードから結構詳しくやる。もちろん暴君として描かれており、近親相姦、セネカ殺害が紹介され、ローマ大火も彼による付け火とされる。最期は民衆の放棄から逃げて、庭にいた農夫二人に自分を殺してくれと頼んだことにされている。
ホロフェルネスのこと
簡単な紹介。
著名なるアンティオクス王のこと
割と詳しくやる。当然のことながらマカベア書(聖書外典。当時はどういう扱いだったのだろうか?)準拠。
アレクサンダーのこと
エピソード紹介というよりも、人となりに少し触れて、彼を賞賛するひとくさりをやる。なお暗殺説(毒殺説)に立っている。
ジュリアス・シーザーのこと
アレクサンダーの際と同様、彼を賞賛した上で、暗殺時の経緯を少し詳しくやる。
クレーソス
没落後のエピソードを少し詳しくやる。絞首刑に処されたとの前提で書かれているが、何に準拠しているのだろうか?
総評等
というわけで、まあただたひすら列挙していくだけです。物語を聞く楽しみはここにはあまりない。運命の女神がコントロールしているから仕方ない、でも悲しいことよ、と、上から目線で投げやり気味でやや皮肉な(?)物言いが付いて回るので、読後感もあまりよろしくない。
そしてこの修道僧の物語には、最後の一行で、巡礼団から矢が飛んでくるのだ。
ここで騎士、修道僧を止めてその話を終らす。
*1:宿の主人の奥さんの名前が出たのはこれが初めてでは?
カンタベリー物語 メリベウスの物語/チョーサー
チョーサーの二つ目の話「メリベウスの物語」は、長い。とても長い。しかも寛容についての物語であって宗教色が非常に強く、説法を受けている感が強くする。読むには相応の覚悟が必要だ。
チョーサーのメリベウスの物語始まる。
有力で裕福な君、若いメリベウスには、プルーデンスという妻と、ソフィエという娘がいた。メリベリウスの外出中、彼の敵が三人メリベリウスの家にやって来て、プルーデンスを傷付け、ソフィエの足・手・耳・鼻・口に致命的な傷*1を与えて逃げ去った。このメリベリウスの物語は、ざっくり言うと、この事件に激烈に反応するメリベリウスを、プルーデンスが、大量の故事や伝説を引きながら宥めてより穏便な方向に持って行くというものである。以下の粗筋紹介からは、引かれた故事の内容をあらかた省きます。気になる方は現物を読んでくださいませ。
- 帰宅したメベリウスは事件を知り、服を裂きながら泣き叫ぶ。プルーデンスは、夫が思う存分泣いてしまうまで見守り、頃合いを見て「嘆くのは賢人に相応しくない、たとえ子が死んでも」と諫める。メベリウスは抵抗するが、プルーデンスは、ほどほどにした方が良いと説き、メベウスもこれを正しいと認める。
- メリベウスがどうすればいいかわからないと言うので、プルーデンスは真実の友を全てと、一族の者で賢い人を呼び相談すべきと説く。プルーデンスはこの忠告に基づき、外科医、内科医、老人、若者、元敵で今は表面上和解した者、隣人、おべっか使い、弁護人などを呼んだ。彼らの多くは、愛情ではなく恐れからメリベウスに従っている者である。プルーデンスの忠告内容とは顔ぶれが違う点に留意してほしい。
- 怒りがダダ洩れの状態で、メリベウスは助言者たちを一堂に会して相談する。彼らの意見は以下。
- 外科医:医療が仕事で戦いの相談には不適任、自分たちは娘さんを治療する。
- 内科医:外科医の意見+「疾病が対症療法で癒される*2ように、人は復讐によって争いを癒すべき」
- 隣人・元敵・おべっか使い:復讐戦をすべき。
- 弁護人+賢明な人たち:拙速はNG、熟慮すべし。ただし守りは固めるべし。
- 若者たち:戦いだ! 戦いだ!
- 老賢者:戦いは始めやすいが結果がどうなるか知るのは難しい。熟慮すべき。なおこの老賢者は野次られた模様。
- メリベウスは忠告の多数派に同意し、復讐戦を決意する。プルーデンスは頃合いを見計らい、あまり急がず、時間をかけて熟慮すべきと説く。
- メリベウスは忠告を以下のように撥ねつけるが、プルーデンスはそれぞれ以下のように宥め、自分を信頼してくれるなら娘を元通りの健全な体にしてみせましょうと言う。……娘の疵は致命的だったのでは?
- 決めたことを今更変えられない:正当な理由があるなら変更か決して愚かではない。またしばしば少数派が賢く多数派は尊敬に値しない。
- 女はすべて邪:すべてを軽蔑する人は気に入るものがない。また人間は全て女から生まれる。ソロモンの発言は、女が最高の善ではないという趣旨である*3。
- 主導権を他人に渡すのは愚か:忠告を受け容れるかどうか決めるのは結局自分なのだから、主導権を他人に渡すことにはならない。
- 女はおしゃべりで秘密が維持できない:貴方も試したように、自分はおしゃべりな女ではなく、隠し事はできる。試したのかよ……(学僧の話を思い返しながら)。
- 女の忠告は邪だ:そういう女も中にはいたろうが、同じように多くの女が善なる忠告をしている(4つほど例を挙げる)。女がそんなにダメなら造物主も男の伴侶として女を作らなかったはず。
ここに至りメリベウスも納得する。ソロモン王の、女性に関してではないが思慮があり秩序立った言葉を賞賛する言葉を引用して納得し(『カンタベリー物語』におけるソロモンの名誉回復だ!)、なおかつ、プルーデンスの知恵を実際に試してよく知っている(試したのか……)からと、妻の忠告に従って自分を律すると言う。プルーデンスは更に以下のとおり忠告する。
- 謙虚になるべき。
- 憤怒はダメ。できないことをできると考えてしまうし、良い判断ができないし、非難がメインになってしまう。
- 貪欲もダメ。諸悪の根源であり、判断することも考えることもできなくなるし、際限もない。
- 性急もダメ。最善の判断にならない。
- 熟考した結果の判断は秘密にすべき。明かした方が利益になる場合は明かしても良いが、素振りで示してはならない。おべっかを使う者が忖度し迎合してくるばかりで、良い忠告が集まらないからだ。
- 忠実・賢明・経験の多い者に相談すべき。ケースバイケースで人を変える必要もある。最初は少人数に相談し、相談する相手が多い方が良い問題はその後で多数に相談するのが良い。実質的には、メリベウスが既に実行した相談会へのダメ出しである。
- 愚か者、追従者、和解した敵、自分を尊敬し過ぎている人、酔いどれ、公の場とは反対のことをこっそり忠告してくる者、邪悪な者(悪漢?)の忠告は避けるか疑うべき。これも実質的にはダメ出しである。
- 助言を受けるに当たっては真実を忠実に話す必要があるし、その助言の結果何が生じるか、様々な助言のどれがより良いかを考えねばならない。理性に敵うかどうかが重要。なお成し遂げるのが疑わしい場合は、何もせず我慢すすべきである。一方、成し遂げられることは最後までやり遂げねばならない。
- 事態が変化した場合や、計画自体が不誠実だった場合は、計画変更は何ら恥じることはない。不可能な事項についても同様である。
さてお気付きだろうが、ここまでの忠告は一般論に過ぎない。メリベウスは、今回のケースだとどうなるの?(大意)と妻に訊く。プルーデンスは、気に染まないことを言っても心を乱さないよう予防線を張った上で、あなたはミスを犯したと明言し、以下のようにガン詰めする。
- 助言者は最初は二、三人に絞るべきだったが、いきなり大人数を呼び寄せた。
- 見知らぬ者、過去の敵、若い人、偽りの追従者、愛もないのに尊敬を示している人も呼んで、憤怒・貪欲・短慮を呼び寄せてしまった。
- 見知らぬ者、過去の敵、若い人、偽りの追従者、愛もないのに尊敬を示している人も呼んで、憤怒・貪欲・短慮を呼び寄せてしまった。
- 開戦すべきとの自分の気持ちを隠さなかった。助言者はあなたの願望に沿うように忠告するようになった。
- 既に忠告に満足しているように見える。本当はもっと助言が必要だし熟慮もせねばならない。
- 忠告内容をしっかり吟味していない。
- 真実の友と見せかけの忠告者を区別していない。賢人より愚物の方が数が多いことは先刻ご承知でしょう?
メリベウスは過ちを認め、忠告者を変えようと言う。プルーデンスは、既に為された忠告の検討を始める。
- 外科医や医者の忠告は賢明であった。娘の治療において彼らは大いに報いられるべきであり、無報酬はダメ。
- 内科医の「正反対のものは他の正反対のもので癒される」という提案*4について、メリベウスは敵意には敵意で返すと解釈するが、プルーデンスはそれは自分の願望に沿った解釈だと煽り*5、復讐の制反対は復讐ではない、善/悪、平和/戦争、復讐/忍耐、不和/調和が正反対だとする。しれっと「忍耐」を混ぜ込んで来たのがミソかな。
- 法律家や賢い者の忠告の論点は以下;
- 「身を守れ」は、まずイエス・キリストに祈るべし*6、そして真実の友に守りを委ねるべし。偽りの友は遠ざけるべし。
- 「家を守れ」も、真の友や、自分を愛してくれる家来・隣人が最大の防御になると理解すべきだ。決して城砦・塔・武具・大砲等によるものではない。それらは費用も労力もかかり、高慢に結びつく*7。
- 「慎重にやれ急ぐな」は、賢い真実の意見である。何をするにも準備と配慮は重要。
- その他の助言者はそもそも人選ミスだが、敢えて彼らの意見「復讐せよ」を考察すると、メリベウスの敵は三グループいていずれも一族が多いが、メリベウス自身は係累が少ない。メリベウス自身は有力で裕福だが、死後に分け前が味方に分け与えられてしまえば、メリベウスの死後にその復讐のため立ち上がる人間など出て来ないだろう。……プルーデンスのこの忠告は、精神面ではなく戦術面に触れており、異色である。
- 復讐権は法にあるのだから裁判官に委ねるべき。またメリベウスは権威ある者なのだから、法を無視はできない。この話の流れで、法治主義の概念が出て来るのには驚きました。
- 復讐は更なる争いを産む、損害も広がる。
- そもそもこの襲撃は敵の憎悪から生じたのだから、復讐すると憎悪や復讐がまた生まれる。
- 今回の事件の根本原因が何か、それについて敵と会話した場合に敵がどう反応するかはプルーデンスには判断ができない。
ここから、会話は忠告者や忠告の評価から離れて、話は復讐そのものの是非に及ぶ。忠告/助言の形式を採ってはいるが、夫の発言や質問も増量し、会話は徐々にディベートの様相を呈してくる。
- メリベウスとは「蜂蜜を飲む者」という意味であり、富・喜び・名誉という蜂蜜に酔い痴れたメリベウスが創造主イエス・キリストを忘れた結果、主がメリベウスから顔を背けて、今回の事件が起きたのではないか。……出たよカルトの考え方。
- メリベウスの「復讐には抑止力がある」という主張に対し、復讐する権利は裁判官にのみあると、法治主義が重ねて主張される。
- メリベウスは不服で、「自分は運命の女神に育てられてきたのだから、今回も運命の女神が助けてくれるだろう」と主張。プルーデンスは、運命の女神は移ろいやすく信用できないとする。つまり運は不確かなので当てにするなと言っている。加えて「復讐はわたしのすることである」との神の言葉を引く。
- メリベウスは「非道に黙っているのは更なる非道を勧めるようなものだ、忍耐してばかりだと人からも甘く見られる」と主張する。プルーデンスは、過剰な忍耐は良くないと認めるが、法治主義を重ねて主張する。また仮に復讐権をメリベウスが持っていたとしても、先述の戦術面の不利があると指摘する。
- そもそも争いは避けるべきである。
- 艱難は先述の通り思し召しなのだから、忍耐すべきだ。……カルトの考え方だが、お布施しろと言われないだけマシなのだろうか?
- メリベウスは「言っていることは正論だがそんなの無理、自分は復讐しないと気が済まない、相手がやったことを自分がやってどこか悪いのか(大意)」と反発する。気持ちは痛いほどわかる。ここまでずっと、プルーデンスは正論棒で夫を殴り続けているんですよね。これに対しても、プルーデンスは、メリベウスの言葉は心の向くままの発言でしかなく、乱暴な行為は悪であり、今のメリベウスの防御は身を守るためではなく復讐のためであり非理性的だ、忍耐が善だと正論で返す。
- メリベウスは、「他人事の場合ならそれでもよいが、今回は自分の事だぞ(大意)」と反発し、自分は敵より富裕で力もあるので、復讐しても自分が危機に瀕するとは思えないと言う。プルーデンスは、「こいつ敵なめてんな(大意)」と見て取って、貧乏は災いをもたらすが富は確かに、立派な人が得る分には良いよねと事実上宥めてから、以下のように諭す。議論のあるところだとは思うが、今回の件には直接は関係なさそうな事項が多く、チョーサーがこのエピソードから汎用的な教訓を与えようとしているように思える。
- 富はじっくり獲得すべきだ。今回の件には関係なくない?
- 富は努力によって得るべき、他人を加害して得ることもNG。今回の件には関係なくない?
- 怠惰はダメ。
- 富を得た後はケチもNG、浪費もNG。ほどほどが一番。今回の件には関係なくない?
- 貪欲も避けるべき。富はあの世に持って行けない。今回の件には関係なくない?
- 富を用いるときは、神、良心、名声を意識すべき。今回の件には関係なくない?
- 自分の富を頼んで戦いを始めようとしているように見受けられるが、富んでいるなら他の手段も使えるはずで、にもかかわらず戦うのはよろしくない。
- 勝負の勝敗は神の御手にあるのだから、神の愛に相応しいか否か明らかでない以上、戦いを恐れるべきである。
- 偉人も戦いでは普通に殺され得るのだから、危ない。
メリベウスは、じゃあどないせえっちゅうの(大意)?と妻に訊く。プルーデンスは敵と和解せよと言うが、これにメリベウスは大反発。
今やわたしはお前がわたしの名誉や名声を愛していないということがよくわかった。(中略)わたしが身を低くして彼らに従い、お慈悲を乞うようにお前は望むのか。確かにそれはわたしへの名誉とはならないだろう。なぜなら「過度の親しみは軽蔑を生む」と人が言うように、あまりにも謙遜し身を低くすれば軽蔑を生むこともまた当然であるからだ。
ここに来てメリベウスも正論を繰り出したようだ。そしてプルーデンスは怒った様子でこう反論する。遂に論戦状態になりましたね。後述の通り、メリベウスはすぐへこたれるんですが。
- 自分はメリベウスの名誉と利益を愛している。あなたも他の人も、まさかそうじゃないと言わんだろうな?
- 「不和は他人から始まり、和は自分から始まる」「力の限り平和を求めろ」とは古から賢人が言っているじゃないか。
- メリベウスから詫びを入れろなんて話、誰もしてへんがな(大意)。
- あなたは私のためには何もしてくれへんよな(大意)。……プルーデンスさん、割とキレてますな。
今度はメリベウスが宥める側に回り、どうか何でも言ってくれ、お前の望む通りにすると言う。ソロモンの言葉まで引いて妻を賞賛する。つまりはタジタジである。プルーデンスは怒っているのではなく叱っているのだ*8と言って、以下のように助言を続ける。
- 敵と和解すべし(繰り返し)。
- 人目に付かない場所で、わたしが敵と話してみる。
- 敵はメリベウスの意思を今のところは知らない状態なので、ここでプルーデンスと敵との会見で敵の思惑がメリベウス側にわかれば、より一層適切な手を打てるようになるはず。
メリベウスは承諾し、プルーデンスは敵に使者を送って秘密裏に会見の場を持った。プルーデンスは敵に、平和の利益や戦争のリスクを説き、メリベウス・プルーデンス・娘に対する悪事についての後悔をどう示すべきかを丁寧に語った。以下、その後のやり取りの概要である。この後、敵側は納得して後日の会見のために帰る。
- 敵側の発言:親切にありがとう。こちらにはメリベウスの言葉や命令に従う用意がある。しかし、与えた損害の原状復帰は無理だし、メリベウスはこちらを深く恨んでいるはずだから、苦痛を与えようとして来るはずだ。相続権を破棄させられたり、破滅させられたりすることのないよう、プルーデンスに女性らしい忠告*9を頼むことはできるか?
- プルーデンスの応答:古来、自分のことを他人に委ねるなと言われているが、それでも夫に委ねることを忠告する。自分の夫は寛容だし(大意)、自分の助言なしには何もしないと思う(大意)。……自分の夫を傀儡だと言ってないかこれ?
- 敵はこのプルーデンスの応答に安心したのか、メリベウスと会って処分を受けると決めたと言う。
プルーデンスはメリベウスに敵の様子を伝える。メリベウスは、敵の態度は確かに立派で斜面に相当するぐらいだが、友の意志や同意なしに処分は決められないとする。プルーデンスは我が意を得たりと喜ぶ。忠告なしに和解するのは、忠告なしに戦争するのと同様ということである。
さてプルーデンスは少数の信頼できる者を読んで状況を説明し、どうすべきか助言を求める。彼らはよく相談した後、メリベウスが慈悲を与え敵を許すことで一致した。プルーデンスはこれを喜ぶと共に、使者を送って会見を調整するよう助言する。その通り事は運び、敵はメリベウスに謁見することになった。
さて時を移さず敵はメリベウスの館にやって来た。彼らは彼らで賢人の友を幾人か連れて来ていた。メリベウスは罰を受けるよう自分とプルーデンスの意思に委ねるか敵に問う。敵のうち賢い者が答えて、自分たちの罪を認め、メリベウスの支配に身を委ねる、ついては慈悲を願うと言う。この際彼らはメリベウスを「主君」と呼びかけており、傘下に入ることを申し出ているように見える。
メリベウスは優しい態度で彼らを絶たせて、判決日を決めて敵を帰す。頃合いを見てプルーデンスは、メリベウスにどうするつもりか訊く。
- メリベウス「相続権を奪い、永久追放にする」……赦すとは何だったのかと思うが、死刑や三族皆殺しでないだけマシという感覚なのだろうか。
- プルーデンスは、それは残酷で反理性的だと説く。
- 相続権:メリベウスは既に富んでおり他人の財産など要らないので、そんなことをすれば貪欲と言われる。
- 追放:彼らの支配権を得たことに鑑みれば、追放は理性を外れている。服従を望むならもっと寛大でなければならない。
- どうか自分の心に克っていただきたい(最後の審判を念頭に)。
メリベウスはプルーデンスにすぐ同意し、期日にメリベウスの前に現れた敵を前に、事件のことを完全に許す。
この悲惨な現世においてわれわれが神に対して犯した罪を神がその無限の慈悲の心からわれわれが死ぬその時に、お許し下さるようにとの願いをこめてである。というのも、(中略)神はわれわれの科を許し給い、われわれを終ることなき至福へともたらし給うことは疑いなきことであるから。アーメン。
総評等
事程左様に長い。しかもお気づきだろうが、章立て・部立てがなく、ダラっと続く。宗教的説教色が強く、現代人それも異教徒にいかほど楽しめようか、という気もする。また、ここで示された寛容はまあ多分やると敵に後で刺されて終わるだろうなとも感じる。そして、しばしば退屈だ。
とはいえ、メリベウス/プルーデンス夫妻が途中でちょっと喧嘩腰になるのはちょっと楽しかった。『カンタベリー物語』は社会的名誉が高い人物の話は、教訓を垂れるためだろうが登場人物が駒のようで人間味に欠けがちだ。この点で、社会的評価の低いorその誠実が疑われている人物による話の方が、登場人物が活きていて、現代人or異教徒でも楽しめる。だがその傾向にもかかわらず、高貴な登場人物にも人間味が感じられる場面がある。「メリベウスの物語」の一部もそれに該当する。嫌いじゃないです。
それはともかく、娘さんはどうなったんでしょうか。
*1:では致命傷なのか、ソフィエは死んでしまうのかというと、どうもそうではないらしい。何かの隠喩かもしれない。
*2:当時の医療水準を考慮して読むべきである。
*3:最高の善は神一人を除いて存在しないので、ソロモンの発言を根拠に女性を否定するのはおかしい、というロジックだ。
*4:そんなこと言ってた?
*5:だってわざわざ「これは、これは」とか言うんですよ。
*6:戦をする人は、イエス・キリストの守護がなければ身を守ることなどできないから、というロジックである。神頼みの優先順位が高いこの感覚は、日本の武将にもあったことだろう。
*7:高慢は七つの大罪なので、この指摘は現代人が思う以上に重いと解釈したい。
*8:ここでプルーデンスは、怒るのは愚かで、叱るのは価値ある行為、更には「愚か者は人の悲しみを見て行動を律する」とさえ言う。これメリベウスを愚か者と言ってません? いやあだいぶキレてますね。
*9:政治的な意見なんか死んでも読みたくない人は、この注記は飛ばしてください。岸田首相は女性を閣僚に任命するに当たり「女性ならではの感性で」と言ったわけですが、14世紀の中世人並みのジェンダー感覚なんだなと思いました。
カンタベリー物語 トパス卿の話/チョーサー
トパス卿は、巡礼団の一員ではない。話の当事者である。つまりトパス卿は、語り手ではなく登場人物に過ぎない。では「トパス卿の話」の語り手は誰かというと、巡礼団の中にいるチョーサーなのである。チョーサーはこの「トパス卿の話」と次回の「メリベウスの物語」で語り手を務める。ならば「チョーサーの話」で良いはずだが、作者自身の現身ということで、題名の時点から特別感があるわけである。
トパス卿の話の序
チョーサーへの宿の主人の愉快な言葉に注意せよ。
前回の尼僧院長の話、誰も彼もが厳粛になった。あの尼僧院長を邪悪と捉えない辺り、巡礼団の人々は皆同じ穴の貉だ。これが中世なのである。恐ろしい。しかしまあそれはとにかく、宿の主人が最初に立ち直り、チョーサーを見て、冗談を連発する。お前は何者だとか、兎でも見つけようとしている顔だとか、ご婦人衆が腕に抱くのにちょうどいい人形だとか、ぼんやりした顔だとか。そして、チョーサーが誰とも言葉を交わそうとしていないと言って、愉快な話をしてくれと頼む。チョーサーは、学んだ韻文の話以外は知らないと返し、宿の主人はそれで結構と話を促す。
ここにチョーサーのトパスについての話始まる。
第一節
チョーサーは、序で示した通り、韻文で話を進める。
まず彼は、美しく品位高い騎士トパス卿の、戦闘と馬上槍試合の話をすると切り出す。トパスはフランドルのポペリングで生まれた。長じて勇猛果敢、見目も麗しい若者になった彼は、夢の中で見た妖精の女王に恋をしてしまう。彼は馬に乗り、長く走り、荒涼たる地に妖精の住む国を見つける。そこにオリファウント卿という巨人が現れて、妖精の女王がここにいる、出て行かないと鎚矛でお前を殺すぞとトパスを脅す。*1トパスは明日勝負すると告げて、鎧を付けるために退却する。巨人は投石機で攻撃してくるがトパスはこれをかわす。
さてトパスは町に戻り、語り部に物語をさせながら、武具を装着する。この際のチョーサーのトパス卿の描写はまことに華麗である。
第二節
トパス卿が勇壮に進む様を、チョーサーは華麗に韻文で表現する。
自身は泉の水を飲みほしました。これはかの騎士ペルシヴァル卿が昔やったこと。甲冑をつけては並ぶ者なきかの騎士が。するとある日のこと……
トパス卿の物語は、ここでストップがかかる。なぜかって? 宿の主人が止めたからだよ!
ここで宿の主人はチョーサーにトパスの話を止めるように言いました。
「もうたくさん、たくさん、神様の威厳にかけてな」とわが宿の主人は言いました。「お前さんの無知ときたら、わたしを嫌というほど飽き飽きさせるぞ。わが魂を祝福下さる神様にかけて、ほんとのところ、わしの耳はお前さんのつまらなん話で痛んできたわい。こんなへぼ詩なんか悪魔にでもくれてやらあ! こんなのは腰折れの歌というものさ」
ボロクソである。もう詩(韻文)はいいから、散文で何か話してくれとチョーサーに言う。再挑戦の機会を与えるわけである。優しいのか何なのか。チョーサーは、一番いい詩のつもりだったのにと不満を漏らすが、散文で別の話をすることは了承する。そして、徳に至る教訓的な話をすると宣言する。ただ、福音書の作者*2が受難を語る内容が少しずつ異なるように、物語は語り手によって細部は変わるのだから、聞き手は自分が知っている物語とチョーサーの物語で言葉が異なっていても咎めないようにと予防線を張る。もちろん彼の言っていることは正しいのだが、なぜここまで言い訳がましいのだろうか。チョーサーの韜晦か? それとも……。
トパス卿の話は、まだまだ冒頭であったけれども、そんなに酷い話ではなかった。これはメタ的にはチョーサーの韜晦なのだろうか……と訝しく思い、少しだけ調べてみたところ、トパスはトパーズのことであり、物語は典型的な騎士物語のパロディであるという。恐らく同時代人にとってこれは聞けば聞くほど悪ふざけだと確信できる類のものだったのではないか。「尼僧院長の話」とはまた別の意味で、時代を越えられなかった何かがここにある。
総評等
パロディならパロディで良いから、最後まで語ってほしかったエピソードだ。トパス卿の恋の行方、巨人と騎士との戦い、どちらも気になってならない。
とはいえ、宿の主人の容赦ないカットには笑う。
カンタベリー物語 尼僧院長の話/チョーサー
尼僧院長の話の序
韻文調の文章が始まる。尼僧院長の話はずっとそうだが、物語に入っていない序の段階でも既にこれで、彼女の話が地の文になっている。登場人物としてのチョーサーの出番はない。
尼僧院長は主を讃す。イエス・キリストの名は出さないが、疑いなく彼のことを崇めている。主のことを「汝」と呼び掛けている。そして言う。イエス・キリストと、その母マリア*1を賞賛する話を物語ると言う。そして「歌か詩歌か?」というぐらいに、キリストとマリアをひとくさり賞賛する。
尼僧院長の物語ここに始まる。
舞台はキリスト教徒の住むアジアの大きな町である。ユダヤ人がある区域に住んでいて、君主の保護を受けていた。ユダヤ人はそこで、キリストやその信者たちのひどく嫌う汚い高利や、厭うべき利得を得ていた。
その町にはキリスト教徒の小さな学校もあった。小さな子供たちが幼年時代に学ぶような歌や読み書きが教えられていた。ある寡婦も七歳の小さな子供を学校に通わせていた。子はマリアの像を見たらアヴェ・マリアを歌うほど、寡婦はマリアを崇め敬うよう教育していた。子供も素直にそれに従っていた。
ある日、ラテン語で聖歌《救い主のやさしき御母》が歌われている*2のを聞いた。最初の歌詞を諳んじた子供は、年長の子に、歌詞を説明してくれと頼む。*3その結果、歌がマリアを称えるものだと知ることができた。それから毎日、彼は友達による、帰る道中でのこっそりした指導の元*4、この歌をすっかり諳んじ、道すがら歌うようになった。
さてこの少年は、ユダヤ人街を歩いている時もこの歌を歌った。ユダヤ人たち*5はこの歌を憎み、この少年を地上から追い払うことに決める。そして少年を捕まえて、喉を搔き切って便所の穴の中に投げ捨てた。いきなり凄惨な展開になって胸が潰れる思いだ。ユダヤ人に対する憎悪と偏見の全開にもうんざりです。
さて息子が帰って来ないので、母親は町中を探し回る。ユダヤ人街にも行ったが犯人である彼らは「知らない」と返す。しかし、母親はたまたま*6息子が投げ込まれた穴の傍で息子に向かって叫んだ。すると穴の中から《救い主のやさしき御母》の歌声が流れて来て、哀れな少年の遺体は発見された。町の長官も呼ばれて、かかわったユダヤ人は皆逮捕された*7。少年の遺体は僧院に運ばれたが、その間ずっと歌を歌っていた。後には長い行列が続いた。僧院で棺に安置された遺体は、母親がその前で失神するなどしたが、それでもなおミサの間中*8歌を歌っていた。僧院長は少年に、喉が搔き切られているのに何故歌えるのかと厳粛に質問した。すると、少年は、自分が死のうとしていた時にマリア様がおいでになり、この讃美歌を死に際に歌うよう言いつけられ、舌の上に種子を一粒置かれていった、この粒が取り払われるときにマリア様が自分を受け取りに来られる、と答える。修道院長が彼の下から種子を取り払うと、少年は静かに息絶えた。人々はこの悲劇に涙した。そしてマリアを誉め称え、この少年を大理石の墓に埋めたのであった。
尼僧院長は、最後に12世紀にユダヤ人に殺され国中を巻き込む大騒動になった、リンカーンの聖ヒューに触れて、話の中の少年もヒューと同じように虐殺されたのだとコメントする。
キリスト教を邪教だとは決して思わないが、この尼僧院長が信じている宗教は邪教であろう。ここで称えられている「イエス・キリスト」や「マリア」を騙るものは、肝心要の惨劇を止める能力を持たない、または持っていても発揮しなかった上に、死体が歌を歌うというクッソしょぼい奇跡で、この世を玩具にしているようにしか見えない。得られる教訓も、「マリアのマリアによるマリアのための奇跡がある」だけ。この「マリア」は邪神か悪魔に他ならない。こんなもんをありがたがる人間はどうかしている。尼僧院長、お前のことだよ。
総評等
尼僧院長は人間のクズ。語られる奇蹟が「死体が歌を歌う」だけでしょっぱいのは、神に現世利益を求めるなということと理解すればまあまだ納得できなくはない。しかし、ユダヤ人に対するこの強烈な偏見と憎悪に弁解の余地はないです。同時代ではどうだったのだろうか。
ということで、また悲惨な話だった。中世人や、敬虔なキリスト教徒にとっては、違うのだろうか。
*1:「かの白き百合の花」と表現される
*2:中世ゆえ、そもそも聖歌は所与の前提でラテン語である。尼僧院長の文章も「ラテン語で聖歌が歌われていた」ではなく、「聖歌が歌われていた。子供にはラテン語はわからなかったが~」といった表現を取っている。非ラテン語話者が聖歌を聞いてわからなかったために、たまたまたそう書かれて、私は「そうかこの時期は聖歌は必ずラテン語だから、現代と異なって、わざわざ書かないんだよな」と思い至れたというわけ。常識はわざわざ書かれないことが多い。
*3:何度も膝をついて頼んだと記されている。歌詞ぐらい教えてやれやと思うが、彼いじめにでも会っていたのだろうか。それとも、こういうのはなかなか教えない常識が当時はあったのだろうか。
*4:苛められてはいなさそうである。
*5:「われら人類の初めての敵、かの悪魔」とまで書かれていて、現代では完全にアウト。そして、中世で彼らがいかに生きづらかったろうと、凄く同情してしまう。
*6:尼僧院長は、イエス様がそのお恵みから、その場で声を上げさせるよう母親の心にふと思いつかせられたのでした、と、イエスの恵みであるかのように言う。じゃあイエス様は、なんぜユダヤ人が子供を殺害するのを止めなかったんですかね? ユダヤ人街を歌いながら歩くのを止めなかったんですかね? ユダヤ人を邪悪なまま放置しているのは何故なんですかね?
*7:後に拷問にかけられ、荒馬に引かれ、吊るし首にされた。
*8:葬送のミサと思われる。
カンタベリー物語 船長の話/チョーサー
船長の話ここに始まる。
サン・ドニに住んでいた貿易商人は金持ちで、ゆえに懸命な人だと思われていた。彼の妻は美しい人で社交好き、お祭り騒ぎが好きな性格だった。
この貿易商人の客人に、三十歳頃の修道僧ジョン殿がいた。彼は顔が綺麗で、貿易商人と同じ村の出であり、仲が良かった。修道僧は自分は貿易商人の親戚だと言い、商人の方もそう思っていた。そして兄弟の契りすら交わしたのである。ジョンはまた大変気前が良く、貿易商人の家の召使にも物を与えたので、家の者皆から好かれていた。
さてある時、貿易商人の家にジョンが来ている日の朝、貿易商人は会計事務室で仕事をしていて、彼の妻とジョン殿が庭でばったり出くわした、という機会があった。ここで妻はジョンに打ち明ける。亭主のせいで楽しくないと。出奔すら考えているという彼女をジョンは宥め、相談に乗ると言う。二人は、愛情と信頼からお互いこの相談の内容は秘密にすることを誓い合い、接吻して、なぜか愛情の告白のようなことまでする。
妻は、夫がケチだと言う。そして、夫の名誉――勇敢で賢く、金持ちで、気前が良く、妻に従順、寝床では新鮮――を守るために、次の日曜までに百フランが入用だ、だから貸してくれとジョンに頼む。御礼もすると言う。ジョンは、夫が予定通りフランドルに旅立ったら、その後で百フランを持って来ると約束する。
ジョンと別れた妻は会計事務室に向かい、まだ籠っている夫に、客のジョンを朝食でm渡しているのは変だから早く出て来るよう話しかける。夫は、仕事は大事だ(大意)、フランドルに明日の夜明けに出かけて行ってできるだけ早く帰って来る、留守は任せたが衣服・食料・財布の銀貨共に十分なものが家にはある、と告げて、食事のために部屋から出て来る。
食事後、ジョンは深刻な顔で、貿易商人に、家畜費用のため必要になったため、一週間か二週間、百フランを貸してほしいと頼む。貿易商はこれを快諾、すぐにこっそりとジョンに渡す。ジョンはそれを持って僧院に戻る。翌朝、貿易商はフランドルに向けて旅立ち、特に遊びもせず、現地では商売に明け暮れた。
貿易商が出かけて行った次の日曜、ジョンは貿易商のいないサン・ドニがやって来る。そして一泊して行った。約束通り、ジョンは妻を一晩中仰向けにして両腕に抱く。これは「文字通り実行された」とコメントされており、性交が行われたと解釈できるかどうかよくわからない。当時は誰もがわかった隠喩だったりするのでしょうか? 「彼らは夜通し歓喜のうちに忙しく過ごし」た、という表現もあるので、まあ多分やることはやってますけど。なお、貿易商の家の者で、ジョンを怪しんだ者は一人もいなかった。それまでに散々好かれていたからだ。
さて貿易商はフランドルでの買い物を成功裏に終えて、二万クラウンを支払う誓約をしたうえでご機嫌で帰って来る。妻と楽しく過ごした後、支払い資金を借りるために仕事でパリに行き、ジョンのいる僧院を訪ねる。ジョンに買い物の成功を語ると、ジョンは、自分がお金持ちだったら二万クラウンを貸してあげたのにと言った後、先日借りた百フランは奥さんに返したと言う。そして僧院長のお供で街から出ないといけないのでと、そそくさと面会を切り上げる。
貿易商はパリでの商談も成功裏に終えてご機嫌で自宅に戻る。そして少しして、妻に問いかける。自分が彼に貸した金ことを話すと少し機嫌が悪かった*1、ジョンが返済したのであればそれを自分に報告すべきであったと。これに妻はジョンに怒り出す。自分にジョンが百フランを貸してくれたものとばかり思っていた、まさか自分の亭主からの借金だったとはと。そしてそのお金は、夫の名誉のために、自分の着物に使った、浪費したのではないと強弁する。夫の名誉ってそういう意味だったのかよ! いや前口上的な部分で船長がそんなこと言ってたけどさあ。そして、ささもういいでしょ、お許しくださいね、こっちを向いて、と軽いノリで話を流そうとする。
その様子を見て、貿易商は為す術がないのを見て取った。彼は、二度とこんなに気前よく振舞ってはいけないと妻に注意するのがせいぜいであった。
なかなか面白い話だった。現代小説なら、修道僧はもう少し状況隠蔽の工夫をするだろうが、彼もまたそれをするほど悪人ではないことも示している。不貞はあったが、後味はなかなか良い。終始平和で何よりです。
地の文で、修道僧ジョンはほぼ言い関して「ジョン殿」「ジョン師」と表記される。皮肉が込められていると見て間違いあるまい。また、貿易商人が先物取引をやっているような描写もある。中世とはいえさすがに商人の業務内容それ自体は、今とあまり変わらないのかもしれない。
船長と尼僧院長に対する宿の主人の愉快な言葉を見よ。
宿の主人はうまい話だと誉め、船長のために祈り、修道僧(ジョン)のことは、夫も妻も愚弄したとして呪う。そして次の話者を求め、慇懃に尼僧院長を指名する。尼僧院長は快諾する。
*1:この直前の貿易商とジョンの会話にそのような描写は一切ない。描写がないことは起きなかったことだ、という発想が中世人チョーサーにはないのかもしれない。或いは、もっと深刻な何かを貿易商が疑っていて、そのため彼が能動的に嘘を付いているのか。