ギュンター・ヴァント/ケルン放送交響楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》
1977年3月、WDRグローサー・ゼンデザールでのセッション録音。このコンビは同年から1984年にかけてシューベルトの交響曲全集を録音している。90年代に入るとヴァントの録音は本人の意向でライブだらけになるが、この全集はセッション録音だ。また彼は、別のオーケストラと《グレイト》《未完成》と3番・5番を再録音したものの、他の曲は結局正規では再録音しなかった(演奏したかどうかも私は不知)。それらの意味で貴重と言えば貴重な録音である。
演奏は堂々たるもの。解釈面で特に変なことはしていないのだが、第一楽章コーダの序奏部再帰のちょっと前から目に見えてテンポを落とし、序奏部主題の再帰箇所がテンポの点でそれほど孤立しないように処理するのはなかなか面白い。そして「これは故意にこう弾かせているな」という拘りが垣間見れる場面――つまり何となく弾いているのではなく、はっきり意図・意識しながら弾かれている箇所――が本当にずーっと続く。ヴァントらしく、指示が大変こまかいのである。ニュアンスの付け方も実に緻密である。振る方も弾く方も、よく集中力がもつなと思います。ただし全体の流れは非常にスムーズで、《部分への拘り》によって阻害されることは全くない。これもまたヴァントの拘りなのであろう。あと表情が基本的に真面目かつ暗めで、オーケストラも美感最優先ではなく、総奏はかなりゴツゴツしていて、時々岩山を見ているような気分にさせられる。これはケルン放送交響楽団が、超一級のアンサンブルでないことも影響しているのだろう。腕は北ドイツ放送交響楽団よりも下と見た。もっとも不満が出るというような「下」ではない。これ以上のオーケストラが複数あることを知っている、程度の感覚である。というか、ケルン放送交響楽団の響きは、これはこれで味だとすら思ってます。スケールはそこまで大きくないのだが、指揮者の意志の強さは見紛いようがない。《頑固なシューベルト》が聴ける、良い演奏でした。
せっかくなので交響曲全集全体についてもコメントしておきます。基本的に《グレイト》と同傾向の演奏で、精妙な演奏ながら後年に比べて緩く、オーケストラも注意深く鳴ってはいるけれど、微妙に反応が鈍い。この緩さと鈍さが意外や魅力に転化しているのも同じである。なお演奏の様式感は統一されており、6番までと《未完成》以降で雰囲気をわざと分けるようなこともしておらず、偉大な作曲家の素晴らしい交響曲群ということで、どの曲も立派に演奏されています。にもかかわらず1番から6番まで演奏の方がオーバースペックだという感じが全くしないのは、ヴァントの芸風の(意外と言えば意外な)汎用性の高さを物語っているのでしょう。
交響曲第1番の第1楽章では提示部の最後の方で聴き慣れない音型(オクターブ高い感じ)が現れて驚かされた。カラヤンも全集録音の際に同様のことをやっているが、他で聴いたことが(今のところ)ない。これ、楽譜のヴァージョンが違うのか、それとも指揮者自身あるいは他の音楽家による改変なのか。知りたいのは山々だけれど、どうやって調べたらいいのやら途方に暮れております。実は意外と有名な根拠があって、俺が無知をさらけ出し赤っ恥かいているだけという可能性が一番高くて怖いけど。
グイド・カンテッリ/NBC交響楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》
1953年12月27日、ニューヨークでの録音。モノラル・ライブだがオーケストラの性質上、ラジオ放送を前提とした収録と思われる。
基本的には常識的な解釈に基づいており、その点での特色はないが、力強さがあってなかなか素敵だ。カンタービレがよく利いている(1920年生まれなのにトスカニーニの後継者と目されただけのことはある!)けれど、そこに硬質性が見られるのは、振っているオーケストラの性質かもしれない。まあこれについては、トスカニーニ以外の指揮者が振った録音をあまり聴いていないので確かなことは言えませんが。残響があまり入っていない録音(または会場の性質)のせいかも知れませんしね。
第一楽章はほんの少し遅め(堂々とした印象を決定づけるに当たり、この楽章のテンポ設定は大きくものを言っている)、第二楽章は速め、第三楽章と第四楽章は普通と、まだ33歳なのに意外とスピードで聴衆を煽り立てることをしていない。ただ音自体は相当熱いようで、フィナーレではまだ音が鳴り終わっていないのに拍手が始まってしまう。演奏自体が相当エキサイティングなものに(実演では)聞こえたということではなのでしょう。力感満点というのは、録音でもちゃんとわかりますし。ただし細部のニュアンス付けは、それほど魅力的・蠱惑的には行っておらず、第二楽章や第三楽章トリオは純粋にまっすぐな歌で押していて、寂寥感その他には乏しい。それが不満ってわけじゃなくて、ちゃんと押し切れているのはカンテッリの才能を証明するものだと考えます。
カップリングは、1953年1月3日の《未完成》と、1952年2月2日のヴェルディ:《運命の力》序曲である。どちらも《グレイト》と同傾向の演奏だが、《未完成》だとさすがにまだ味わいが不足しているように思われる。しっかりした力強さは感じられるので、聴いてられないとかそんなことはないですが。そして《運命の力》はカンテッリの本当のレパートリーという感じがするぐらい、曲想と芸風がピタリとはまっている。テンポが若干遅めなのは意外でしたが。彼が1956年の航空事故に遭わなければ、少なくともジュリーニ以降のイタリア人指揮者の国際的キャリアは、結構な影響を受けていたのではないかななどと思う。
ゲオルク・ティントナー/シンフォニア・ノヴァ・スコシア シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》
1988年2月10日のライブ録音。演奏場所についてはCDに記載がないけれど、オーケストラの本拠地でやってるのであれば、ケベック・シティーのホールでしょうなあ。残響および拍手の響き方からすると、ホールはそれほど大きくないと思います。
オーケストラのヘボさが致命傷の域に達した演奏で、終始、「貧相な演奏だなあ」という感覚が付きまとう。下手さが味に繋がってれば良いのだが、そういうわけでもないのです。ただし、そのヘボさは音楽を馬鹿にしてのものではなく、彼らなりに必死で頑張った結果であるのはしっかり伝わって来ます。弦の人数が少ないのは間違いないですが、それに加えて木管も金管も音が痩せており、オーケストラに金がなくて良い楽器が使えていないのかも知れないな、なんて思いました。ティントナーの解釈は至って標準的で、感心するところはない代わりに「この解釈はないだろ」という箇所もない。印象的なのは、全ての楽想を慈しむように奏でさせている点。よってオーケストラの安っぽい響きが気にならない箇所では、なかなか魅力的な音楽に聞こえます。しかし基本的に楽器の音の一々に魅力がなく、力感も明らかに不足していて、全体的には具合が悪いと言わざるを得ない。弁護しておくとすれば、もう少し大きな編成のオーケストラだったら、話が違って来た可能性があるということぐらいかな。実際、NAXOSのブルックナーは悪くないわけですし。各楽章とも、クライマックスで意外と見栄を切っていて、それらの箇所がこんなにショボいサウンドでなければ、印象が変わっていたかも知れない。力感を込めよう込めようとしている箇所で、絶望的に薄い響きしか出て来ないのは、ティントナーがちょっと可哀そうでした。このクラスのオーケストラしか振れない名声しか得られなかったのだから仕方ないが、やっぱりオーケストラはヘボいと駄目という当たり前の、だけれどつい忘れがちなことを思い出させてくれます。ただし、落ち着いてる演奏で、変なことも特にしておらず、下手とは言ってもずっこけるような大崩れはしていないので、疲れた時に何気なく聴いてみると結構良く聞こえたりするかも知れません。
カップリングは1990年12月12日の同じオーケストラによる《未完成》ライブ。演奏の方向性も全く同じですが、こちらは曲想が曲想だけに、楽想を慈しむスタンスがよりハマっています。ちょっと柔らか過ぎて、強奏部が本来果たすべき「楽曲全体におけるアクセント」の役割がちゃんと出ていないですけれども。
ヨーゼフ・クリップス/ロンドン交響楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》
amzn.to
1958年5月、ロンドンのキングスウェイ・ホールでのセッション録音。
クリップスは「戦争直後のウィーン楽壇立て直しに尽力した」みたいな言い方で紹介される指揮者だが、その割にはウィーン・フィルに重用された印象が薄い。非ナチ化処理が済んだ指揮者が戻って来ると、そっちの方に人気が戻ってしまったんでしょうか。ただ、別に縁が切れたわけではなく、1972年に物故するまで共演の機会はそれなりにあった模様である。実際、この《グレイト》のカップリングは1969年3月にウィーンで録音された、ウィーン・フィルを振っての《未完成》ですからね。
演奏はなかなかのもの。基本的には職人芸の世界で、ちょっと速めのテンポで進行する音楽を、細かいところまでよく彫琢しており、バランスを破ってまでではないが、どのパートもしっかり目立つ。ハーモニーはむしろ角張っているとさえ言える*1のだが、リズムが軽めで旋律もスムーズに流れるよう注意が払われており、特に硬質なイメージも喚起せず、《グレイト》に対して人が抱く「一般的なイメージ」を逸脱することはまるでない。クリップスはこの時期の伝統的ドイツ人指揮者とは異なって、重低音をベースとしたピラミッド型のオーケストラ・サウンドを採用しておらず、高音・中音・低音に大変平等に接するのも、この点に強く貢献している。要は、ドイツロマン派の濃厚な味付けは為されておらず、シューベルトを古典派の延長線上に捉えているということである。それでいて、古典派に比べて明らかに息が長くなっている旋律線の処理に困っている感が微塵もないのは、クリップスが有能な指揮者だったことを証明している。どことなく雅な空気感すら漂っているような気がするのは、クリップスがウィーンの音楽家だからか、それとも事前情報としてそれを知っている私の思い込みゆえか。ロンドン交響楽団も実にいい仕事をしています。誰だよイギリスのオーケストラはつまんないなんて言ってたの。
カップリングの《未完成》は、ウィーン・フィルとの演奏である。と言ってもクリップスのやることは変わらず、古典的な造形感で曲を処理しているため、情緒纏綿では全くなく、雅な雰囲気をふわりと漂わせつつ、締まった音で綺麗にまとめられている。普段着だけれどその普段着がカッコよくて、ああこの人は本当にお洒落なんだなとわかる。そんな感じの演奏である。
*1:これは初期ステレオ録音のせいかも知れません。
チャールズ・マッケラス/スコットランド室内管弦楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》
1998年3月10日〜12日、ダンディーのケアード・ホールにおけるセッション録音。
まるで古楽器を用いた演奏であるかのように、ビブラートが非常に薄い。弦の人数が少なめなこともあって(室内管弦楽団ですしね)、ハーモニーはざくざくしている。ただしそれがショッキングな響きを生んでおらず、ノリントンのピュア・トーンのような輝きも生んでおらず、サウンドがあくまでシックにまとまっているのが特色だ。マッケラスはこの音を用いて、速めのテンポ設定でさくさくと要領よく演奏を進めていく。熱気はさほどなく、活きは良いし愉悦感に満ちているし音はビタビタ合っているものの、聴き手の精神状態を高ぶらせはしない(あるいは逆に鬱に引きずり込んだりもしない)演奏である。代わりにニコニコ聴いていられるわけだ。もちろん、第二楽章を筆頭に、適度な憂いは付与した上での話である。あと、ここぞというところでアクセントを上手く使い、おっと耳をそばだてさせられる。ド迫力で聴き手を圧倒するというよりは、ここで局面が変わりますよ的な注意喚起に近いように思います。
スケールの点では「小さい」と言わざるを得ない演奏だが、箱庭のようで結構可愛いし、曲やオーケストラ・サウンドの魅力に感じ入るのも確かである。「普通にいい演奏」というのはこういうのを指すのだと思う。
カップリングの《未完成》も同傾向の演奏。メロディー・ラインの特色がより強い曲である分、「小ささ」はさらに目立っていると感じますが、必要十分なことはしっかりやっています。普通にいい音楽だと思う。
コリン・デイヴィス/シュターツカペレ・ドレスデン シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》
1996年7月2日〜4日、ドレスデンのルカ教会でセッション録音されたもの。1994年、1995年にも同じ場所でセッションが組まれて、シューベルトの交響曲全集が完成している。
序奏のホルン独奏からしていい音色、その後の木管も素晴らしく、弦の響きもこれ以上ないぐらい魅力的、金管にも独特のニュアンスがあって、打楽器はそれらにぴたりと寄り添う。主部になるや(テンポ自体はそれほどで速くないが)大いに運動性を感じさせるととも、美感は全く同一水準の素晴らしいものに保たれている。堂々たるスケール感、しっとりした歌、沈着でいながら盛り上がるべきところでは迫力満点に盛り上がり、熱気も感じさせる。細かいところもしっかり弾かれ、その一々が魅力的な音色で為される。素晴らしい。本当に素晴らしい。
魅力の源泉は複数あるのだが、そのうち最大のものは間違いなくシュターツカペレ・ドレスデンの、無上に素晴らしいとしか言いようがない音色である。このオーケストラとウィーン・フィルは音色の点で他のオーケストラとは隔絶された評価を誇っている気がするわけですが、ウィーン・フィルが意外と鋭くて光り輝いているとすれば、ドレスデンはとにかく柔らかくてどのパートも悪目立ちせず一つの楽器のように鳴り渡る。その特性が余さず発揮されており、どの一瞬を切り取っても魅惑的なサウンドに仕上がっている。コリン・デイヴィスはこの音色自体は邪魔せず、細部のニュアンスはオーケストラに任せているような気もするが、全体を見事に掌握している。どっしり構えて下手にテンポを動かさず、軽さに傾くこともなく、細部をクローズアップしたいとの誘惑にも打ち勝って、見事なまでに正攻法の解釈で締めくくっている。歌い回しも特に変なことはしておらず真っ当極まりないが、それにオーケストラが積極的にニュアンスを付けていくので、とにかく魅力たっぷりである。もちろんオーケストラに主導権が取られているわけではなく、ちょっとだけもっさりした音楽の動きはまず間違いなくデイヴィスの指示によるものだ。リピート指定は忠実に守っていて、それで演奏時間が1時間強と大変なことになっているが、全くだれない。正直、どこから指揮者の解釈でどこから楽団員の積極性発露なのかわからない箇所もたくさんある。指揮者とオーケストラの理想的コラボレーションの一つと言えるだろう。そして最終的には、《グレイト》という名曲のほとんど奇跡的な素晴らしさが立ち現われてくる。けだし名演である。
他の曲も同傾向。《未完成》はともかく、他の曲がこれだと重過ぎるんじゃないかと思われそうですが、そこは全く問題ありません。ドレスデンの温かく柔らかい音色による包容力を舐めてはいけません。あとテンポ設定はかなり常識的で、走るべき所は走ってくれます。よって天馬駆けるごとくの、ふわふわかつストレートな演奏が全ての曲において楽しめます。だいいち、コリン・デイヴィスはモーツァルトも得意とした指揮者で、そこら辺に抜かりがあるはずはないわけです。実際、このオーケストラと組んだモーツァルトの交響曲集(フィリップス。今はデッカですね)も素晴らしいんだよなあ。あ、《未完成》はとても優美で、悲しげに演奏されております。ドレスデンの性質を完璧に活かしているのは他の曲同様。というかホント、オーケストラが素晴らしい。
この交響曲全集は、《グレイト》も含め、極めて優れた演奏だと思います。デジタル録音のクリアな音質で楽しめることもあって、交響曲全集全体としても超オススメの逸品。こういう演奏をしたデイヴィスも、もうこの世にいないんだよなあ。
レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》
1967年、エイヴリー・フィッシャー・ホールでのセッション録音。
よく弾みよく歌いよく鳴る活き活きした演奏だ。弾けるような生命力が全篇に横溢していて、聴いていて実に楽しい。楽団員もやる気満々で、細かい箇所に様々な表情付けすらおこなう。これはアメリカのオーケストラ――たとえばこのブログで《グレイト》音盤鑑賞の一環として取り上げた、ミュンシュ盤でのボストン響やジュリーニ盤でのシカゴ響、そして実演で聴いたマゼール指揮下およびマイケル・ギルバート指揮下のニューヨーク・フィル――で見られる、指揮者の意図には真面目に従うが個々人のプレーにはそれほど表情がない演奏とは決定的に異なる。またトスカニーニ指揮のNBC交響楽団が見せた、指揮者の無茶な要求にしゃかりきに応える必死さも薄い。どこまでバーンスタインの指示でどこから自主性なのかがわからない。というよりも渾然一体となって一緒に音楽をやっている。これが本演奏最大のミソということなのだろう。バーンスタインは楽団員を乗せるのが実に上手い*1。
特色としては、リズムがよく弾んでおり、第一楽章と第三楽章主部は楽しげだ。一方で、第二楽章の寂しげな歌もばっちり表現、第三楽章トリオも憂いを混ぜ込んで万事遺漏なしだ。基本テンポは速めで、それが快活な印象を強めるのだが、旋律を歌い込むべき個所ではさり気なくテンポの変化も付けている。また場所によってはレガートの付与、デュナーミク変化など、楽想の変転に伴いやり方を微妙に変えて来る。上手い。心憎い。もちろん情感に不足は全くなく、最初から最後まで充実した演奏が繰り広げられる。技術面でも全く問題はない。録音状態も上々だ。要はどこもかしこも素晴らしいのである。バーンスタインがいかなる名指揮者だったか、これ以上ないほどはっきり示した演奏である。
なおこの録音を私はバーンスタインのシンフォニー・エディション(60枚組)で聴いたが、このセットは本当に交響曲しか入れていない。交響曲全集とかを録音する場合、カップリングで序曲や前奏曲その他の管弦楽曲を用意するのはよくあることだが、そういうのが一切ない。「交響曲」のみで全CDが構成されている。この徹底ぶりはなかなか好ましいことである。
*1:もっとも、彼のやり方が通用しないオーケストラもあったようである。
オトマール・スウィトナー/シュターツカペレ・ベルリン シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》
1984年9月20日〜24日、東ベルリンのイエス・キリスト教会で録音。なお1983年から86年にかけてこのコンビはシューベルトの交響曲全曲と《ロザムンデ》の楽曲の一部を録音しており、《グレイト》録音もその一環ということになる。
解釈は最初から最後までおおらかでまろやか。後ろ倒しのリズム感と、滑らかな楽句処理をベースに、堂々と構えて雄大なランドスケープを展開し、この交響曲を雄渾・壮麗にまとめ上げている。ただしテンポは意外と速めだ。性急な感じは全くしませんけれど。細部に拘ってオーケストラを締め上げることはせず、音楽の盛り上がりや盛り下がりはあくまで楽想に従って自然かつなだからに為されるため、急激な雰囲気変化がまるでないのも特徴である。よって、恐らく第一楽章主部の最初の10秒*1が気に入れば、演奏全体でも絶対に満足できるはずである。あとは全部そんな感じなんで。特筆すべきはオーケストラの鳴りである。とにかく美麗! ハーモニーも個別の音も何もかもが極上で、聴き手を酔わせてくれる。スウィトナーがここまでおおらかな音楽作りをしているのは、ことによると、このサウンドを堪能させるためではないか。そして、このサウンドがありさえすれば、絶対に素晴らしいシューベルトになると確信しているからではないか。そんなことを考えさせられるほど、シュターツカペレ・ベルリンの音が素晴らしい。それに録音もいいんだ。教会ということで残響は強いけれど、それがまたいい味を出しているし、また残響に負けて音がブレンドされ過ぎていることはない。どの楽器もクリアに録れてます。
他の曲も同傾向の演奏である。すなわち、リズムは後ろ倒し気味で、音楽の進行は滑らか・なだらかだ。細かい部分での仕掛けはほとんどなく、全体の流れを最重視しており、オーケストラはひたすら美しく壮麗に鳴り渡る。テンションの上昇や下降も、音楽の流れに沿って徐々に為されるため、「急に様子が変わる」場面はない。教会が録音場所ということで、残響がいい仕事をしているのも同じである。《未完成》《グレイト》と同じようなノリで初期6曲も演奏されるが、不足感や過剰感が全くないのが面白い。スウィトナーの解釈が確かということなのか、その芸風の汎用性が非常に高いのか、俺たちの曲へのイメージが間違っていたということなのか……。あと《未完成》は、特別なこと何もしていないのに、これだけの美音&美録音で鳴らされると、絶句するぐらい優美になってしまうんですよねえ。とにかく素晴らしい全集である。この中で私が一番気に入っているのは《ロザムンデ》の序曲。実は私これ大好きな曲なんですが、たぶんこのスウィトナー盤が一番しっくり来ます。
*1:序奏の最初の10秒を挙げないのは、序奏のテンポが主部に比較して速いタイプの演奏だからである。どんな演奏でもそうだが、この曲の場合、序奏のテンポ設定の意味は主部を聴くまではわからないので、序奏だけ聴いて判断を下すのは一番やっちゃいけないことである。
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》
1953年9月15日、ベルリンのティタニア・パラストでのライブ録音。RIAS録音集成の1枚である。
あの1942年盤と比べたら落ち着いており、テンポが強烈に変転する場面ももちろんあるのだけれど、寛いだ風情や伸びやかな表情がそこここに頻出し、呼吸感も深まった。メロディーの歌わせ方に《未完成》よろしく浮遊感があるのも特徴で*1、ドラマティックな要素は十分に残しつつも、夢見るような感傷性が強く出ているのが特徴となっている。1942年盤ではほぼ感じ取れなかった雄大さも加わった。1942年はもっと必死でもっと硬質で、(変化はめちゃくちゃ付けていたけれど)感情表現としてはストレートであった。しかし11年後、歳をとっただけではなく、国・社会・ベルリンの状況が全く変わった今、同じような表現はできなくなった、ということなのかも知れない。フィナーレでも煽るだけじゃなくなっていて、もっと多様な表情が付与されているのである。エキサイトできる演奏ではないが、代わりにより落ち着いて聴けます。至芸感が強いとでも言おうか。ベルリン・フィルが好調でほとんど崩れていない(出で若干ずれるのは、指揮者が指揮者だから仕方ない)こともこの演奏の価値を高めている。
なお、テンポを加速させたり減速させたりする箇所が、1942年録音とほぼ同じなのは、フルトヴェングラーが意外と即興的ではないことを示しているようで、興味深かったです。先述の通り、受ける印象がほぼ別物なのも、なかなか面白い。演奏行為というものについて考えさせられます。
マルク・ミンコフスキ/レ・ミュジシャン・ドゥ・ルーヴル シューベルト:交響曲第8番ハ長調《グレイト》
2012年3月、ウィーンのコンツェルトハウスでのライブ録音。同月同会場で一気にライブ収録した交響曲全集の中の1枚である。以下、全集の他の曲も聴いた上での感想。
オリジナル楽器を使っており、ピッチは低く、音は基本的に軽い。テンポは中庸で、意外なことに第一楽章コーダの序奏部主題回帰のところはぐっとテンポを落としている。テンポも第一楽章はさほど速くなく、第二楽章も速くない。第三楽章とフィナーレも、とりたてて快速とは言えないテンポである。そしてフィナーレは提示部のリピートを省略している。そして表情は概ね真面目なものである。彼らのハイドンの《ザロモン・セット》に比べると、真面目ぶりは明らかである。シューベルトの本拠地たるウィーンに乗り込んでのライブという事情もあるかも知れないが、それよりも合理的な推測は、古典派でミンコフスキがよく見せる愉しげな演奏を志向しておらず、一つの大曲として正面からしっかり弾き切ろうとしている、というものだろう。既に古楽器が「それ自体」で表現になる時代は終わった。古楽器もただの表現ツールに過ぎず、この《グレイト》は、古楽器を使いつつ、常識的な範疇の音楽作りをしようと試みたのかも知れない。
とはいえもちろん、演奏がつまらないわけではなく、どこもかしこも標準的な解釈ばかりというわけではない。第三楽章とフィナーレでは、おっと思うアクセントの付け方やイントネーションが出て来て面白かったし、第一楽章のラストはまるで《王宮の花火の音楽》のようなサウンドが聴かれてこれも面白かった。前者は指揮者の個性的解釈に相違あるまいが、後者は古楽器でこの曲をしっかり演奏するとこうなるという楽器の持ち味かも知れない(もっともオリジナル楽器を使ったら必ずこうなる、というものではない)。あと、これは恐らく故意に近い彼らの個性だと思うが、音が大変にふわふわなのである。メレンゲ、マシュマロ、中華料理の卵白仕立て、そんな感じの食感を想起させられるほどの聴感である。これがシューベルトには結構合っていて、夢見心地気分を倍加させる。だからこそ、先述のアクセントやイントネーションが効果をあげるのだ。というわけで魅力的な演奏ではあるのだが、ただし、ミンコフスキならもっと官能的かつ愉悦感に満ちた演奏ができたんじゃないかという思いを拭いがたいのも事実。実演を聴いてしまっているコンビだから、要求水準を高めてしまうんだよなあ。音盤の聴き手としては良くないことです。あと、ミンコフスキがモダン楽器のオーケストラで《グレイト》を振ったらどうなるか、聴いてみたい気がします。
なお全集の他の曲では、《未完成》が同じく真面目で曲想も考えてか幽玄な雰囲気に満ちた良い演奏であった。6番以前は、ハイドンの時ほどではないけれど、《未完成》や《グレイト》に比べると、より表立って明るく楽しげに演奏している。きりりと引き締まりつつ、どこか鄙びた古楽器のサウンドが、楽曲にえもいわれぬ味わいを醸し出す。私は大好きです。《未完成》や《グレイト》ではそこまで大好きと言えないのは、それまでの6曲と性格が異なるので、ミンコフスキの方法論が通用しづらいということなのだろうか。
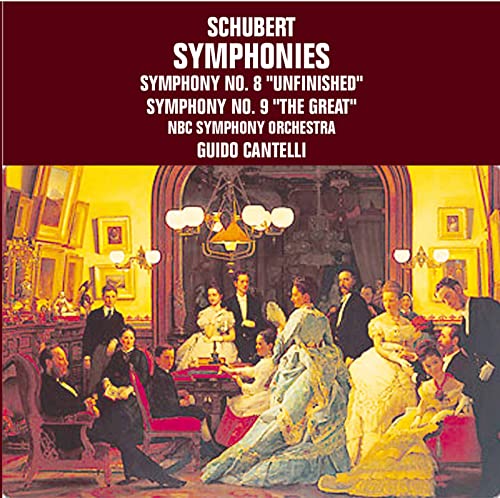






![F.シューベルト : 交響曲全集 (Schubert : Complete Symphonies / Marc Minkowski, Les Musiciens Du Louvre ・ Grenoble) (4CD) [輸入盤] F.シューベルト : 交響曲全集 (Schubert : Complete Symphonies / Marc Minkowski, Les Musiciens Du Louvre ・ Grenoble) (4CD) [輸入盤]](https://m.media-amazon.com/images/I/51UFPo43QDL._SL500_.jpg)