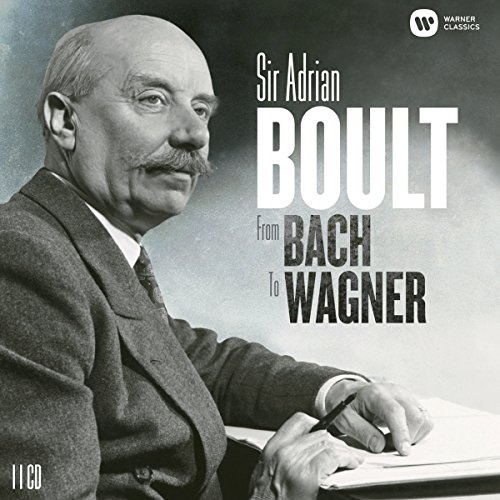エイドリアン・ボールト/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 シューベルト:交響曲第9番ハ長調《グレイト》
1972年5月28日〜30日、ロンドンのキングスウェイ・ホールでのセッション録音。
堂々たる演奏である。全体の設計図をおおまかに書いて、それに沿って拘るべき所にはとことん拘りつつ、奇矯な解釈は一切排除されている。温かい雰囲気が支配的だが、第一楽章やフィナーレの両コーダや展開部などでは、かなりの迫力を出している。つまり、やる時はやるというわけで、弦のうねりを有効活用して全篇にわたって雄大なスケール感を醸し出しており、その威容には圧倒されます。しかも常識的なテンポを採用している割には呼吸が深く、じっくり冷静に聴いているつもりでも自然と演奏に引き込まれ、いつの間にかがっちり心を掴まれてしまうのだ。全体的には包容力で勝負した演奏と言えるが、木管群の音色を目立たせての細部のニュアンス付けも見事に決まっている辺り、さすがベテランというか、英国内にほぼ限定されていたとはいえ《名声》を獲得した指揮者の実力の何たるかを遺憾なく見せつけてくれる。特に素晴らしいのは、総奏とその直前/直後の対比である。強音から弱音、弱音から強音への切り替えは毎回とても巧みで、一々ハッとさせられる。強弱の対比それ自体にこんな情報量があるなんて……。オーケストラの総奏の次の瞬間、木管がソロで音を出す箇所などは、取り残されてしまったようでいかにも可愛く、また哀しげである。で、こんなこと毎回やってたら音楽の流れが寸断されそうなのだけれど、実際は全くそうなっていない。これは録音人の腕の良さもあるかも知れません。
こういう演奏はありそうでなかなかなく、実際これを聴くまでにこのブログで40種類以上の演奏に接して来ましたが、このタイプのは皆無だった。拘っている部分はあるけれど、それは特殊な解釈とまでは言えず、むしろ今まで気付いていなかった魅力に気付かさせてくれる感が強い。もちろん、そのために色々手を尽くしてはいるわけで、よって朝比奈隆ほど無為ではないという点でも「普通の」指揮者ではある。しかし、こういう演奏はボールト以外では聴いたことがない。実に説明の難しい指揮者だなと思う。第三楽章は本当に普通に演奏しているだけなのに、どうだろうこの立派さは!
ただし彼の芸風のコアが、今や絶滅危惧種となった《職人芸》にあることは間違いなく、ベームほど「ブロックの積み上げ」感はありませんが、基本をしっかり押さえて、デフォルメは避け、音楽を立派に鳴らそうと、入念に組み立てた解釈なのは間違いないと思います。常識的な譜読みでも、しっかりやりさえすればここまで行けるのだ。もちろんオーケストラを乗せることは前提となり、この録音でも、ロンドン・フィルが実に気合の入った演奏を披露している。アンサンブル全体の出来はたとえばベルリン・フィルに比べると劣り、ザッツが緩い場面はありますけれど、代わりに指揮者の指示通りに意思統一が図られていて、不満は全くありません。